|
ピリカベツ川で
95年の五月下旬から六月末にかけて、北海道の道南地方を渓流釣りや山歩きなどの野遊びを目的に一人旅をしたときに出会いのあった、きたきつねの話です。
函館から国道五号線を北上して渡島(おしま)半島の東海岸を内浦湾沿いに百キロほども走れば、長万部(おしゃまんべ)町の国縫(くんぬい)というところに着いた。国縫で左折して国道230号線を西に走り、ちいさなピークの美利河(ぴりか)峠を越えれば美利河湖畔の集落をみて、湖畔沿いの林道を北上するとピリカベツ川に行き当たった。ピリカベツ川は長万部岳に源を発する後志利別(しりべしとしべつ)川の源流域にある一つの支流である。
長年のあこがれの地、北海道の渓流河川に始めて釣り糸を垂れる渓流は、ここピリカベツ川にしようと、取り立てた根拠もなしに地図を広げて眺めているうちに、そう決めていたことであった。
それに、この日の最大の関心事は、始めて釣る北海道の渓流魚に対して、私のテンカラ釣り (毛鉤釣り) の腕前と自作の毛鉤がはたしてどこまで通用するのかを問うものであった。
ところが、この日の結果は、いままでに長年にわたって釣り歩いてきた山陰地方から近畿北部の渓流、北陸地方の渓流河川、東北地方では朝日・飯豊連峰の渓流などでの山女魚釣りや岩魚釣りと同じように、渓流魚特有の毛鉤に躍りかかる大胆かつ俊敏な動作や渓流魚の習性にはなんらの違いも違和感もなかった。むしろ、勝手が違うという思いを強くしたのは渓流の河川形態には大きな差異があることであった。傾斜のゆるい流れがゆるゆる・ながながと続いて、瀬か淵かの境目がはっきりしない渓流が滔々と続いているために、渓流魚が居つく場所を見極めての釣り場の選定に戸惑いを感じる、そんな印象を強く受けたのであった。
|
| 釣果のほうは短時間で型の良い山女魚を釣って、今日の昼食と夕食に食べきれる分だけを魚籠に入れ、それ以外のものは元の流れに返してやった。予期せぬ幸先の良い釣果と自分の釣り技への確かな手応えを得て、このあとの、この旅での楽しみや渓流釣りへの興味を一層増幅させてくれる展開へと進展するであろうことを予期して、やたらと興奮を覚えるのであった。 |

|
ピリカベツ川沿いの林道を走って最奥にある、鬱蒼とした原生林に囲まれた奥美利河温泉の苔むす岩肌の露天風呂でゆったりくつろいだあと、林道を少し下ったピリカベツ川を跨ぐ橋のたもとから開けた河原へ車を乗り入れた。そこを今夜の野宿場と決めた。
早い流れが山裾の大きな岩盤に突き当たって流れを大きく屈曲させている。その下流側には広い河原が展開している。一帯にゴロタ石を敷き詰めて、石の隙間からは野草の新芽が伸びだしている。まばゆいばかりの陽の当たる河原では新緑の山斜面に囲まれて清々しい緑風が射るように頬を撫でていく。
遅い昼飯の炊飯にとりかかり、まずは今日の獲物の山女魚を塩焼にした。焼きあがった山女魚を酒の肴にしながら飯盒の飯が炊きあがるのを眺めていた。
そこへ、きたきつねが現れた。唐突に何の前触れもなく不意のお出ましであった。その場の雰囲気に何の不自然さも警戒心もない、お互いの存在を既知の仲としているような出遭いであった。山女魚の塩焼きの匂いに誘われて森から出てきたのだろうか。
私の真正面の近くに立ち、私の顔をじっと見つめている。目を反らしたかとおもえば数歩あるき、立ち止まってチラッと見てあたりをうろついて、立ち戻ってきた。じっと私の目を見つめて動かない。 |
山中深くに棲んでいるためか野生の粗野な風貌は見てとれるが体毛には艶がない。動きは静かで落ちついている。老狐だろうか。鼻の回りの黒い斑紋を頂点にした逆三角形の顔に大きな両耳をピンと張り、黒ずんだ目緑の眼窩は吊り上がって双耳に向かっている。眼は褐色のビー玉に似て鋭い。顔面を下げてうわ目遣いで睨む目は野生の凄む鬼気を見せもするが、顔面を上向けて私と向き合えば気の許せる懐きも感じさせる。澄んだ野生の目で「そうか、これがほしいのか?」
「・・・・」
食べ終えた山女魚の頭と骨をそっと地面に置いてやる。静かに足元に寄ってきて瞬く間にたいらげた。じっと私を見つめて、もっと呉れと目が催促をしている。山女魚の身肉をつけたままのをまるっぽで与えた。それもガツガツとすぐに食べ終え、次のものを催促する。 |
|
「もう、おしまいや。もう山女魚は無くなったのや。・・・・」
食事を続けたが、きたきつねは一向に立ち去ろうとはしない。つぎのものを呉れという目と動きに根負けして「この川の山女魚やから、おまえも相伴する権利が有るのはわかるけれども、もう無いのや。・・・夕飯時には君の分も焼いておくから、夕方になって山女魚を焼く匂いがしたらまた出ておいで」
じっと私の口もとを追う目つきで見つめていたが、次のものを催促している。
「しようのない奴やなあ・・・。今晩はこの場所で野宿をさせてもらうから、君のなわばりで厄介になるのだから場所代ということで、いいものを奮発しよう・・・・」
長万部の町で買ってきた竹輪を取り出し、ナイフで輪切りにして与えた。竹輪の二三切れは味わうように喰った。そのあとの口許の動きがどうもおかしい。口に入れても噛まないでつぎつぎと拾い上げて口の中に蓄えているのだろう。つぎのものをくわえようとして口を開いたとたん口の中から竹輪の切れ端がこぼれ落ちたりもする。ようやく竹輪の一本分を頬ばり終えると、躊躇することなく川岸に行き当たって、下流方向へ小走りで姿を消し去った。
半時間ほど経って、きたきつねは戻ってきた。私の間近に来てから向き合って目を合わせて立ち止まった。
「そうか・・・、おまえには子供がいるのか・・・、もっとほしいのか?」
「・・・・」
もう一本、竹輪を与えた。
夕飯時には塩を振らないで焼いた山女魚も用意して、きたきつね君のお出ましを待ったがなぜか現れなかった。
|
ほっけ泥棒
蝦夷富士ともマッカリヌプリとも呼ばれる羊蹄山(ようていざん・標高1898m)は実に雄大で端正な山容をもち、美しい形の風格ある独立峰であった。
独立峰の姿の整った羊蹄山は自身の裾野をぐるりとまとわりつくように尻別川に巻かれている。尻別川は上流部から中流部へと周回して流れて、途中で真狩(まっかり)川をニセコ町で合わせ、さらに西へと流れ、蘭越町を経て日本海へと注ぐ北海道では六番目の大河である。 |
 |
羊蹄山の西北西の方角には尻別川を挟んで遠くにニセコアンヌプリ・イワオヌプリ・チセヌプリという名のニセコ連山が好もしい山容を見せて聳えている。関西の丹波地方で育ち京阪神地方で生活をしてきた私には、この一帯の、胸がすくような展望の効く風光や景色には経験したことのない異質で不思議な情緒が充満していることには驚きであった。
羊蹄山の裾野の広がりは展望をさえぎるもののない雄大さで、空も限りなく広く高く大地も広くて異国的な趣を呈している。豊かな大地と風土は田園と自然の調和を生んで、山あり河川あり温泉あり、実に魅力あふれる土地であった。
ニセコアンヌプリ(標高1309m)の登山基地となる五色温泉のそばにニセコ野営場がある。ニセコアンヌプリからの緩斜面となったこのあたり一帯はねまがりだけの藪が絨毯のように敷きつめている。そのなかの一区画を切り開いて造った野営場である。二三日滞在する予定で、昼過ぎに着いた。先客の小さな天幕が一張りだけがみえる。展望が最もいい場所という条件だけで自分の天幕を設営した。 |
野営場の向かいにあるJR山の家の温泉をゆっくり楽しんでから野営場に戻ると先客の天幕の主である青年と出会った。どちらもひとり旅ということもあって、すぐに打ち解けて旅の情報交換などを気安く話した。彼は、この野営場で三泊したがこれから次の地へ移動するという。
その彼が言うには、「このあたりにいる、きたきつねは特別に質(たち)が悪いので十分に気をつけたほうがいい。これは、私の前に滞在していた人からの申し継ぎでもある」と、言う。 |
先々客からの申し継ぎの話しとして、
「天幕を張り、そのなかにリュックザックと登山靴を入れて、二時間ほど温泉やあたりの散策ですごしたのち天幕に戻ってみると、天幕は側面を喰い破られて大きな穴を空けられていた。天幕の中に侵入してリュックザックも喰い破られさらにそのなかの食糧はすっかり盗られ無くなっていた。登山靴は天幕の外に引きずり出されていた」
と、語ってくれた。 |
彼の出立を見送ったあとの広いニセコ野営場には私の天幕だけがぽつんとひとつ立っている。早速、夕飯の下準備だけをしておいて、まだ陽もあるので木製の椅子に座ってゆっくり酒を呑みながら、展望の効く景色を楽しんだ。ニセコアンヌプリを背にした緩斜面からの展望は一面にねまがりだけの笹藪が二メートルを超える高さで地表をどこまでも覆い尽くしている。繁った葉波はどこまでも緩やかに下って行き、広い空の下弦のなかに沈んでいく。野営場のはずれの藪際で立派な体軀のきたきつねの姿をみつけたが、足早に走り去った。
ピリカベツ川で出会ったきたきつねの粗野であってもおだやかで人懐こい残影が強く今でも脳裏にあるので、この先客の話には誇張があるのではなかろうか。天幕の中のリュックザックの中にある食糧の臭いを嗅ぎとっての行為であろうから、二重三重の遮蔽物を超えての臭いを嗅ぎ分ける能力がきたきつねには果たしてあるものなのだろうか。疑問に思ったりもした。
あたりにゆっくりと夕景が迫るころ、酒の肴のほっけの燻製をアルミ皿に取り出しテーブルに置いて、椅子から立ち後ろを振り向いた。途端、
「カタッ」とアルミ皿の音がした。
振り返ってみるとほっけの燻製がない。
「やられた!・・・コラッ!・・・待て!」
大きなきたきつねがほっけの燻製をくわえて、一直線に走って逃げて行く。野営場を突き切って人間の背丈よりも高い笹藪の中に走り込んで姿を消した。
いつの間に私の背後まで忍び寄っていたのか。忍び寄ってくる気配も感じない自分の野性の感性の無さが不甲斐ない。それが不気味で不安だ。ほんの一瞬の、私が振り向いた動作をチャンスとして起こした決断力と狡智さ、瞬発の行動能力には舌を巻いた。それにしてもすばやい身のこなしと体軀、運動能力の高さは全く油断のならない奴だ。先客の忠告が頭をよぎった。
|
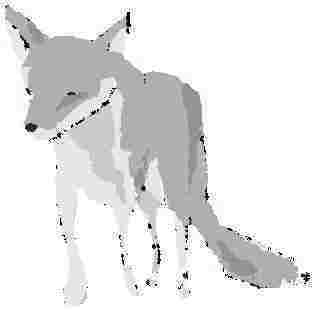 |
|
夕食の準備をしながら、奴が姿を眩ませた笹藪のあたりをそれとなく見張っていると、しばらくして、ほっけの燻製を喰い終えたのか野営場に姿を現した。
ここは、きっちりと懲らしめの報復をして、人間社会としてのけじめをつけておく必要がある。椅子の回りの石を五六個も拾って木の机の上に置いた。奴には無関心を装って油断をしている姿を見せながら、横目で姿を追ってチャンスを待つことにした。
奴が大胆な行動で近づいて来るのを横目で見ていると、先程の窃盗行為は不問にして、さらに次の獲物をせしめようと近づいて来る行為には、まさに人間様を見くびっている行為に違いない。怒りがこみ上げてきた。大きいほうの石つぶてを右手に握り、残りを左手にしてさらに待った。
奴が石つぶての射程距離に入ってきた。頃合いを見計って振り向き様に石つぶてを投げつけた。
命中はしなかった。が、奴は泡をくった。ピョンと背中を丸めてその場で飛び上がり跳ねたあと、大きなトロットで笹藪に向かって一直線に逃げて行く。
奴の後を必死に追いかけながら石つぶてを投げつけた。脚の速さと素早い身のこなしには叶う筈がなかった。逃げ込んだ笹藪の手前まで追いかけて止まり、さらにあたりの石を手あたり次第に拾っては奴が逃げ込んだ方向に何度も投げつけた。荒い呼吸と気持ちが収まるまで投げた。所詮は運動能力の格段の差を思い知らされて愕然とした。
大人気ない・・・・虚しい敗北感だけが残った。
|
夜襲
快い酔いのなか、夕食を済ませた。油断のならない奴にはこれ以上のスキを見せないためにも食事の後片付けを入念にした。ごみや食糧、炊飯用器具などは丁寧に片付けて、車のトランクに収めた。天幕の中に持ち込むものは寝袋とマット、ランプと水筒だけにして寝た。
夜中に奴がまたやって来て、天幕の回りを徘徊している気配は察知したが、無視をして眠った。
翌朝、天幕から外へ出てみると夜のうちにひと雨があったようで黄土色の地肌がゆるんでいた。天幕のまわりには奴が徘徊した足跡が無数に残っていた。奴は夜中にもスキあらばとうろついていたのである。人間様を標的に挑発をしての、訪問であろう。
朝食の用意をするために駐車場に下りて行った。
「やられた!」
思わず大きな声が口から突いて出た。私の車が泥だらけに汚されていた。車の前部とフロントガラス、屋根の上も後部のトランクの上も一面に奴の泥足の跡がびっしりと着いている。夜中に車の上に何度も乗っては動き回り、地団駄踏んで、得意気になって私を挑発していた奴の姿が目に浮かぶ。心底忌々しい。トランクに収めた食糧の臭いを嗅ぎつけることは奴には容易だろう。が、車の上にまで何度も乗り降りし、泥だらけの足でこれみよがしに踏みつけていたとは、全く悪質極まりない行為である。憎き奴である。昨夕のほっけ泥棒のけじめも付けられないうえに今朝のこの惨々な体たらくでは、まさに惨敗であった。
朝食を済ませてからニセコアンヌプリへの登山の準備をした。朝から良く晴れて太陽が出ているので、車に付けられた泥の足跡が乾燥しだしたために、遠目にもみじめな汚れがはっきりと見えだした。このまま放置すれば車の掃除にかえって手間取ることになるから登山の前に洗い落とすことにした。
道道の脇にある休憩舎の水道を借りて洗車した。観光客が私の車の異様な汚れを目敏く見つけて、そのわけを尋ねるので昨日からの顛末を話した。登山の開始が予定の一時間ほど遅れた。
|
ニセコアンヌプリ
|
|
|
ニセコ火山群のなかの主峰であるニセコアンヌプリを登った。野営場の脇にある登山口から一時間半で頂上に立った。快晴の頂上の展望は四方に効いて、宙空のかすむような紫煙のなか、紫煙の向こうには羊蹄山の頂上が屹立し、姿の良い裾野が広々と展開して胸が空く、晴々とした心地よさを味わった。指呼のあいだに存在するように見える羊蹄山の頂上から丁寧に目で追い焦点を下げていき、裾野を下がって尻別川を確認してニセコの裾野へと見やって、再び羊蹄山の頂上に目を移すと、とんでもない大きな紫煙の空間があることが判って、驚きを大きくした。
ようやくニセコアンヌプリの頂上が見え出したあたりの登山道には、頂上寸前のアプローチに格別の楽しさが秘められていた。ニセコアンヌプリの頂上が見えだしたあとの一歩一歩には、その向こうに突然に羊蹄山の頂上も姿を見せてきて、二つの山の頂上を重ねて見せたあとは、自分の歩みが二つの頂上をスライドさせながら目の当たりに迫ってくる様は、大きな山が動くような錯覚と迫真の感動であった。
一度たどり着いた頂上から引き返し、両方の山頂が見え出すあたりまで戻ってから、再び頂上を目指して、ゆっくりゆっくり歩き、目に飛び込んでくる絶景を堪能しながら進んで、二度目の頂上に醍醐味を味わって、立った。
|
登山道の設定に巧みさがあった。この登山コースを作った人はニセコアンヌプリの登山の価値を高めるには羊蹄山との関係にあることを熟知していて、その特徴を生かすための演出を巧みに行ったのではないか。そのようにさえ思わせるのであった。これまでに百座近くの、名もあまり知られていない近畿地方の山々を中心に、単独で登山をしてきた自分には、特別に格調のあるいい山に巡り合ったという気持ちで、満悦であった。
|
 |
下山途中で、登山道から少し外れた展望のいい稜線に出て、大きな岩盤に座って昼食をとった。にぎり飯を食べているとどこからともなくカラスが現れた。二三メートルほどの距離に来て、私を注視しながらさかんに頭を上下させる。にぎり飯を分けて与えて一メートルほどの前に置いてやるとさらに近づいて来て、そこで旨そうに喰った。カラスにこんなに至近距離に寄られたことは今までになかったことである。北海道の動物たちは人間をさほど恐れてはいないのだろうか。
それにしても、昨日からの質の悪いきたきつねの振る舞いは、一体どうしたことだろうか。人間社会との接触で餌が獲得できるという学習が身について、獲物を得るためには人間社会から略奪であれ窃盗であれ、本来の持ち合わせている野性に学習して得たものが加わっての能力を発揮している。結果として、人間が教えたものなのだろう。ピリカベツ川で出会った個体とここニセコ野営場の個体との段差はあまりにも大きい。その段差は、餌獲得をより自然環境に依存している個体と人間社会との接触する環境から餌獲得をしている比率が高い個体との差なのだろう。
自然環境に依存している個体は自然のなかから餌を獲得するための野性の学習能力は長けても人間に対しては、素朴で控えめな振る舞いは好感さえもてる。一方、人間社会に餌獲得のある部分を依存している個体は人間社会から餌獲得のための学習能力が長けてくる結果、野性の能力や狡智さは人間に対しても攻撃的・敵対的に向けられるのであろう、と思われる。
二日目の夜は、私のほかに三組の野営客があったためか、奴の夜襲はなかった。
|
働き者
だが、どうしたことか。真夜中の二時過ぎだというのに野営場の下段にある駐車場には次ぎ次ぎと車がやって来る。
北海道の夏は夜明けが早い。午前三時頃には、もうほんのりと夜が明けかけてくる。 あまりに駐車場あたりが騒々しいので天幕から抜けでて様子を伺うと、もはや駐車場は半分ほども車で埋まっている。車のそばで身支度を整えてから、三四人ほどでひとかたまりになっては林道から笹藪の中に消えて行く。背中にはリュックザックを背負ってはいても登山客とは見えない。すっかり明るくなった午前四時ごろには、もはや駐車場は満杯であふれ、道道の路肩にまで駐車の長い列ができている。
午前五時ごろには背中のリュックザックを膨らませて重い荷を背負って車に帰り着く人の姿が目立ってきた。リュックザックの中身を車に置くと再び林道から笹藪のほうに引き返して行く。
夜が明けるのも早いうえに、なんとも、北海道の人達は実に働き者だ。いつの間に寝るのだろうか。
よく見ると、装束がすごい。頭は野球の帽子の上から頬かぶりで顎の下で結んで、首回りにもタオルを巻き、目と鼻と口の回りは最小の面積だけ露出している。男は上下のつなぎ服で軍手、足元は長靴で固めた完全装備である。みんな一様に煤けたような姿で重い荷を背負って駐車場へ帰ってくる。荷の中身を車の中に移してからまた笹藪に戻って行く。
尋ねてみると、たけのこ(ねまがりだけ:チシマザサのたけのこ)採りだと言う。このあたり一帯は例年なら六月十五日ごろが採取のピークだが、今年は雪が少なかったので一週間ほど早く成長している。たけのこの成長は山の裾から順次に高いところにのぼって行き、このあたり一帯が今採りごろで、今日は土曜日だから特に人出が多いと言う。
「たけのこは、いくらあっても困るものではない」
その言葉を印象深く聞いた。
湯搔いて塩漬けにしておけば保存が効くので一年中食べられる。煮物やおでんなどが一般的な食べ方で、採り立てなら皮を剥かずに焼いて食べるもよし、湯搔いてから山葵醤油で食べるのも旨い。など、親切に教えてもらった。 |
 |
笹藪からたけのこの荷をリュックザックに二三度も運び込んだあとは、野営場でグループ毎に車座になり、炭火を煽こして、採り立てのたけのこや焼き肉での宴会がはじまる。
まだまだ、時刻は都会の人にとっては早朝ではあるが、みんなひと仕事を終えての宴会である。こんな健全な娯楽を楽しんでいる人達に親しみがわく。
倶知安(くっちゃん)町へ抜ける道道の路肩にはたけのこ採りの人達の駐車で長い列ができている。営林署の広報車がやってくる。
「万一の場合に備えて非常食や雨具などの用意は十分か。家族には、どこの山に何時から何時まで入るかを伝えてあるか。携帯ラジオなどの熊対策は十分か。火の始末は完全にしましょう」などと、大音量で呼びかけて行く。
間もなくして、今度は消防署の広報車がやってくる。同じように拡声器で呼びかけて行く。たけのこ採りに山へ入っての事故が絶えないらしい。
私も教わった通りにねまがりだけ採りをやってみた。林道から笹藪の中に入っていくと最初のうちは自分が林道から笹藪に入って来た方向ははっきりと覚えている。たけのこをあちこちで見つけて夢中になって採る。そのうちに自分の帰る方向があやふやになって判らなくなる。自分の回りのどこを見ても笹竹ばかりの密生した状態で見通しは全くなく、体をぐるりと一回転させても同じ笹竹ばかりの壁の世界である。ときには、樺の木などの立木を目印にしていても、すこし離れてしまうと、もうそれも見えない。自分の頭上だけが小さな明るい空間があるだけとなる。この、密生した広大な閉塞世界から生還するには林道に行き当たることしか方策はない。
密生した竹の幹の隙間を手や腕で押し開き、全身で前のめりになって退けて前へ進むので、竹の幹についた油気の煤のようなものが衣服にこびり付く。たけのこ採りの人達の装束が完全装備である事が当然のこととして納得できる・・・・・野球帽の上からほおかぶりをしているわけは、跳ね返ってくる笹竹から顔面を護るために帽子の庇や頭部から顔を覆ったタオルが有効に機能してくれることもわかった。
そこで彼らは採取を終えたあとは、無事に林道へ脱出するために、仲間と連れ立って笹藪に入り常に声を掛け合ってお互いの存在と方角を確認しあいながら行動をしている。また、林道からすぐのところに携帯ラジオを置いて、音量をあげていて、自分が藪から抜け出す方向を知るために利用している人もいる。
採る時間よりも持ち帰ったあとの保存のための処理のほうに時間がかかるのではないかと思われるほど、ねまがりだけはあちこちで頭を斜めにもたげていた。皮付きのまま湯搔いて山葵醤油で食べたり、焼いて食べてみた。私には生まれて初めて口にする食べ物である。たけのこ特有の香気とうま味とやさしい甘味があって、孟宗竹のたけのこよりも、上品なものであった。これなら「いくらあっても、困るものではない」と言われるだけあって、ありがたい山の幸、珍味であった。
たけのこ採りの人達の野営場での宴会は二時間ほどで切り上げたあとは、みんな草の上で昼寝をして酔いを覚まして、昼過ぎには三々五々に引き上げていく。
大自然の中でおおらかで健全な娯楽を家族や友達と極当たり前のこととして楽しんでいる北海道の人たち。私には、豊かな天然資源に依存した健康な「遊と食」に没入している人たちに、自然の懐の大きさからくる本当の「ゆとり」というものを見る思いで、うらやましさと、北海道の大きさと自然の豊かさをひしひしと感じないわけにはいられなかった。
|
野宴
イワオヌプリ(硫黄山)あたりの火山群の地肌剥き出しの山中で散策を楽しんだあと、ニセコ野営場を引き上げた。
質の悪いきたきつねへのけじめもつけられないままに、一里ほど離れた湯本温泉野営場に移った。湯本温泉野営場はシラカンバなどの木々が鬱蒼と生い茂った林間に造られている。太陽の陽ざしが強くなる季節には林間のほうが快適に過ごせる。風や雨の悪天候時には天幕が、この森に包まれて守られているという実感がするものだ。駐車場からできるだけ離れた一角に天幕を張った。森の木々の新緑の息吹が聴こえるような静けさで、こころが落ちつくのが良い。
湯本温泉も近く、そのすぐそばには大湯沼というのがあって、大きな沼の底から吹き出すガスで煮立っており、その間欠泉は硫黄臭い白い湯煙を絶えずあげている。風の向きによっては硫黄の臭いの洗礼をもろに浴びる。
一泊しただけでここの環境が快適な野営場で居心地の良さが気に入った。ここを基地として、尻別川の渓流釣りに専念したいので、当分の間滞在することにした。
尻別川の渓流釣りは対象の魚種が豊富で、ヤマメ・アメマス・オショロコマ・ニジマスなどで型も大きいのもいるという情報である。本州の渓流河川に比べれば、緯度も高く夏期の水温が低く、平野部から山地渓流までの広範囲に棲息域が広がっていて、河川規模の大きい場所から源流の細流までが釣り場だという。
先ず手始めに尻別川の中流域に昆布川が左岸から合流しているあたりから釣ってみた。尻別川も昆布川も川幅が広く、十二尺のてんから竿に5.5メートルの仕掛けでは短くて太刀打ちが難しいと思われたが、膝あたりまで流れに立ち込んで釣った。山女魚の新仔が毛鉤の相手をしてくれる。
そのうち、規模の大きい一級の瀬に行き当たり、瀬脇に立ち込んで毛鉤を振ると・・・・・35センチの野生化したニジマスが毛鉤をくわえた。その取り込みは激しく縦横無尽に走ったり水面に飛び跳ねたり、強引に耐え耐えの全くの翻弄されっぱなしであった。自分の中に久しく眠っていた野性の感覚に火をつけ、覚醒させるものがあって、なんとか取り込めた。野生化したニジマスの強大な力には目を見張るものがあった。その強大な力を体感し、興奮は最高潮に高まった。心臓はばくばくし、釣り師の血が騒ぎだした。 |
 |
一号半のハリスが切れずによく持ったものだ。ハリスと鉤を点検して、しばらくは呼吸を整えて水面に目をやると、この瀬には40センチを超える大物の魚影がまだある。あの大物を何んとしてでも釣りたい。ハリス切れを防ぐために三号のハリスに交換した。思惑は的中し、40センチを優に超える大物が毛鉤をくわえ水面に勢い良く跳ね出た。反射的に力任せにアワセをくれてやった。見事にアワセ得たはずの動作であった。が、「ボキッ」という鈍い音とともに力んだ右腕は空を切った。てんから竿が握っている手の数センチ先のコルク巻きの端部分で折れて脱落し、仕掛けと竿が水面を力なく流れていく。その反動で毛鉤もニジマスの口から外れた。
二本目のてんから竿を取り出して、三号ハリスで竿が折れるのなら二号ハリスに強度を落として、再度、挑戦した。結果は同じことでアワセた瞬間にコルク巻きの端部分あたりで折れてしまった。二本のてんから竿を駄目にした。
冷静になって、考えればすぐに判ることである。てんから竿を折損から守るために竿の調子に適合した強度以内のハリスを使用する設計になっていて、設計値を超える力が加わったときにはハリス切れを起こすことで高価なカーボン竿を折損から守っているのです。
今までに、竿の限界強度を超えるような大物釣りを経験したこともない、身の悲しさであった。私が長年にわたって釣り歩いてきた幾多の渓流での魚型は三十センチが閾値で、その閾値を超えれば巨大(大物)魚、閾値に足らなければ大型・良型・中型とさがっていく尺度です。余程の幸運か、困難な条件を克服しなければ巨大(大物)魚にそうたやすくお目にかかれないのが実情です。もちろん、本州にも40センチを超えるニジマスは多くいますが管理釣り場を中心とした養殖魚で、だらしがないほどの運動能力であり、ひとかどの渓流釣り師なら誰も相手にしないのです。
そんなことですから、てんから竿の限界強度に配慮することなど頓着の外であった。しかし、そんな火に油を注ぐ様な釣りをやって、残すところ短めのてんから竿一本と餌釣り用の延べ竿が一本のみとなって、こころもとないことではあった。渓流釣りの魅力と熱に取りつかれ夢中になって、興奮の坩堝から抜けきらない日々が続くのであった。
それでも、大物魚への執着する熱から離れれば、三日目には尻別川の釣り場や釣りの様子が把握できるようになり、一人では食べきれないほどの型揃いの山女魚を野営場に持ち帰った。
湯本温泉野営場では天幕の張れる場所が、段差のある地形と自然の植生をあるがままに受け入れ利用した形で巧みに造られ、設定されている。その条件によって設営する天幕の相互の間隔も距離を置いていて、森林のもつ特有のやすらぎと温もりをお互いが享受できるように配慮されている。
 |
東京からの一人旅で登山や観光を楽しんでいるという、私の設営した天幕の近くで野営している中年の男性を夕食に招待した。
山女魚は塩焼きとムニエルにしてたっぷりとある。たけのこは皮つきで湯搔いて山葵醤油で食べる準備も整った。あとは、お互いの手持ちの酒とつまみを持ち寄って、一人用のテーブルを二つ向かい合わせにした上に並べ、途中で席を立つこともないように整えてから、野宴を始めた。 |
お互いが一人旅だということもあって、寡言がちな環境から一気に解き放れたように饒舌を誘い、二人きりの野宴は大いに盛り上がった。お互いが初対面の間柄だが、この場所で、この環境での一期一会が、共通する趣向や価値観に響き合うものがあって、大いに語り、大いに呑み食い、彼は思いのほか喜んでくれた。
魚は大好物だという。この山女魚は格別においしいという。しきりに山女魚のおいしさをほめてくれる。
そんななか、向き合って話す二人の目の前に、
「ポトッ・・・」
青虫が頭上の木から落ちてきた。
それを見た瞬間、私にはひらめくものがあった。
「そんなに山女魚が好きなら、明朝は山女魚釣りを尻別川に案内をしたいが、魚釣りはどうですか?」
と、尋ねると、
「私も魚釣りが好きなので、やるつもりで餌釣り用の延べ竿と簡単な仕掛けは用意してきているのですが、北海道の河川は随分と様子が違うので、どうしたらいいのか戸惑っていて、まだこちらでは釣りをしていないのです」と言う。
「それなら・・・、明日は僕にすべてを任せなさい。山女魚の大釣りを体験させてあげるから・・・・」
酒の酔いも手伝って、大風呂敷を広げてしまった。しかし、二人の目の前に落ちてきた青虫を見た途端、私には明日の二人の山女魚釣りに根拠のある自信があった。
翌朝、起き抜けに天幕の回りで、例の青虫を拾い集めた。両の手に一杯ほどを集めるのにさほどの時間は掛からなかった。彼が天幕から起き出てきて、怪訝そうなおももちで、
「その青虫を釣り餌にするのですか?」
「そう・・・このブナ虫さえ手に入れば鬼に金棒、御の字や。・・・ブナ虫は山女魚の大好物。今日は山女魚の大漁は間違いなしや・・・」
朝食もそこそこに済ませて、二人で尻別川へと走った。尻別川の中流域の大きな瀬と淵が繰り返す曲流部に、上流と下流に二人は分かれて釣った。ブナ虫を流れに入れれば予期したように山女魚は入れ喰い状態であった。彼も第一投から良型の山女魚の取り込みにはおおわらわで、興奮して満悦の様子であった。二人では食べきれないほどの良型の山女魚を釣って、持ち帰った。
二人で湯本温泉の混浴の露天風呂を楽しんだあと、昼ごろには山女魚とたけのこ、山菜での野宴を再びやった。
このときの青虫をブナ虫と呼んだが、渓流釣り師の間では、蛾や蝶類の幼虫期間のも
ので、ブナ科などの植物を食葉として (時に大発生することがある。) いる幼虫類を
総称してブナ虫と呼んでいる。正確にはシラカンバ (カバノキ科) の葉を喰っている
シャクガ (尺蛾) 科のなかまの幼虫であった。
天気さえ良ければ、早朝より渓流釣りに出掛けて良型をせしめてくる。笹藪にほんの少し潜り込めばおいしいたけのこが採れる。山菜もいたるところで採れる。昼過ぎにはそんな野遊びから戻ってきて露天風呂にゆっくり浸かる。
渓流魚やたけのこ、山菜など豊かな天然資源のなかからほんの少しだけ頂いてくる。今日の収穫で野宴を張る。全国からきて野営している登山者や釣り師、一人旅の旅人などに気安く声を掛けて、一期一会の感覚が合えば大いに語り合って、呑み食い、何も着飾ることのない裸の付き合いをする。野営の旅での巡り合いを楽しむ。豊かな大地の恵みにおおいに感謝する。
陽が沈めば眠りにつく。太陽が昇れば起きて、野遊びに夢中になる。雨が降る日は町まで出掛けていき、食糧などの補充をする。読書をする時間もたっぷりとある。
ここは、まさに野遊びの仙境であった。
さらには、豊かな大地の恵みには、こんな楽しみもあった。
|
女狐
夕刻にはまだまだ時間のある明るい日差しが乳色の湯面に燦々と、光輝を放っている。
乳色の湯から立ち昇る湯気と大湯沼の白い硫黄の臭いがする湯煙が混じりあって、女男混浴の露天風呂に漂っている。まさに仙境の湯船にふさわしい雰囲気を醸しだしている。岩風呂の壁にもたれてあぐらをかけば、いい塩梅にあごのあたりに湯面がくる。
野遊びの心地よい疲労に、身もこころも湯の中に伸びきっている。
眠気もさしてくる・・・・
・・・うたた寝の夢か?・・・うつつか?・・・
この露天風呂には、いつも若い女狐が湯に浸かりにくる。いやいや、若い女狐だけじゃなくて老いも中年も子狐も、男狐も。日に日に湯に浸かりにくる顔ぶれが新しい。旅の途路に湯を楽しんでいくのだろう。
「エイッ!はいっちゃえ!」
関東弁の若い女狐たちが気合を掛けて、よく育った体軀に背筋をのばして混浴の露天風呂に入ってきた。
そう言えば、先程、女湯のほうで、
「旅の恥はかき捨てじゃん・・・・せっかくここまで来たんだから・・・・ねえ、露天風呂に入ろうよ!」
大きな声での会話が聞こえていた。
そうかと思えば、先客に向かって軽く会釈をしながら、しとやかに湯に浸かりにきた淑女狐もいた。小さな笑みを湛えた顔が湯面に浮かんでいる。
なかには、素っ裸で湯船のそばまで歩いて来ながら、先客のほうを見てニヤッと笑ってから、女湯のほうに引き返していった中年の女狐もいた。なぜ笑ったのか。なぜ湯に浸からないまま引き返したのか。・・・・夢うつつのなかの鈍んな頭では、感度が悪くて解せない。
しかし、そんな奴はほんの少数派である。ほとんどの女狐たちは、素っ裸を、もやった外気のなかを通ってくる太陽の光線に晒すことを楽しむように、おじけつかずに堂々として背筋を伸ばして歩いてくる。一枚の小さなタオルを体の前に垂らして広い石畳の通路を歩いてきて、湯船に浸かる。
それでいいのだ。おどおどされたら、こちらのほうが困る。おおらかに振る舞ったらいい。ここでは、こせこせするほうが恥ずかしい。心配することなど何もない。燦々と輝くお日様が見守ってくれているではないか。 |
 |
私の小さなこころは湯のなかでときめいている。
湯面から出した顔は泰然自若を決め込んではいる。
ときに、老婆狐が先に歩いてきて、
「さあさぁ・・・こっち、こっち・・・少しも恥ずかしがることなんかないんよっ・・・こんないい湯に入るのに男狐も女狐もあるもんかぁ・・・さあ、さっ・・・遠慮しないで・・・・こっちへ、こっち・・・」
大きな声でのたまわって、若い女狐たちばかりを大勢引連れて、先導してくる。手慣れたものである。ひょっとしたら、この老婆狐は地元の常連様なのだろうか。仙境の露天風呂に相応しい和んだ雰囲気を作ってくれる。白桃色の菖蒲の大きな花びらが一陣の風に揺らいで姿を低くして沈んでいくかのように列をなして、若い女狐たちは次々と湯船に入ってくる。乳色の湯船はいっそうに華やいだ。
湯に浸かってしまえば、濃い乳色の場だから、湯の中は、折角の自慢の身体であっても見えやしないから・・・若い女狐たちも安心して湯を楽しめる。
やがて、若い女狐たちの柔肌は、ほんのりと上気して鮮やかな桃色に。いい湯を楽しんだあとは湯船から出て女湯のほうに戻っていく。
一枚の小さなタオルでは身体の前は隠せても、きたきつねのような大きな尻尾を持たない女狐たちは、豊満な桃色のうしろ姿をたっぷりと私に見せて、自慢げにゆっくり歩いて去っていくのであった。
|
|
昨今の、酒の席で、その場の雰囲気も和んでから、酒を勧めるときに「たぬきの金玉でまた一杯」と言って勧めても相手には、果たしてそれに答えてもらえるものだろうか。今で言うところの親父ギャグではあっても、たぶん、何を変わったことを言うのかと怪訝なおももちをされるのが、落ちではないだろうか。
自然の風物を愛で、花鳥風月を友とする古き時代には気の効いた洒落ことばとして、立派に通用した言葉です。この洒落ことばには伏線として「たぬきの金玉八畳敷」というのがあり、たぬきの睾丸が非常に大きいという俗説を知っていることが前提になっている。
たぬきの金玉が大きくて「股いっぱい」であるというところから「また、一杯」にかけてお酒のおかわりを勧める、実に他愛ない話なのです。
「証誠寺の狸囃子」として伝わる、たぬきがうかれて腹つづみを打ってはやすという伝説もあります。酒にうかれて腹鼓を打つたぬきの風体は擬人化されていて、信楽焼きのたぬきの置物に象徴的にみられます。ユーモラスといささか下卑た誇張で、酒徳利と狸腹と股いっぱいの金玉が三位一体となって醸しだす愛嬌ある風体がおなじみです。
和歌山県の日高川の支流、丹生川の栃谷の瀬で、99年の春五月のよく晴れた日にコサメ(地元ではあまごのことをコサメという)釣りをしていたところ、流れのうえをいく釣り仕掛けの目印を追って見ていると、その向こう岸にふらふらと歩いている動物が目に入ってきた。対岸の岩場の手前の砂利のうえを、たぬきが今にも倒れそうな足取りで、よろよろとゆっくり歩いている。まるで、病気を患らっていていきだおれのような足取りであった。そのうちによろけながらも岩場の上にあがり、小さな窪みのそばまでくると、その窪みにパタッと倒れ込んで動かなくなった。
めずらしい光景なので、川を渡って、岩場にあがり窪みの手前で立ち止まって、たぬきをよく観察した。罹病などではなくて色艶もよく、よく肥えた健康そうな体軀であった。
大きな息をして熟睡している。横臥した腹部を規則正しく波打たせている。両足の付け根あたりには八畳敷といわれる睾丸は確認できなかった。たぬきの腹は体軀全体の釣り合いからみても狸腹に相当する大きさであった。
この限りは、俗にいう「たぬき寝入り」ではなく、陽春の日溜まりのなかまさに白河夜船の真っ最中で、昏睡状態に陥っている。この時のたぬきの眠りは深い眠りであって、人間が至近距離に近づいても全く反応がないものであった。私が猟師なら、いとも簡単に銃器などつかわなくとも捕まえることができたのであった。猟師でなくとも、天敵の、歩行する大型動物はいないのであろうか、上空からの鷲や鷹の猛禽類からの攻撃はないのだろうか。実に大胆な眠りではある。
「たぬき寝入り」の寝入りとはよくねむることであり、そのうえにたぬきがつくと、眠ったふりをすることと、辞書には出ている。そうすると、たぬきには二つのねむりかたがあって、「本当の寝入り」と「たぬき寝入り」を使い分けているということになる。「たぬき寝入り」の戦略については、あとで触れることにします。
由良川は京都府北部の舞鶴市と宮津市の境で日本海の栗田湾にそそぐ、近畿地方では淀川と熊野川につぐ三番目の大河である。その由良川の源流域である美山町の、ある渓流筋の最奥の集落からさらに林道を一里ほど遡った、伐採時の木材集積場として使った跡地にある広場で野宿をした。一泊の予定で渓流釣りにきての夕食時、釣った山女魚を塩焼にして食べているところへ、
「フン・・・フン・・・フン・・・」
三頭連れのたぬきが現れた。
「フン・・・フン・・・フン・・・」
椅子に腰掛けている私には、全く反応を示さないで無視し、そのまわりを三頭連れが臭いをかいて動き回る。狙いは机の上にある塩焼きの山女魚であり、どうも机の脚元あたりでその臭いが途絶えるのであろう・・・しきりに「フン・・・フン・・・」と鼻を鳴らして回りを徘徊している。
机の上で食べかけの塩焼きの山女魚を、自分の分は取りのけた残りを三等分にして、地面のうえに三箇所に分けて置いてやった。
「ひょっとしたら、今日も君達のおでましがあるのじゃないかと思って、多い目に焼いていたんや・・・」
餌にありついたためか、「フン・・・フン・・・」の鼻鳴らしは止んで、一途に食べている。たぬきは与えたものを、その場で無心に貪っているのがかわいい。ホンドキツネは折角与えたものを、ひったくるようにして、くわえて持ち去るので愛想がない。
早く喰い終えた奴が、まだ喰っている奴にちょっかいを出して、軽くあしらわれたので私の前に来て立ち止まり、そっと目を会わす。やっと、私の存在を認識したのであろうか黒い瞳で見つめながら、うろつく。ひとしきり三頭でうろついたあと、もうなにもくれないので見切りをつけたのか、闇のなかに連れ立って消えた。
小心者のたぬきが、突然の身の危機に直面したときに「死に真似」をすることはよく知られています。「死に真似」も「たぬき寝入り」もたぬきにとってはおなじもので、危機を乗り切るための本能としての策・戦略であろうと思われるのです。その場の状況によって人間側が「死に真似」をした、やれ「たぬき寝入り」だったと、説明している節があると思われるのです。
「狸爺」や「狸親爺」という言葉の意味は「狡猾な年老いた男をののしって言う語」ということにはなっています。たぬきが狡くて、悪がしこいとののしられるのは、その身の危機に直面したときに「死に真似」や「たぬき寝入り」の策を弄して切り抜けるのに対して、問題の核心にまともに向かい合う解決をするのではなくほっかむりにしておいて、その場をなんとか取り繕い切り抜けるための狡い戦略を、狡猾な年老いた男の生きざまに見立てての言葉です。
しかし、私の知る範囲でのたぬきは、とてもそんな悪智恵の働く奴ではなくって、おっとりとした緩慢さだけが目立っている特性を持ち、人間に馴れやすく剽軽さもあわせもつ生き物です。「死に真似」や「たぬき寝入り」の手管で処世を渡っていかざるを得ないところを見ると、狡猾さよりも、むしろおっとりした緩慢な動きと小心者の臆病さからくるもので、突然に襲いくる身の危機への対処方法は、失神だとか衝撃による一時的な仮死状態などの奇態で対処しているものだと言えます。
そのおっとりした緩慢な動作や「死に真似」や「たぬき寝入り」の習性が災いして、実に悲惨な情景に遭遇することが度々あります。早朝や深夜に渓流釣りで地方道や林道を走っていると、路上でたむろしているたぬきたちに遭遇する機会が多くあります。突然のライトアップに驚いたたぬきたちは、その場に立ちつくしてしまう習性があり、決して逃げだそうとはしないのです。たぬきがそういう習性であることを知っている運転手は必ず停車して、衝突を避けます。その習性を知らない運転手は、たぬきが犬やきつねなどのように逃げてくれるものと思って、速度を少し落とす程度で通り抜けようとしますが、たぬきは立ち止まったままですから、車に巻き込まれての悲惨な結果となります。実に痛ましいたぬきの交通事故死が数多く見られるのは、このような習性をもつが故の結果であり、里のけものと言われるたぬきたちが住処の里で車社会に対応できない悲惨な現実に直面しているのです。
たぬきは大昔から人間社会と密着して生息してきた生き物です。薄暮から早朝にかけて活動し、人家や田畑、森林、河川敷などを食餌を求めて徘徊します。タニシ・ザリガニ・カタツムリ・爬虫類・カエル、柿の実などの果物類など幅広い食性によって、環境に巧く順応して生きています。人里のごみ捨て場にも依存しているかとおもえば、ひと里遠く離れた山中でも遭遇することがあります。
美山町の南に位置する日吉町を車で走っていると、紅葉が今盛りと輝いている、こじんまりとした神社が目に止まった。境内を見学させてもらう。正面の拝殿に向かって、見事な紅葉の下を潜って石畳を歩いていく。右手方向からのそよと吹く風にのって、きれいに掃き清められた神社には似つかわしくない異様な悪臭がした。右方向には松や楓の木があり根元にはびっしりと苔が生えている。その先は割り石の垣根で、その手前の二本の太い松の木の根っこの側に、直径が1メートルほどの円形に盛り上げた糞が堆積していて、悪臭を放っている。たぬきの溜糞と言われる糞塚であった。
四囲の環境は、神社の社は張り出した山稜に取りついて建てられ、その正面の方向には人家が散在して、境内の回りを左から流れてきて正面あたりで右へと曲流していく川があって、低い山々に囲まれた小さな盆地の中は田畑が作られている、典型的な丹波地方の山里である。たぬきたちにとってもとても棲みやすい環境で、神社境内の糞塚を中心としたこのあたりは、多くのたぬきたちの社交場になっている。
一方、神聖な場所である神社境内に、この糞塚の存在を、神社をお守りする人や里人たちも十分に承知していて、それを許しているのです。境内は綺麗に掃き清められ、もちろん糞塚の周囲もきれいに掃除が行き届いていることからも、それは判ります。
里の人たちも、たぬきたちも、いのちあるものたちがみんな、あるがままに、お互いの存在を認めあって、お互いの生活を尊重しあい、共に生きていく。山里のひとたちのあいだでは至極当たり前のことであっても、都会に住む私には、驚きをもって、温かい心根をそこに見たのです。
|
|
京都北山と呼ばれる地域は京都の都市部の北方に展開する高原地帯で、北は福井県境(若狭・丹波国境)、東は滋賀県に境を接し、西は中国山地東端へと連なる準平原状の千メートル以下の群山が蟠踞する広大な地域です。その地域のやや北部寄りに、ほぼ東西方向に分水嶺が走っていて、南側を流れ下る諸河川は大堰川(桂川)となって京都市内に流れ出て大阪湾に注ぐ淀川水系で、分水嶺の北側の山々の山襞から流れる川は美山川となって綾部市、福知山市を経て日本海に注ぐ由良川水系と、二つの流域に分かれています。
その昔、由良川水系の上流域のある土地で、周囲の地面とは1.5メートルほどの高さに盛り上がった、まるで出臍のような土地の上に、一軒家があったという。その一軒家のまわりにはぐるりと田圃が作られていて、その一家の山居があったという。その田圃の外側はぐるりと山の襞に取り囲まれていて、小さな小さな盆地の中の土地であった。
今では、住む人も家屋も田圃もなく、植林された杉の大木が鬱蒼と繁っていて、かつての山居の面影は何ひとつ見いだせない。この土地は釜ケ原と今も呼ばれ、その出臍のような小さな台地の上に立って、周囲を眺めてみると回りの山斜面が等距離に衝立のように立ち塞がっていて、まさに釜の中に立っているのと同じで、不思議な雰囲気をもった土地であった。山居した一家の人達はあしたに夕べに見る景色は、釜の底から見る、お日さまとお月さまを近くの山の端に迎えては、せわしくも反対の山の端に見送るという短いお日さまや短いお月さまの日夜を余儀なくされていたのだろう。釜ケ原は由良川水系の上流域にある、佐々里の村落から佐々里川を少し遡った右岸側にある土地である。
| 90年の秋十月の初旬、昼過ぎに釜ケ原の地に到着した。佐々里川の川岸に狭い砂礫の堆積地をみつけて、今夜の宿とし、天幕を張った。明日は早朝から佐々里川の右岸の品谷を遡行して、源頭の品谷峠を越えて、かねて念願の廃村八丁の地を尋ねる予定である。帰路は八丁川と佐々里川沿いに下って釜ケ原に戻ってくる予定である。 |
 |
八丁は丹波高原の山襞に囲まれた小盆地で、壁遠の地にある。明治期には五戸が居住していたが、
昭和九年の豪雪で村民は孤立無援の飢餓に苦しんだと伝えられる。
これを契機に、行く末の不安と子女の将来を考え、村民たちは挙村やむなく父祖伝来の墳墓の地を涙
をのんで離れることにした。捨てられた土地だと伝わる。
いまでは廃村八丁と呼ばれ、廃村の残影や静寂境を求める登山者や杣人が消えかけた往時の小径を踏みわけて訪れている。 明日の行動予定は私の体力から判断して、それ相応の覚悟がいる。単独行での、強行に備えるため、早い夕食を済ませた。夕闇が迫り来るころには天幕の中で寝袋にくるまっていた。登山地図を広げて明日の予定の行程を確認した。往路は、ほぼ中間点となる品谷峠までが破線で示されているところからも不明朗な難路を行くことになるのではないか、峠を越えれば等高線も間隔が開いていて、道は実線で示されているので廃村八丁までは歩きやすいのではないだろうか。
そんなことを考えているなか、突然に!・・・大音声の戦慄が全身を襲った。
「!!!・・・・・・!!!・・・・・・・!」
両方の耳は瞬時に「キーン!」となって、何も受付けない。あまりの大音声に、あわて、わなななき、身体は震えが止まらない。大音声の波動に天幕の布も震えた。天幕のなかに寝ころがっている私の頭のすぐ側での大音声である。
まさに、震天動地の不意打ちをくらった。
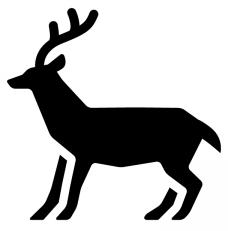 |
それが、牡鹿の猛り立つ、雄叫びであることが判ったのは、先程とは少し離れたところでの、二度目の雄叫びを聞いたときである。両方の耳はまだ、「キーン!」と鳴ったままで、その大音声の振動を受け止めていた。
「ぴゃああああ・あるん。ぴいひひひ・よん!」
その夜は、すっかり太陽が落ちて、あたりに漆黒の闇がくるまで、遠く近く、あちこちで何度も何度も鳴いた。牡鹿たちを煽情するための、誘惑の声である。夜のとばりが迫りくる山峡に煽情と哀切の情を送り付けている。 |
私には恐怖心は全く無かった。牡鹿の猛り立つ、雄叫びをほんの間近で、全身で受け止めた感動と、その余韻に・・・血が騒いだ。大きな生き物が生身でぶつかり合う、野獣の血潮が昂る息吹と慟哭が、瞬時に人間の度肝を抜いて、ぶつけて気圧される迫力に・・・感動と感激を味わった。
眠っていた野性を呼び覚まし、動物本能を駆り立てる、生き物の世界に引きずり込んでいくような余韻と誘いを・・・いつまでも受け止めていた。それにしても牡鹿のまじかで鳴く声は気圧される音量と振動、体臭はもちろん体温まで直に伝わってくるような野性の雄叫びであった。幼い頃に接した農耕用の飼い牛の肌に素手で触れたときの蠢くような生身の血の温もりと、息吹の逞しさにも似た獣への親しみを覚えた。
| |
|
おくやまに 紅葉ふみわけ 鳴く鹿の
声聞くときぞ 秋はかなしき |
万葉びとの歌が頭を過った。今夜のこの野営の体験には、相応しい歌である。 「かなしき」に情景と心情、心根のすべてを集約しいる。「かなしき」にすべてを託した作者の意図はどのようなものなのだろうか。
「かなしき」は、単に「悲しい」では無論ない。鳴く鹿の声は、作者の居る秋の情景と野鹿を包んで、歌の詠み手と鳴く鹿のあいだには、近くで鳴く鹿の声は生命の躍動感に印象を強め、遠く鳴く声には生命へのいとおしさを讃える声として聴いて、身にしみていとおしくもかわいいものとしてとらまえているのだろう。そんな鹿鳴く秋の風情がじんと胸に迫り、涙がでるほど感じる情感を冷静に「かなしき」に、作者は詠み込んだのだ・・・この夜の、天幕の暗闇のなかでは、そのように思うのであった。
「山河に遊ぶ」web版
著者:陶 山汀(上原 濶)
community船場website掲載:2017/11/6
|