彼女とやり取りしていた手紙は手元に無く
最後に彼女へと手紙を書いた日からはもう随分と時が経っていた。
「どうかお幸せに、と」
彼女と今でも交流のあるガブラスが敬礼をして部屋を出ていく。
閉じた扉。
一人きりになって、私は彼女の姿を久しぶりに思い描いた。
彼女の事をガブラスに尋ねる事はしていない。
帝国の繁栄の為に、ロザリアから妻を娶ってからは一度も。
昔と変わらぬ笑顔を浮かべて、
平凡な日々を送っているのか、
それとも冒険に満ちた日々を送っているのか。
瞼の裏に浮かび上がる彼女の姿が
とっくに捨てたとものと思っていた痛みを呼び覚ます。
一度思い出してしまえば
どうしても確認したかった。
自らの目で。
彼女が真実幸せであるのかどうか。
彼女を幸せにする人が―――自分でなく誰であるのか。
長く潜伏していた病魔が今になってその猛威を奮ったかのように
彼女を求める衝動が、発作のように自分の身体の自由を奪う。
知ってしまったから、もうどうしようもない。
震える手から書類を取り上げて、私は立ち上がる。
彼女の姿を一目だけ。
きっと
一目だけ見たとしても何も変わらない。
きっと彼女は幸せで
そしてその事に安堵し
見なければ受けずに済むであろう衝撃を受けて
私はまたここへ戻って来る事になるだろうけれど。
愚かな私は
病魔に侵されるまま
部屋を出た。
鐘の音。
人々の拍手と祝福の声。
ダルマスカ王国に新しい条約を持ちかけるのだという体面で
私は美しい都に降り立つ。
凝ったガルテア様式のバルコニーで目を細めた女王には
これがただの言い訳でしかない事などお見通しであろう。
それでも彼女は何も言わずに私を見送った。
王都ラバナスタの一角
小さな祭を祝福する人々の間から
彼女を―――見た。
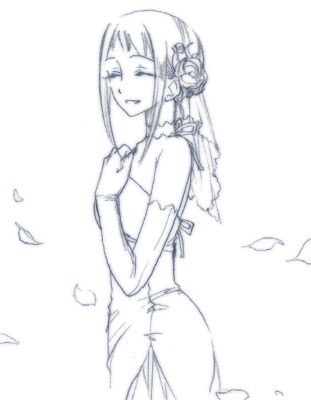
記憶の中のどの彼女よりも美しく、
そして幸せそうに笑うその姿に
私は喜び
後悔する。
その微笑みを向けられる、一人の人になりたかった。
そんな願いは随分前に涙と共に捨てたというのに
胸が―――ひどく痛む。
私は彼女の幸福に包まれた笑顔を目に焼き付けて、踵を返した。
これが本当の最後だ。
もう二度と、彼女と会う事は無いだろう。
踵を返した私は知る事などない。
彼女が人ごみの中、私の姿を見つけ
そして―――
私と同じ表情を、刹那、浮かべた事など。


人の喧騒から遠く離れてから、私は気付く。
彼女の手を取った相手の顔などまるで見ていなかった事に。
だが、
それはどうでも良い事だ。
彼女が幸せであるのならば―――
だからどうか幸せに
私の愛しい人よ
さようなら