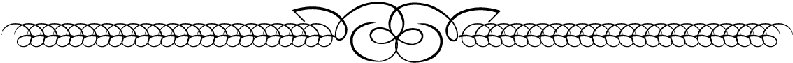
丸山 正衛
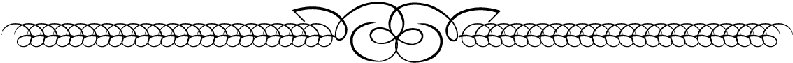
当時、二十歳になると男子は否応なしに徴兵検査を受けなければならなか った。伊達の小学校で検査を受け、良い体だ甲種だと言われ、私の国家社会 に対する殊更の認識が始まる。希望していなくとも、入隊通知は来る。昭和 六年満州事変勃発の直後、札幌二十五聯隊に入営となった。入営後九ヶ月後、 満州派遣軍に編入され、いきなり満州事変の禍中に投げ出された。東奔西走 一年半、行程千二百里交戦百二十六回、最後の熱河戦には二十四時間歩かさ れたのは最も苦しかった思い出となっている。
昭和九年二月、任伍長で除隊となり喜んでいたが不景気の就職難は現下の 比ではなくとても厳しかった。 そんな時、満州国警察官募集の新聞を見て応募。札幌では合格者二名の中 に辛うじて入り、八十円の赴任旅費を受け全国から百名が東京に結集、旅順 の戦跡見学から始まり警察官としての使命をたたき込まれる。 首都新京中央警察学校で新任教育を受けた。初任地は南満州の蓋平県とい う所の警務局、県警五百人のうち日本人はわずか七名程で、いきなりの指導 的立場はそれでなくとも血気さかんな青春の血を一層沸かすこととなった。 県境に侵入してきた金日成軍と対戦、進退極まった思い出。忘年会で遠く 大連の地で遊んだこと。忘れられない思い出はたくさん有る。
勤務二年目に昇進して奉天城内警察署勤務となり、張作林・張学良など旧 軍閥要人の動静は慎重に把握しなくてはならず、地道な管内巡りで靴の底が 半年ともたない。おかげで管内の生き字引と重宝がられもした。 そうこうしてる内に、慰問袋が縁で札幌の人と結婚が決ったが迎えの休暇 も取れない位忙がしい。彼女独りで全く知らぬ地へ旅立ち、私は土曜の午後 大連港まで出迎え急いで帰宅翌日曜日は新居づくり月曜日にはもう普段と変 わらない勤務についていた。今に到っても薄情者と思われているかも。
昭和十五年五月清原警察署次席となる。撫順炭坑の隣県で人口三万余の街 ではあるが、県下は五十余万程。 戦火は厳しさを増し軍民のあいだに立つ警察行政は苦境に立たされていた。 誠意を以て事をなすよりすべが無かった。三年目、奉天省警務庁に転勤の内 命があった。後日、この転勤を取り止めて欲しいとの住民からの要望があっ たという事を知って嬉しかった。 昭和十七年、七市十八県を管轄する奉天警務庁で省下の情報収集を担当す ることになった。当時、中国国民党の東三省(満州)の失地回復運動が地下 で活発化してきていた為終戦の前の年、数十名の幹部を検挙し取調べること となった。私の担当は党書記長斉某氏警察学校の教官であったが、取調べ中 に敗戦。一転して敗戦国の戦犯という立場に・・・・・。
逆に解放されて満州国の行政を接収した斉書記長から数日後手紙が届いた。 「取り調べ中は温情を受け感謝している。立場は変わったが、何か困った ことが有ったら知らせてくれ。必ずお手伝いする。」と。 嬉しかった。感激も束の間、九月二日進駐ソ連軍司令部地下室にほうり込 まれた。連日厳しい取り調べを受けた。こっちにも心得はある、がんばった。 最後の取調官でブルドックと恐れられていた大男の少佐に両足をつかまれ逆 さづりにされ二・三回振り回されたその力には恐れ入った。天皇は降伏した のに何でおまえは・・・・・と拳銃を突き付けたりされた。ニヵ月余の取り 調べの後、最後に韓国人でハルピン露語学校出身の男が通訳し調書を読んで くれた。内容は言ったこともない事ばかり。当初の通訳は市内のキャバレー の女性でお粗末な日本語で困っていたが案の定めちゃくちゃだった。ソ連刑 法第四十八条により処分するぞとの脅しには屈しなかったものの、結局はシ ベリア連行ということになった。 十一月末の厳冬に向かおうとしていたウラル山中の収容所を転々とし過酷 な労働の月日が五年間続いた。この間の体験は、最高の修業だったと考える ことにしている。どうにか、スターリン教に染まることなく日本へ生還の日 を迎えることが出来た。
帰国後、さきに戻っていた妻子ともめぐりあい周囲のあたたかい支援を受 けて生活の基盤を築きかけた失先、住んでいたアパートが焼け、どうにか皆 無事逃げ出せたことを喜んだものの、一方では何の因果かと一度にカが抜け た。 戦中彼の地で失った二児、引き上げて青年となり大学に行っていた次男が 旭岳で遭難しこれも亡くした。
私にはどうしても戦争が糸を引いているように思えてならない。 無情の人生を幾度も悔やんではみたものの月日は人を待たずとか。数十年 の重みがわが身にのしかかってきたかのようだが、先は健康であることに感 謝し、老いの一徹多少のことは目をつぶり老の坂をゆっくりゆっくり登って ゆこう。戦中戦後同年輩の皆さんも凡そ同様の苦難を克服されてきたのでは ないでしょうか。今日充実した日々を送りながらも若い世代の人々に語り残 すことも大切と考え、たわごとを書き連ねてみた。