『下崗(シャー・ガン)』
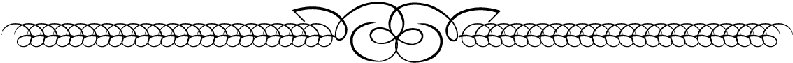
東出 隆司
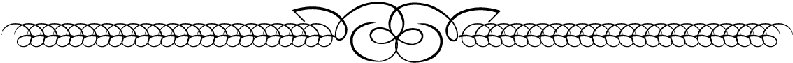
リストラ、という言葉を初めて耳にしたのは一体何時頃の事だったのだろう。 そう遠い日ではない。年をとるにしたがって、月日の経つのがとても速く感じ られ、一年なんてアッという間の事だから、私にとってはついこの間の事と言 って好い。
最初変な言葉だな、と思ってたらいつの頃からか頻繁に耳にするようになり、 いつの間にか慣らされた。但し、その正確な意味を知っているかと言うと怪し い。怪しいどころか言えない。リストラに限らずそうした外来語を私は沢山抱 えている。抱える量が増え過ぎて相当苦しいのだが、いかんせん、前の奴が解 決せん内にもう次の奴が飛込んで来るもので最近では成るに任せている。 外来語に関して言えば、私は巨人軍某監督のよう自分からそれを多用する方 ではないので、誤って使う心配はないのだが、時々心配になるのは、相手が使 った時、自分なりに勝手に解釈してその言葉を聞いて分かった風を装ってるん だが、合ってるのかどうがすこぶる怪しい。時折、ン、と首を傾げたくなるの は、私の解釈に問題が有るのか、はたまた、話し手が使用法を誤って使ってる のかが判らん。 無論、手元に「現代用語辞典」なんてのもあって時々気が向けば調べたりも する。するが、最近のこうした外来語は直接「物」よりも「気分」を表すのが 多くて、いつも分かったような分からんような。要するに分かってない。でも、 皆が使うのまで阻止できないから、こっちが慣れるより仕様がないと、諦めて る。正直言えば、もう勘弁してよ、と思ってるが、見栄もあって、黙ってる。 「リス(栗鼠)」と「トラ(虎)」がなんで急に持て囃されるようになった か理解できない友人に、「トラ(虎)」と「ウマ(馬)」っていうのも流行っ てるようですよ、と教えてあげた。 その友人は、尻取りみたいですね、とまるでその意味など気にも留めておら れん様子。そう、こういう手もある。一々気になどしちやおられんくらいに次 ぎから次へと最近の外来語は浮かんでは直ぐに消えてくのだから。
取り敢えず私のような個人零細自営業者には直接「リストラ」は関係ない。 良いですねお宅はリストラも何も関係なくて、と言われたことはある。私に言 わせれば、「リストラ」されるからには「リストラ」されるだけのシッカリし た職場と地位に就いていなくてはならない。況や、する側の地位に就く事など 有り得ない。つまり、私には失う程の確たるものもなく、奪う程の権力もない。 ハナからなにも無いだけで、羨ましがられるのは存外のこと。 テレビで、日本の雇用も終身雇用を見直し、これからは能力主義の時代だ、 個の時代だ、と声高にリストラの必要性を叫ぶ人達。呪文のようにリストラを 唱えるが、それを唱える人達が大学や銀行や公共機関に身を寄せる比較的安定 した所のそれなりの地位の人が多いのはどうしたものだろう。 それと、彼等が言うように本当にそんなに必要なものならもっと早くに、バ ブルに浮かれてた好景気のうちにやりゃあ良かったのに。不景気になってから やるのは如何にも便乗の感が免れない。 テレビご出演のお一人が、「中国でもリストラは・・・」とおしやっておら れたが、どうもしっくり来ない。日本で使われてる「リストラ」と中国での「 リストラ(下崗)」を同じに論じていいものかどうか。制度が違い、組織の形 態も違うのにそれを一緒にし、尚かつそこから結論を導くのは無茶だ。
知人が上海からの手紙を持ってやって来た。半分中国語で書かれていて判ら んらしい。途中から問題がややこし過ぎて日本語の能力が追いつかんようだ。 職場で試験があって落ち着かず返事が遅くなったこと。この試験で職場に残 れるかどうかが決まること。試験に失敗したようで失意の中にいること。もう 一度試験があるのでその準備に入らなくてはいけないこと。結果、経済的にも 苦しい状態にいて、違う職を探そうとも考えてる、と綿々と綴られていた。
で、何だって。と、せっかちな知人。近況報告ですね、と、落ち着き払って 私。そんな位はオレにも判る、職場を首になったってこと。いやいやまだ首じ ゃないの、ここからの説明が難しい、何せ体制が違う国の制度を説明し、仕組 みを話し、最近の情勢と新しく取り入れた方式を語り、さてと、漸くこの人の 場合は、となった時、知人は「合理化」ってやつですね、とのたまう。 懐かしいなあ「合理化」って言葉も。暫くぶりで聞いた。人員整理の意味で は、「リストラ」なんかよりずっと「合理化」の方が意味が取りやすい。中国 はさあ、日本より景気いいそうじやないの、なのにどうして首きるわけ、と知 人。また、同じような説明が続く。首を切られて黙ってるわけ、組合はないの、 の質問に、またまた長い注釈。 首切り、首切りと彼は勝手に決め付けてるが、そうじゃなくて、と何度言っ ても聞き入れてもらえない。おそらく、手紙の主も給与は大幅に減るだろうが、 彼の想像するようなある日突然の解雇、とはならんはずだ。それは保障しても いいが、私が保障したって何の支えにもならんだろう。土台、私とて偉そうに 講釈たれてるのだって、中国の新聞で読んだのと、ついこの間見た中国の連続 テレビドラマの受け売りで、もっと突っ込んだ話になると、よく分からんとこ ろがいっぱいある。 失業保険なんてな制度はおろか概念さえ必要なかった社会が、根底から変わ ろうとしている。困ってるんだろうな。お金をさ、送ってやりたいんだけど、 どう思う。どお、って。だから、幾ら位。やらない方が好いと思う。どうして。 何か変、だから。どこが。お金が欲しいとは書いてない。そうだけどさ、何が できる。なにもできない。
と、二人の話は続く。贈り物は、無論それを受けとり喜ばれることを順い贈 るが、往々にしてそれは贈る側がどう満足するかの問題で、贈る側の自己満足 の為にある、と私は考えてる。知人は、ひねくれた考えだと言う。確かに私は ひねくれてるが、良かれ、と思ってやってることが必ずしもそうではないこと は周知の事実。更に、例えば日本でもリストラの嵐が吹き荒れてるわけだから、 もし日本の友人が中国の彼と同じような境遇にあったら、あんた同じ様にお金 あげる、あげないでしょう。そこんとこも考えてよ。更に更に、何時から始ま った文通か知らんが中国での彼の職場も見たことない、家族の事もそんな詳し くない、そんな人から突然お金が贈られてきたらどう思う、反対の立場だった らどう思う。中国は今、国をあげて変わろうとしてる、文通相手の彼はあまり 器用に立ち回れない方の人間らしい。常にそうした人が犠牲になる。社会の変 革に付いて行けない層がいる。どの国にもいる。組織や、制度は急変できるが、 人はそう簡単には変われない。ならば選択の道は二つ、無理にでも変革に付い ていくか、そんな律義なことは御免とするかだ。 「リストラ」「トラウマ」と聞いて、尻取りみたいですね、と受け流す手も ある。どうせ過ぎてしまえば又新しい何かが目の前に現れるのだから。
ここまで聞いた知人は、やっばあんたはひねくれてる。言いたいことはわか った。贈り物は止した。オレ、シャンハイに行って来るよ、と言った。
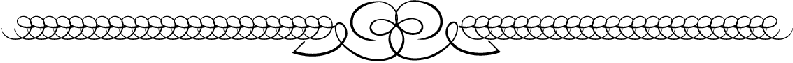
隗報の目次へ戻る