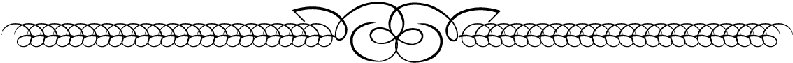
今井 禮子
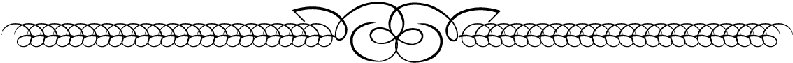
私の滞在した大都会、南京についての印象を思い出して見よう。市内人口約 300万人、その昔、都があった古い歴史の街である。 駅前には玄武湖が広がり、明時代の城壁が修復され市民の憩いの場所になっ ている。街中は緑が多く、特に道路に大きくせり出して、夏は木陰になり、冬 は梢の合間から陽を通すプラタナスの大木の並木は見事だ。日本の京都に似た 街のようにも思える。
上海から南京までは経済的にも国の大動脈に当り、そのベルト地帯はまるで 時を待つのがもどかしいようにフル回転で、どの町も村も変貌を続けていた。 私たちが南京に滞在する4年前に南京を訪れたことのある日本人の一人は、 私たちの処に来て、以前に来た時はビルなどほとんど無かったのに、南京は次 々に高いビルが建ちまるで別の街になってしまったみたいだと、その大都会化 の早さにおどろいていた。小高い丘に有った私たちの住んで居た大学の専科楼 の5階からは南京の様子がよく見えた。当時は窓から鉛筆のようにとがったビ ルが7棟ほど視界に入っていたが現在はどのように変貌したか想像がつかない。 窓からは、あちらこちらで建かけのビルに建材を上げるクレーンが終日動い ているのが眺められ、活力がみなぎり、日ごとにそのビルの高さが増して行く のが楽しみでもあった。 部屋の真下には5〜6階建ての近くにある大病院の職員アパート群があり、 私たちの部屋の窓からは見下ろす形で、否応なしにそれらの家庭の台所の様子 が手に取るように眺められた。毎日、朝夕同じ時間になると、あちらこちらの 食事の支度がいっせいに始まる。 たまに男の人も厨房に入って中華ナベで何かをいためる動きや、掃除や洗濯 物の取り入れなど、家事をこなして居る様子が見えたが、表向き男女同権の国 ではあるが、家庭の中に入れば、やはり女性の方が細々と動き回るのを見てい ると、やはりこの国でさえも家事の主役は女かな、との印象が伺えた。
中国人の日本語教師も5〜6人居たが前任地の田舎のように心が通じ合う触 れ合いが無かった。職場だけの仕事の触れ合いに留まり、彼らの家庭に招かれ て一緒に食事することは残念ながら一度も経験できなかった。 たまに食事に招かれても、いつも少し無理をしているなと思わせるようなレ ストランでの家族との交流であった。 汚いから、狭いから、と言うのがその理由であったが、それぞれ日本への留 学を終えた先生たち、ためらわせたものが何であったか未だに解らない。
南京で友達になった日本女性にNさんがいた。Nさんは昭和5年南京に生ま れ育ち、南京の学校にも入り、敗戦近くまで南京で育っている。 日本で何が有ったか知らぬが、子育てを終え、夫を見送った後、矢も盾もた まらず、サケが死ぬ前に川に帰るように、南京が懐かしく周りの皆にあきれら れながらもその意志を通し、現在たった独りで南京のど真ん中の26階建ての 高級マンションの最上階で暮らしていられる。日本の衛星放送を引き(もち論 公安の許可を得て)大画面のBSテレビがリアルタイムで見られる。 中国語のほとんどできないNさんが、生活のすべてで何かと世話になってい る中国人Wさんのアパートへ誘われて、ひよんなことからNさんと一緒に何の 前触れもなくW宅に連れ行ってもらったことがある。 南京ではただ一度の中国人家庭の訪問であった。Wさんは日本と交流のある 旅行会社に勤めている。年齢は40歳前後だろうか。軍の通訳からの転身で日 本語は流暢である。その時期、日本からの高校生修学旅行受け入れの仕事でち ょうど日本から帰ったばかりのところであった。
アパートの4階、開口一番「狭いよ、だけど農場が近いから便利。」とWさ んは言う。黒光りの5階建てのレンガ造り、暗い廊下、狭い階段が歴史を感じ させる。若いWさんの収入では近くに建ち始めた新築のマンションはまだ遠い のだろうか。部屋の窓を開けると、なるほど狭い。 家具類が大き過ぎて部屋からあふれんばかり、ソファは特大の革製でふかふ かとして埋まりそうだ。大きなサイドボードには中国では流行しはじめたまだ 高価なガラスの食器、グラス類と日本のこけし人形などの飾り物が置かれてい る。人は斜めになって通らなければどこも動きがとれない。
私には他の何より目についたのが、中国の家庭で始めて見たアップライトの ピアノである。都会ではもうこんな時代になっているのかと認識を改めさせら れる。 一人っ子の息子がピアノを習っているのだ。両親から促され、4〜5年生の 子が私たちに今習っている曲をとぎれとぎれ恥ずかしそうにひいてくれた。 そのWさんの自慢の息子は、日本でも公開された「1937年」の映画に早 乙女愛と中国人との間に生まれた子供の子役として出演していたのである。 見回せば居間の壁一面に昔の映画館を思わせるようにべたべたとポスターが 何枚も張ってある。4〜5年前の撮影現場の話などWさんは当時を思い出して リアルに語ってくれた。二年前私が中国に初めて足を踏みいれたとき、滞在し ていた大学ではその南京大虐殺の映画が公開され、抗日学習が盛り上がってい た。 数少ない日本人としては上映されるたびに片身の狭い思いをした記憶がある。 そのころは、日本人として南京だけは行きたくないと思っていた。その後縁が あって南京に滞在し、話題映画出演の重要な子役と対面しているのだから成り 行きとは言え、奇遇としか言いようがない。映画には中国人日本語教師や日本 人の教師も駆り出されて日本軍人として出演したそうである。私は帰国して今 年になって自主上映でその映画を見たが、Wさんの子供は成長著しく当時の子 役の面影は全く消えていた。他の出演者もカットされたのかよく判らなかった。
Wさんの奥さんは美人でスタイルがよく、大きな会社の社長秘書とのことで ある。物事をてきぱき処理するのか物おじせず明るい。奥さんとは日本語が話 せないからWさんの通訳つきでおしゃべりをする。Wさんのお土産なのか日本 の品々を奥の部屋からごっそり持って来て私たちの前に並べて満足げににこに こして見せている。 ご夫妻で何やらそれらについての会話が始まる。折を見て奥さんは私たちに コーヒーを入れてくれた。中国の家庭ではまだ珍しい立派なそろいのティーカ ップとスプーンである。絵柄から多分日本製かと思われた。中国ではコーヒー はネスカフェを売っているのをたまに見かける。コーヒーが一般的な飲み物と して中国人に好まれ出回るにはまだまだ時間がかかるだろう。南京でさえ、大 きなホテルに行かねば本物は飲むことはできない。そしてまだ高価な飲み物で ある。部屋に訪れる中国の学生達にコーヒーをすすめても一度は試しにこわご わ口にするが奇妙な顔をして辞退し決して二度とお代わりはしない。お茶受け にクッキーが出た。日本のメーカーのものである。お土産にいただいたものら しい。Wさんは煙草も日本のセブンスターが好きだが南京には無いという。ハ イライトも中国製(香港)と日本製があるから気を付けなければならない。本当 の偽者も?有るからよく見ないとねと笑っている。
奥さんの着ているトックリの深いこげ茶のセーターも上質な既製品(高級品) である。ブローチなどあしらい、なかなかセンスがよくおしゃれである。そし て、お二人ともただいま流行のステータスシンボルである良質の革のコートを 着ていた。Wさんは黒、奥さんは緑色のロングコートとヒスイの指輪である。 デパートや繁華街を歩くと、艶の有る色とりどりの革のコートの若い男女が かっ歩し始めている。多分まだ高嶺の花だろうに。日本円で一着2〜3万はす る。 高価なカシミヤもあるが流行ではないらしい。色彩やデザインが私たちとは 感覚が少し異なる気がした。デパートではカシミヤの人気が今一つと思われた。
南京の冬は思ったより寒い。揚子江より北は、雪が少なくシベリヤおろしの 冷たい刺すような風が吹く。革のコートはその冷たい風を通さない理にかなっ た衣服である。革の素材はまだ新しい。それが流行と結びついたと思われ、こ の冬は高級衣料品店ではどこもかしこも革、革のコートに埋め尽くされている。 革製品はまだまだ高価である。しかし、おしゃれに人々の気持ちが向くように なったことは、それだけ生活にゆとりが生まれ、豊かになっている証拠だ。や はり大都会である。経済力があるのだと思われる。大きなデパートの一階では バックと革のコーナーが、数多い化粧品の次に場所を占め始め、イタリー製の ブランドものの革のバックも有った。お金の出し入れもポケットからではなく、 おしゃれな革の財布から女性がお金を出すのも大都会の南京では珍しくない。 しかし、ひったくり防止のためかショルダーバックはどの女性も首から脇に掛 け、日本の中学生の通学かばんのようにしっかりとたすきにかけている。私は、 始めはあまりにもそろい過ぎた女性の同じ姿に、不自然で奇妙な光景に見えた。 さりげない肩がけの方がおしゃれだろうにと思っていた。間もなくその訳がわ かる時が来た。
ある日、わたしはいつものように手提げの中に財布を入れてバスに乗り、南 京博物館前のボロ市に行った。前から目につけていた端渓のすずりを再び見つ けて、値切りに値切った末に喜び勇んで買って帰りのバスの中で見事に財布を すられたのだ。そのバスはそんなに込んではいなかった。私の側にだれもすり 寄って来た人も居なかったように思っている。乗り換えなしの一本の路線で立 っていた何分かの間である。帰宅していくら考えても、降り際だったろうか、 どこでだろう、などと繰り返し様々な場面を思い出して見ても解らない。すら れるようなスキは無かったと思って居る。今もってまだ解せない不思議のひと つである。 しかし、現実はお見事としか言いようのない手品のような手技であった。カ モを見誤ってか、その成果がくたびれ果てた空に近い財布で申し訳なかったが、 ただ、その日買ったばかりの未使用の百元のテレホンカードがいまだに心残り ではある。こうした私の体験から、安全上、多少格好が悪くてもしっかりとバ ックは身につけ身体の前に回し、気を配らねばないのだ。野暮と言われようと 生活の知恵から生まれたスタイルなのである。口の開いた手提げなどプロには 難ないものに違いない。自分たちと文化の違う国に居て、不思議だ、何故かな、 と感じる裏には必ずそれなりのその国の理由が隠されているのだ。
Wさんの奥さんはホンダのスクーターで通勤している。Wさんもホンダのス クーターに乗っている。以前住んで居た山東省済南市では私たちの宿舎では私 たちの宿舎に何の仕事をしているのか解からぬ青年が一日中バイクを磨いて満 足げに終日過ごしているのを不思議に思ったことがあるが、この国ではこうし た個人的乗り物を持つことは、日本での高級外車を持つことに匹敵することな のかも知れない。 Wさんは自家用車は公用車か、会社持ちでなければ、税金、維持する費用、 車庫など様々な問題があり、個人で持つことはまだできないと言っていた。今 のままで中国の人達がみんな車に乗り始めたら世界の環境破壊になるだろう。 リッチなWさんの次なる夢はやはりWさんのアパートの周りに建ち始めたマ ンションらしい。Wさんのような日本と中国を行き来しながら仕事をバリバリ し、売上げが収入に比例する人達にはその夢も手がとどきはじめ、近いのかと 思う。あるいは今ごろはどこかの物件を物色しているのかも知れないと思った りする。繁華街を歩いていると、別荘の売り出しのビラなどが手渡され、日本 人と解るとつきまとわれる。自由に売買できるのだろうか。 南京には日本の料理店が私の知ってるだけで4軒もあり、さらにもう一軒で きると聞いてる。ラーメンもカレーも刺身も有るし、接待用の会席コースもあ り、和服を着せられた中国人ウェイトレスもいる。商売として成り立つからに はそれだけ需要があるのだろう。欧米式のレストランも同様である。
南京で私たちの知り会った中国人は学生か、公務員の日本語の大学教師しか 居ない。大学の教師たちは多分Wさんのようにまだ経済的に豊かでは無いと思 う。しかし、日本の企業の進出によって日本語教師たちも何らかの日本との接 点を求め、幾つかのポケットを持ち、言葉を駆使して、日本人に中国語を教え たり、通訳や翻訳のアルバイトをしているのではないかと想像された。 時には、真新しい日本経済新聞の何日か分の束などを持って来て活字に飢え ている私たちを喜ばせてくれたりした。また、突然電話がかかり、「これはど う言う意味か。これはどう言う言い回しをすればいいのか」と言った日本語の 教科書にはまったく関係のない畑違いの専門語の意味や質問をされ、彼らの生 活の一部が想像された。医師、弁護士、教師、「シ」のつく職業は中国では社 会的地位が低いと聞いている。中国が経済的に発展すれば、大学で勉強した貴 方たちの職業が見直される時代が必ず来るからと若い人達や先生方に言ってき た。近々大学の教師の給料が上がると聞いて居る。それが、その兆しであるこ とを願って止まない。
中国では都市と農村と自由に居住することができない仕組みになって居る。 生まれた所が運命の分かれ道とも言える。あらゆる意味で都市と農村の格差が 縮まり、中国がさらに豊かになって行くのを日本から眺めている。 勝手なもので時間を経るとともに、あの中国の生活が懐かしいものに変わっ て来つつある。何の気負いも無く仕方なくついて行ったにもかかわらず、いつ の間にか中国にはまり、取り込まれたのか、それとも帰国してからの日常があ まりにも平凡すぎるのか、何かと中国が気になってテレビや本などに目が向く。
中国で過ごした900日がこの後、私の中で貴重な心の財産になって行くよ うな気がしてならない。南京は紛れも無く中国の大都会であり、これからもビ ルが建ち続けて行くだろう。今も、夫子廟のあの川は相変わらずよどんでいる だろうか。 狭い路地のお店には小鳥や犬猫の市場が開かれているのだろうか。振り返る とあの街のざわめきが聞こえてくる。
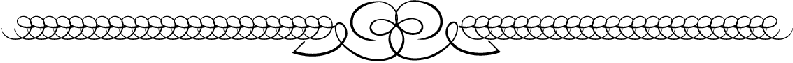
隗報の目次へ戻る