「グリーン、昼メシできたよー」
束の間の休息となったある日、レイは昼食の準備を済ませると、外に出て薪を割っているグリーンに声をかけた。
「ああ、こっちも丁度終わったよ」
額の汗を軽くその手で拭いながら、グリーンは眩しそうに目を細め、顔を上げる。
どこまでも続く青空に輝く太陽。昼寝でもしたくなるような爽やかな風が吹き抜けている。
そんな陽気のなか、薪を割っていたグリーンは、じんわりと心地よい汗をかいていたようだ。上着を脱ぎ捨て上半身裸で、汗に光る体を水に濡らしたタオルで拭っていた。
普段はゆったりとしたシルエットの服を着ているためあまり気付くことはないが、グリーンは着痩せする性質のようだった。スラリとしたシルエットからは想像できなかった、しっかりと発達した上半身の筋肉。形よく、バランスの整ったその体は、決して下品な印象を与えるものではなく、むしろ彫刻のような美しさに憧憬の念を抱くほどだ。
戦場でレイが嫌というほど見てきた偏太りの筋肉バカのような男とも、ガリガリにやせ衰えた体にいびつに筋肉をつけた貧弱そうな男とも違う。男としての逞しさだけでなく、その体の美しさをも兼ね備えた異性を、レイは今まで見たことがなかった。
知らず知らず、その剥き出しの上半身に目を奪われていた。
「どうした? レイ」
声をかけられてハッとする。
そして、グリーンの裸に見とれていた自分に気付き、頬が紅潮した。
「レイ?」
訝しげにもう一度、グリーンは声をかけた。
「あ、ううん。何でもないよ」
赤くなった頬に気付かれないように、レイは顔をそらす。
「頬が赤いぞ。熱でもあるんじゃないか?」
折角そらした顔を覗き見るグリーン。慌ててレイはその場を離れ、家へ向かう。
「大丈夫。スープ作って火にあたってたからだよ、きっと。さぁ、昼メシ食おうぜ」
「・・・そうか? ならいいが」
グリーンもレイの後に続く。
レイは自分に驚いていた。こんなことで、こんなに心臓が早鐘を打つことがあるとは。
自分の鼓動が耳について離れない。紅潮した頬は益々その赤みを増していく。こんな経験をしたことは、今まで一度とない。戦場で、死に直面している時ならまだしも、日常の平和のなかで、こんなに緊張や動揺をすることがあるとは。
向かい合って昼食を摂っていても、まともにグリーンの顔を見ることもできず、俯きがちになる。
突然そんなレイの視界に、しなやかな指が飛び込んできた。
「!!」
「髪が随分と伸びてきたな。私がそろそろ切ろうか」
レイの前髪を指で梳きながら、グリーンは呟く。
「え!! い、いや、いいよ」
あまりにも突然、グリーンに髪を触れられて、レイは再び慌てた。頬に火がついたかのように顔が熱い。その鼓動は大音響でレイの身体中に響き渡り、外に洩れでやしないかと心配するほどだ。
「・・・今日は何だか変だぞ、レイ。髪を伸ばすつもりなら別に構わないが、前髪くらいは切ったらどうだ? そのほうが視界が広がっていいだろう」
顔を覗き込もうとして距離を縮めるグリーンに、あたふたとしながらレイは席を立つ。
「と、とりあえず、メシの後片付けをしなくちゃ。それから、じゃぁグリーンに前髪だけ切ってもらうよ」
「そうか、まかせておけ」
優しい声で、グリーンは微笑みながらレイの背中に語りかけた。
そうして昼食の後片付けが済むと、レイを椅子に腰掛けさせて、グリーンは現代でいうハサミのようなものを取り出した。
「・・・? それで切るの?」
レイは不思議な声で問いかける。
「これではさみ切るんだ。知らないかな? そうだな、それもそうか。精霊界にも人間界にも、こんな道具はあまり無いかもしれないな。私が作ったものだから」
「へぇー、そんなこともできるんだね」
「そうとも。武器類の手入れをしなくてはならなかったし、必然的にね。こういった片手で安全に扱えるものがあると、いいだろう」
「うん。それもそうだ」
そう、現代から千五百年程の時を遡ったこの当時、そのような道具はまだまだ日の目を見てはいない。ナイフやダガーで髪を切るよりも、手軽で安全なこの発明を、グリーンはとても気に入っていた。
「さぁ、切るぞ」
「あ・・・うん」
レイは目をつぶった。
刃が擦れ合う音と、前髪に触れるグリーンの指の優しさ、温かさ。
先程までの動揺が嘘のように、連続していく作業音が心地よい。
何を緊張する必要があったのだろう。別にありのままの気持ちで良いではないか、自分はグリーンのことが大好きだ。フルーラが死んでから、レイは人を好きになることを忘れてしまっていた。そして、ようやくその心を取り戻したのだ。それも、一個人として見守ってくれるグリーンがいたからである。どんなに厳しい修行も、それはレイのことを真剣に受け止めていてくれるからこそのものだと理解している。だから、レイはグリーンを家族のように大切に思えるのだ。
グリーンは、あたしの憧れの人だ。あたしもグリーンみたいになりたい! そうだ、グリーンのように髪を伸ばそう。それから、言葉遣いももう少し女らしく、丁寧にしよう、グリーンに認めてもらえるように―――
レイはそう心に決めて、ゆっくりと目を開いた。
そこには、微笑むグリーンの顔があった。
|
  
|
そうして十年、レイはグリーンの元で剣術の稽古を続けていた。髪はグリーンと同様に腰まで伸ばし、後ろでひとつに束ねていた。まだまだ幼いその姿かたちも、一度剣を握れば成人顔負けの迫力と技量を発揮する。グリーンの特訓だけでなく、恐らく天賦の才も備わっていたに違いない。優れた指導者をみつけ、その才能が開花したようだった。
「レイ、少しいいか」
素振りをしていたレイの元にグリーンが現れた。
「なに? グリーン、私に何か?」
手を止め、レイは振り返る。いつの頃からか、レイの言葉遣いもすっかり女らしくなっていた。
「そろそろ良い頃合ではないかと思ってね。君の剣技も随分と上達したから」
そういって、グリーンは掌をレイの目の前に広げた。
「え? 何!?」
「―――実は、出会った頃から気になっていたんだが、あまりに幼くひ弱な体には、恐らく耐えられないと思って、今日まで触れずにいたんだ」
「え!?」
グリーンの掌が、異様にまぶしく感じて、レイは思わず目を閉じた。
「誰かが・・・恐らくは君の育ての母が、君のことを想い、封印したのだと思うが・・・これから教えていくことには必要となるはずだから、申し訳ないが封印を解かせてもらうことにするよ」
グリーンの言っている意味が、レイにはよくわからない。「封印」? 何を封印したというのか―――
「目を開けてごらん」
しばらくすると、グリーンがそういった。
レイは恐る恐る目を開ける。もうまぶしさは感じないようだ。
「・・・やはり、そうか」
「え、何が? ねぇ、一体どうなっちゃったの、私」
「ああ、そこの小川に姿を映してごらん」
グリーンに促され、水面に自らの姿を映し出したレイは、驚きの声をあげた。
「!! これって・・・」
そこに映る自分の姿、ただその瞳はまるで紫水晶のように、透き通った紫色に変わっていた。
今まで、自分の瞳はフルーラと同じ桜色だと思っていた。いや、桜色だった。それが、封印の下に隠れていた瞳が、まさか紫瞳だったとは。
精霊の能力の強弱は瞳の色として表れる。一般の精霊たちの瞳の色は黒瞳で、それが大部分を占めている。それから、橙瞳・桜色瞳といった、少し特殊な能力を有する者たちがいる。それでもそれは、まだ一般的な精霊たちと近しい存在で、フルーラはその部類に属していた。ただ、一般に近しい存在ではあったが、全土に知られる戦闘能力に長けた精霊であったため、妖魔狩りを生業とすることができたのだ。その、更に上位に位置する翠瞳・黄瞳・碧瞳・紫瞳といった精霊たちは高格精霊と呼ばれ、そのほとんどが貴族と呼ばれる階級になり、守護精霊の任を受け、人間界へ派遣されたりしているのだった。それはもちろん、精霊界全体から見れば、ほんのひと握りの存在にしかすぎず、レイもそんな高格精霊は今までに三人ほどしかお目にかかったことがない。そして、その最上位に位置するのが、精霊界の女王である聖女王唯一の瞳である金色瞳と、その一族のみといってもいい程に少数しか存在しない白銀瞳である。あまりにも少数しか存在しないため、レイたちのような一般の生活区域に生活をしていた者は、その存在すら知らずにいることが多く、レイもそれは例外ではなかった。
つまり、レイが知るなかで最も強い力の表れである紫瞳が、自分の瞳に隠されていたという事実は、まさに青天の霹靂のようであった。
「・・・グリーン、悪い冗談はやめてもらえないかしら・・・」
ようやく口から出たことばは、それであった。
「いや、冗談ではない。君は身寄りがないといっていたが、恐らくはやむにやまれぬ複雑な事情があって、どうしても君を育てることができずに、人に託してしまったのではないだろうか。そうでなければ、大切な我が子を手離すことなどできないだろう」
特に、それほどの強い能力を持つ者ならば、この乱れた世の為を思えば、誰しもが黙っていないはずである。それを手離すということは、人知れず産み落とされた不運の子であるか、とてつもない問題を抱えていたかといった見当もつく。
実際、噂でしかなかったが、その瞳の色を見て、グリーンはレイの親の見当がついていた。しかし、敢えてそのことを口にすることはなかった。
「・・・私・・・どこかの貴族の子だったかもしれないの?」
「そうだな。その可能性はある」
「そう・・・」
信じられない話だった。フルーラとの暮らしは幸せであったが、決して裕福なものではなかったし、フルーラの死後の生活は悲しみと苦しみに満ちていた。―――グリーンに会うまでは。しかし、あの妖魔との苦しい戦いの日々がなければグリーンと出会うことはなかっただろうし、最近は苦しかった日々にも感謝の気持ちを持てるようになった。それにいくら貧しくても、精一杯愛し育ててくれたフルーラとの生活は、何にも代え難い宝物である。
「もし、どこかの貴族の子どもだったとしても、捨てられてよかったわ。きっと今の私みたいに充実した日々を知ることはできなかったと思うから。それに、私の母さんはフルーラ母さんだけでいいもの。フルーラ母さんのこと、大好きだから。あ、グリーンのこともね」
衝撃の事実を告げられたというのに、自分でも驚くほど冷静でいられた。恐らく、満ち足りた生活を送ることができているからなのだろう。グリーンとの十年の日々は、レイの心をも大きく成長させていた。
「そうか、ならいい」
グリーンも安堵の笑みを浮かべた。封印を解き、事実を白日の元に晒すことは、大きな不安を伴う。いくら大丈夫だと信じてはいても、わからないのが人の心なのだから。
「さて、修行を始めるぞ」
「はい!」
迷いのない、すっきりと通る返事。グリーンはレイの心の成長を喜ばずにはいられなかった。
|
  
|
そうして、新しい修行が始まっていた。それは気を練り上げて自在に操れるようにするというものだった。その力をマスターすれば、剣技に応用できる。剣技と気のふたつを同時に操ることができて、ようやくグリーンとレイの目指す剣士となれるのだ。
「指先に気を集中させるんだ。指先が熱くなるのを感じるはずだ。雑念を捨てろ」
そう言われて、すぐにできるものでもない。
いくら雑念を捨てろと言われても、捨てようと思えば思うほど、いろいろな思いに支配されてくる。
「折角封印を解き、力を解放したというのに、なぜその力を操ることができないんだ。それでは、まったくもって意味がないじゃないか」
「ねぇ、グリーン」
「ん、何だ」
「こんなに大変なやり方じゃないとできないものなの? これじゃぁ、あまり実用的じゃないと思うんだけど」
それはそうだ。こんなに時間がかかるようでは、咄嗟の時に役にはたたない。
「最初だけだ。最初の一回が難しい。慣れてしまえば、何気なくでも放てるものだよ。例えばこんなふうにね」
グリーンはすっと指を正面にある木に向ける。すると、その次の瞬間に木の枝が一本、折れて地に落ちた。
「え!! すごい!! すごいよ、グリーン」
あまりにもさりげなくなされた一瞬の出来事に、レイは素直に感動した。
「レイ、君もこれくらいできるように頑張ることだ」
「はい!!」
レイはグリーンが見せてくれた手本を思い出しながら、静かに目を閉じる。先程までの疑念や雑念がすっきりと払拭されていた。レイのその脳裏にはグリーンの見せてくれた手本だけが強く焼きついていた。
指先が熱くなる。指先でパチパチと小さな音がした。
「グリーン、見た? 今の感じでいいの?」
レイは目を開くと振り返り、グリーンを見やった。
「グリーン!?」
そこにあるのは、地に倒れ伏したグリーンの姿だった――― |
 |
各章へジャンプできます |
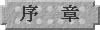 |
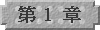 |
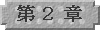 |
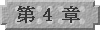 |
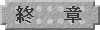 |

