サイラからの誘いで大学へ通うことを決めたレイの元に、大学関係者がやってきた。
大学の事務長官だという彼が抱えてきた資料はとてつもない量で、いかにこの大学が大きく、伝統があり、立派なものかということを、滝から流れる水の如く、惜しげもなく延々と語りつづけていた。
レイはその話にはほとんど耳を傾けず、目の前に山のように積み上げられた資料に目を通す。彼の話を聞かずとも、知りたいことはその資料にすべて書いてあったからだ。
ちょび髭を生やした事務長官が話しつづけて一時間半を経過した頃、レイはすべての資料に目を通し終え、自分の世界にすっかり浸りきっている事務長官に声を掛けた。
「あの、よろしいですか? 早速受講の手続きというのを進めていただきたいのですが」
「おお、おお、そうでしたね。では、こちらの羊皮紙に希望される講義の名称を記入してください」
忘れていた、といった感で慌てて胸元からひと巻きの羊皮紙を取り出すと、事務長官はレイの前に羽ペンと共にそれを差し出した。
羊皮紙を受け取ったレイは、早速希望する講義名を書き出し始める。まだ、学ぶかどうか、迷っていた講義もあり、それらを記入すべきか考えていたが、事務長官の「後ほど追加することもできますよ」ということばで、今回は見送ることにした。
「はい、確かにお預かり致します。ひのふのみぃ・・・6講座ですな。学び始めるのには適量でしょう。では、カリキュラムを組みましたらまたご連絡致します。来週には、講義への出席が叶うはずですよ。では、よく学んでください」
そういうと、羊皮紙をくるくると巻き直し再び胸元に収めた事務長官は、レイの部屋から退室していった。
事務長官がつけていた甘ったるい香料の香りだけをそこここに置き去りにして。
レイが受講を決めた教科は、歴史、魔法術、呪術、薬学、宇宙学、心理学の6科目。まずは実用的な教科をメインに選ぶというところがレイらしい。
来週には――という事務長官のことばだったが、一日でも早く学んでみたい、とレイはその待ち遠しさを隠せなかった。
|
  
|
一週間ほど後、ようやくレイが大学へ通う時がやってきた。
前日の晩などは、幼い子どものように夜遅くなってもなかなか寝付けず、その期待の大きさを窺えた。それは、今教室へ向かう足取りの軽さからも窺い知ることができるだろう。
今日の午前中は「歴史」の講義がある。
レイにとっての一番目となる講義。その「歴史」の講義が行われる教室へ到着すると、ひと呼吸おいて扉を開く。
「!」
その室内にいた人数は多くなく、十人に満たないほどだった。さらにどうみてもその外見は五百歳に満たない幼女たちである。
自分と行って返る程に年の違う少女しかいないことに、レイもかなり面食らってしまった。
取りあえず、空いている椅子に腰をおろす。
室内の少女たちの多くが、ひそひそとレイを見ては何かを話していた。
後で知ったことだが、レイの受講する教科の中で、この「歴史」だけはほとんどの者が幼い頃に受ける講義だという。この世界の歴史を幼い頃から学び、そこからより良い将来を自らで作り上げていくことを望んでいるのだそうだ。
レイが幼い時を過ごした居住区は、この月花城からは遠く、周囲に大学へ通っている子どもなどいなかった。レイももちろん。大学の存在自体知りもしなかった。知っていたとしても、ここまで通ったかどうかは定かではないが。
さて、どうしたものか――自分の所在のなさを感じ、落ち着かずにいると、眼前にひとりの少女が現れた。
その少女はふわりと柔らかそうにウェーブしたプラチナブロンドの髪を持ち、さながら天使の巻き毛のようである。両の碧瞳はきらきらと輝き、薄桃色の小さな唇もまるで果実のみずみずしさ。こんな幼い頃より持つ美貌は大人となったとき、どれほどその魅力を増すのか、と考えずにはいられないほどに愛くるしい少女。そして何より育ちの良さそうなその衣服。自分の幼い頃と比べれば、こうも違うものなのかと愕然としてしまう。
「ねぇ、あなたレイでしょ?」
小鳥がさえずるような高く美しい声で、その少女は語りかけた。
「え、ええ」
戸惑いながらも、レイも返事する。
「やっぱり!! あなたのこと、あちこちで噂になってるのよ」
「・・・そう」
それは先程教室に入ってきてからの周囲の者たちの様子で充分に感じていた。それをわざわざこんな幼女に教わる必要もない。
そっけないレイの返答に、少々肩をすくめてみせると、それでも少女はレイに語りかけた。
「あのね、あたしはセルリア・クライスターっていうの。よろしくね」
レイの目の前に自らの右手を差し出しながら、その少女――セルリアは笑顔を見せる。
「コーガー。レイ・コーガー」
セルリアの差し出した右手に己の右手をほんの瞬間触れ合わせると、レイはすぐにまた右手を引っ込めた。
なんとなく気に入らなかった。こんなに年の離れた少女に対等に、あるいは優位に立たれていると思うと、苛立ちを感じた。
「取りあえず、よろしく。仲良くしてね」
これ以上話しかけてもムダと悟ったのか、セルリアはそう言い残し、自らも教室の前方の空席についた。
すると程なく訪れた教師により、レイの初の講義「歴史」の時間は始まった。
この自分たちが生活する精霊界の歴史。それは奥深く、多彩に彩られている。現在この世を統べる聖女王以前より始まりまで、ほとんどの時代でその座についていた女王たちの中ただひとり、先代のみが男王だったことも、レイにとっては始めて知ることだったし、古から妖魔との戦いが続いていたことも知らなかった。
教師によって語られる歴史の流れは、レイをあっという間に虜にした。
ただ、講義中度々後ろを振り返り、自分を笑顔で見つめるセルリアを目の端に留めながら。
|
  
|
その日は、もうひとつ講義を受けることになっていた。
「歴史」の時間が終わると、レイは早々に次の教室へと向かう。セルリアの話しかけたげな様子は伝わってきたが、こちらはそんな気分になれなかった。
次の講義は「宇宙学」。これは、科学的に星々のことを学ぶとともに、星を見て世を占う”星見”についても学ぶことのできる講義である。
こちらは「歴史」とは打って変わって、レイよりも少々年上の者が多いようだった。それでも、「歴史」と変わりなく、人々が奇異の眼差しや蔑視を送っていることがすぐに感じとれた。何故そうまでされるのか、レイにはわからなかった。
「貴女に、ひとつお聞きしてもよろしいでしょうか?」
空席に腰を下ろしたレイに声がかかる。
自分の横に立ったその女性は、銀色の瞳でレイをみつめていた。
「・・・何でしょうか」
その銀色の瞳と銀髪を持つ女性の、穏やかでいて威厳ある立ち姿に少々戸惑いながら、レイは答えた。
途端、教室内は水を打ったような静けさを迎える。皆が固唾を飲んで事の様子をうかがっているようだ。
「貴女が毎夜、聖女王様の私室へ招かれているというのは、本当ですか?」
「え、はい」
何を質問されるのかと思えばそんなことかとレイは即座に答えた。
周りの人々がざわつく。
「それが、何か?」
続けて今度はレイが問いかけた。
「いえ・・・そこで貴女が何をしているのかをお聞きしてもよろしいでしょうか?」
「は?」
質問の返答としてまたしても質問が返ってくるとは思わず、レイは少々唖然とした。
「別にたいしたことは何も。聖女王様が話が聞きたいと仰るから、お話をしているだけです」
「どのような?」
レイは気分が悪くなった。何故こんなまったく知らない人にあれこれ詮索され、根掘り葉掘り質問されなければならないのか。それに対し、正直に答えなければいけないという義務もないだろうに。
「・・・それはこちらの勝手でしょう!? プライバシーに関わることなので、お話できません」
まっすぐその銀髪で銀瞳を持つ美女を見つめ返しながら言い放つ。
それに対し、美女も視線を逸らすことなくレイの紫瞳を見つめた。
「ふふふ。そうですね、立ち入ったことまでお聞きしてしまい、申し訳ありませんでした」
しばらくして彼女が笑顔で口を開いた。その笑顔は優しく和やかで、レイの心を氷解させてしまう気がする。
「貴女に対していろいろな噂が飛び交っているものですから、真実をお聞きしたかったのです。気分を害されてしまいましたね。でも、お陰で噂が噂でしかないことが、これで良くわかりました。貴女は嘘のつけない人ですね」
「はぁ・・・」
なんとも納得いかない気がしたが、何かしらの誤解が解けたというのならそれでもいいか、とレイは気の抜けた返事を洩らす。
「申し遅れました。私はダイアナ・モーゼです。この講義では一番年配者となります。わからないことがあれば、何でも質問してください。お答えできる範囲でいくらでもご協力いたします」
「あ、はい。私はレイ・コーガーです。よろしく」
思わずどぎまぎしてしまう。こんなに丁寧な言葉遣いで優しく微笑まれたら、男女問わず頬を赤らめるに違いない。銀髪銀瞳の美女ダイアナは、誰に対しても公平な態度でいられるということを知ったのは、その少し後だった。
「さぁ、皆さん。誤解は解けました。私が言うのですから、間違いありませんよ。もう、この噂はおしまいにいたしましょう」
先生がそうするように、ダイアナは教室内の皆に呼びかけた。
その途端、今までと打って変わって室内は和やかな雰囲気になる。
そしてレイは悟った。
ダイアナはレイの為を思い、あのような質問をしてきたのだ、ということを。それだけの影響力を持っているのだということは、周囲の様子を見れば明らかだったし、ダイアナ自身それを理解しているからこそ、ああいった行動に移せたのだろう。噂だけが先行し、どの教室へ行っても気まずい思いをしなければならないのを、ダイアナは良しとしなかったのだ。実しやかに流れていた噂がどんなものだったのかはレイは知らないが、その噂を払拭するダイアナのお手並みの素晴らしさにただただ脱帽してしまった。
それから、すべての人が誤解だったと信じてくれなくても、幾人かはレイを見ると笑顔を向けてくれるようになったし、レイの頑なな表情も和らぎ、互いにことばを交わす交流も生まれた。
たくさんのことを学ぶことができ実りの多い時間ばかりで、レイは本当に大学へ来ることができてよかった、と思わずにはいられなかった。
|
 |
各章へジャンプできます |
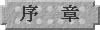 |
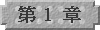 |
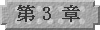 |
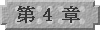 |
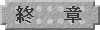 |

