「大学での講義はどうですか?」
聖女王サイラの部屋へいつもの如く招かれていたレイに、サイラは尋ねた。
「はい、今までまったく知りもしなかった多くのことを学ぶことができて、とても楽しく思っています。このように学ぶ機会を与えてくださって、本当にありがとうございます」
レイにとって、大学で学ぶ事柄は本当に新鮮で、幼な子のように貪欲に知識を吸収したいと感じていた。そしてその機会を与えてくれたサイラに対し、感謝の気持ちが波のように押し寄せる。
「よかった。私も貴女に大学へ通うことを勧めた甲斐がありました。私としても、学びたいと思う者に学ぶ機会を多く与えたいと常日頃考えているのです。ところで・・・大学で特に困ること等はありませんか?」
「――! いえ、特には・・・」
レイは一瞬ことばに詰まった。大学で蔓延している何かしらの噂――そのために、初めは周囲の者との関係がうまくいかなかった。しかし、ダイアナの計らいでそれもなんとかうまくいくであろう。サイラは何でもお見通しなのでは、と少々驚いた。
「そうですか? なら良いのです」
レイの様子を目に留めつつ、レイが何もいわないのであれば深く追求することは止めにしよう、そうサイラは考えた。
実はレイの一日の行動は、逐一サイラに報告が入るようになっている。そのために大学で何があったのかもすべてサイラは知っていた。
しばらく他愛のない話などをして夜も更けると、レイはサイラの部屋を後にすることにした。
「それではサイラ様、今日はこれにて失礼します」
「あ、レイ・・・」
「はい?」
何かを思い出したかのようにサイラはレイを引き止めた。
「以前より尋ねてみたかったことなのですが、その紫瞳は生まれついてのものですか?」
「え? あ、はい」
瞳の色は、その者の能力の高さを表しているということをレイも知っている。 紫瞳はそのなかで、金色瞳、銀瞳に次ぐ高い能力を持つことを示しているのだ。
まさか自分がそんな瞳を持っているということは、グリーンに会うまで知らなかった。それは捨て子だったレイを拾い、育ててくれた義母フルーラによって封印されていたからである。
そのような経緯を、レイはサイラに語った。
「――そうだったのですか・・・込み入ったことを訊いてしまいました。申し訳ありませんでした」
「あ、いいえ! でも、そのお陰で今があるのでちっとも辛くないですし、捨てられて良かったと思っているくらいです。気になさらないでください。でも・・・それが何か?」
「いえ、何でもないのです。紫瞳は珍しい色だったものですから・・・」
少々上の空といった感でサイラは答えた。
「ならいいんですけど。では、私は失礼します。おやすみなさい、サイラ様」
「おやすみ、レイ」
レイはサイラの部屋を後にした。
ただひとり、部屋に残されたサイラは神妙な面持ちである。
「レイがあの時の――、だからグリーンはレイを私の元へよこしたのですね・・・」
それぞれの運命という名の歯車が噛み合う瞬間を、サイラは痛感せずにはいられなかった。
|
  
|
一週間後、再び「歴史」の講義に出席するために教室へ向かうレイは、少々気が重かった。
それはあの少女、セルリアのことである。
考えてみれば、彼女は彼女なりにダイアナのように、噂に振り回されていた他の級友たちを良しとせず、なんとかレイの居心地を良くしようとしていたのだろうと感じられた。
悪い少女ではない、それはわかっている。
「レイ、おはよう!!」
「・・・おはよう、セルリア」
ただ、セルリアの明るい声、幸せそうな笑顔を目にすると、何故か憂鬱な気分になるのだ。何も悩みなどなさそうに感じてきて、いらつきさえ催す。
「ねぇ、レイ。あなた、ダイアナ様と同じ”宇宙学”を受けているんでしょ?」
「え・・・? ええ」
レイのそんな気持ちをよそに、セルリアは相変わらず朗らかに話しかける。
「うらやましい!! あのダイアナ様と一緒の講義を受けられるなんて! あぁ、早くあたしも大きくなりたい・・・。ねぇ、ダイアナ様とお話しした?」
セルリアは頬を紅潮させてレイに問う。
レイは、ダイアナの影響力の大きさを感じてはいたが、一体ダイアナがどんな人物なのかということをまったく知らなかった。だから、何故セルリアがこんなに羨ましがるのかが気になった。
「・・・ダイアナ様って・・・?」
恐る恐る口に出した問いに、セルリアの表情は一段と明るさを増して、レイはたじろいだ。余計なことを言ってしまったか?!
「レイから初めて話しかけてくれた!! うれしい!!」
――やっぱり。こういったタイプだろうとレイも想像していたが、まさかこうまで単純とは。レイはこれからもセルリアにつきまとわれることになるのか、とドッと疲れを感じた。
「えっと、ダイアナ様はね、聖女王様のお従姉妹様なんだよ。ダイアナ様のご家系は名家中の名家で、その内なる能力もすっごく強くていらっしゃるの。ダイアナ様の瞳の色、ご覧になったでしょ? 銀瞳なんだよ。この大学のみんなの憧れのお方なんだから」
うっとりと宙を仰ぎながらセルリアは語った。
そうだったのか、ダイアナはそれほどの立場の者だったのか。そういえば、グリーンの瞳も銀色だった。そう考えると、サイラに近しい立場の者だということも自ずと理解できる。
セルリアの存在も、考えようによっては役に立つかな? と、レイは考え方を少し改めた。
|
  
|
セルリアにダイアナのことを教わってから、レイはダイアナの存在の大きさに心を奪われてしまった。「宇宙学」の講義が終わっても、ダイアナについてまわり、一緒に会話を楽しんだ。
ダイアナも、素直で実直、そして頭の回転の速いレイと話をするのを楽しく思い、多くのことを語って聞かせていた。
「私、”歴史”の講義も受けているんですが、初めて講義を受けた日はすごく驚いてしまいました」
「まぁ、何故です?」
「だって、私より皆随分と年下なんですよ」
「ふふふ。そういわれればそうでしたね」
感情豊かに表情を変えるレイの話し口に笑みを洩らしながら、ダイアナは更にレイのことばに耳を傾ける。
「その講義を受けている子のなかに、ひとりだけすごく・・・私に興味を持った子がいるんですよ・・・」
鬱陶しい、はたまたまとわりついてくる、といった形容をしたいところだが、流石にダイアナの手前では気がひけて、レイも慎重にことばを選びながら話す。
「ご存じですか? セルリア・クライスターっていう子なんですけど・・・」
レイがダイアナの様子を窺うと、ダイアナはこくりと頷いた。
「セルリアはクライスター家の次女です。クライスター家は代々水晶の守護精霊としての重役を務めている名家です」
やっぱりそうなんだ――レイは納得した。どうみても悩みのなさそうなセルリアの様子は恵まれた環境に身をおいているからだ、自分とはまったく違う存在なのだ、と感じた。
「セルリアは、本当に明るく素直な良い子です」
ダイアナがセルリアのことを誉めるのが、レイには気に入らなかった。
「本当に。悩みなんか知らない、といった感じですよね」
ついつい、軽い嫌味が口から出てしまった。
するとダイアナはレイの顔をじっとみつめ、そしてひとつ溜め息をついた。
「偏った一面だけで人を判断するのは悲しいことですよ、レイ」
曇りのない瞳でまっすぐにレイをみつめる眼差し。レイは自ずと視線を逸らしてしまわずにはいられなかった。
「レイ、貴女はもっと多方向から様々な事象を認識する客観性を持つべきですよ。グリーン・エメラルダの後継者として、その名に恥じない人物になりたいと語ってくれたのは、嘘ではないのでしょう?」
ダイアナのそのことばに、レイはハッとした。そして自分の矮小さに気が付いた。セルリアに嫉妬していた自分に気が付いた。幼い頃の環境から知らず知らずのうちに「貴族」と呼ばれる人たちへのコンプレックスを育んでいたことに、今気付いた。そんな醜い感情を持つ自分が情けなく、悔しかった。
唇を噛みしめ涙ぐむレイに、ダイアナはそっと語りかける。
「セルリアは、恐らく本当に純粋に貴女を慕っているのだと思いますよ。彼女には、遠く離れて暮らす姉がいます。その面影をレイに重ねて見ているのでしょう」
「・・・遠く離れて暮らす、お姉さん?」
涙を袖口で拭いながら、レイは顔を上げた。
「そうです。セルリアの姉、クレアは水晶の守護精霊として人間界にいます。クレアはそれは素晴らしい精霊で、セルリアの自慢の姉でした。そして成人してすぐの昨年、守護精霊の任を受けて人間界へと向かったのです。守護精霊となれば、まずこの精霊界へ戻ることは叶いません。セルリアはまだ幼いというのに、姉と二度と会うことができなくなったのです。彼女は明るく笑っていますが、本当は寂しいはずです」
悩みなど何もないと感じさせるほどに、明るく幸せそうに笑うセルリア。まさか彼女にもそんな悲しみが隠されていたとは思ってもみなかった。自分が義母フルーラを亡くしたのとそんなに変わらない年齢。その寂しさは痛いほどに理解できた。それでも周囲にそれを悟らせないように明るく振る舞う精神力の強さを持ち合わせていたとは。レイは愕然とした。
「クレアは、レイと同じく両眼に紫瞳を持っていました。ですから余計にセルリアは貴女を慕うのでしょうね」
なんといじらしく可愛らしい少女だったのか。今まで自分は彼女の何を見ていたのだろうか――レイの目からは、はらはらと鱗が落ちるようだった。
「ところでレイ。貴女のその紫瞳は、生まれついてのものなのでしょうか?」
どこかで聞いた台詞。そう、聖女王サイラにも同じ問い掛けをされた。
「聖女王様にも同じことを問われたのですけど、紫瞳に何かあるんですか?」
「え・・・い、いいえ、紫瞳は比較的珍しい瞳の色ですから、つい気になってしまって。答えたくなければ別に構わないのですが・・・」
ダイアナの様子に少し違和感を感じながらも、レイはサイラに話したのと同じように、自分の生い立ち、境遇を簡単に語って聞かせた。
「そうでしたか――」
ダイアナも、サイラに同等の答えを返したときと同じように、何やら考え込んでいるように見受けられた。
「どうかしたんですか?」
レイが問い掛けても、ダイアナはひとことふたこと声を洩らしただけで、深く自分の中に渦巻く考えに思いをめぐらせているようだった。
しばしの沈黙の後、ダイアナはしっかりとした眼差しをレイに向けて言った。
「グリーンのように強くなりたいと言っていましたね。だとすれば、貴女には習得しなければならないことがあります」
「習得しなければならないこと・・・? それは何ですか!?」
突然のダイアナのことばに、レイは驚き色めきたった。グリーンのようになるためにマスターしなければならないことがあったとは!? それをダイアナが知っているというのである。
「それは・・・絶対神術です」
絶対神術――聞きなれない術の名に、レイは固唾を飲んだ。
|
 |
各章へジャンプできます |
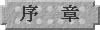 |
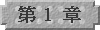 |
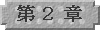 |
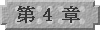 |
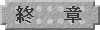 |

