絶対神術――それの名を知ったのは、ほんの数日前のことであった。亡き師グリーン・エメラルダを目指すのであれば、必ずマスターすべき術だとダイアナは言った。
それからのレイは、絶対神術という名が頭から離れず、書物を調べたりもしていたが、どうしてもその実態を知ることができなかった。日数ばかりが過ぎていく。
ある日、レイはダイアナに問いただした。
「ダイアナ様! 絶対神術とはなんですか!? 書物を調べても、それについて書かれているものはありません。グリーンのようになるためには必ずマスターしなければならないと仰っていたでしょう? どうすればそれを会得することができるのですか!」
激しく強く訴えかけるレイと正反対に、ダイアナの表情は静かで重い。
しばらく黙っていたダイアナは、その後にゆっくりと口を開いた。
「絶対神術は秘術です。書物に書き記されてはいません。口伝されるものなのです。そして、今現在の会得者は三人。同時期に最高で四人までしか習得することができないと定められています」
「ということは、今空きがあるということですよね!?」
口伝のみで伝えられているものならば、書物に載っていなくて当然である。同時期に四人までしか会得者を出してはいけないなどと、なんと厳しそうな定めだろうか――それはつまり、その術の特異さ、強大さを表すものだ。
レイは益々絶対神術に強い興味を持った。
「どうすれば口伝を受けられるのですか?」
「・・・」
ダイアナはなかなか二の句を継がない。レイは苛立ちを顕わにした。
「ダイアナ様!!」
「レイ・・・貴女は本当にこの術を会得したいと考えていますか?」
ようやくダイアナが次のことばを洩らし始める。
「はい!!」
「どんな術かもわからないのに?」
「・・・それでも、です!! 私の尊敬する師が会得していた術であれば、それは習うに値するものと信じています」
そう。あのグリーンが禍々しい術を学ぶとは思えなかった。レイはグリーンの人柄をよく理解しているつもりだった。
「何故にそれほどまでに強くなることを望むのですか?」
いつものダイアナと何か違う。これは問答のように感じる。しかし、レイはダイアナの問いに正直に答えることしか考えられなかった。
「ある程度の力を手にすれば、更なる大きな力を手にしたいという欲が出てきます。私も例外ではありません。でも! それだけじゃないんです。私は育ててくれた義母のように、困っている人を見かけたときに、必ず助けることのできるような人物になりたい!」
「貴女は、確かセイジという村の育ちでしたね。その村は、どのような村でしたか?」
レイの育った村、セイジ。それはここ月花城から遥かに離れた辺境の地であった。
「セイジは・・・貧しい村です。男は畑を耕し、女は機を織るのが仕事で、生活には余裕もなく、日々の糧を得るので精一杯の人々ばかりの村です。こどもも小さい頃から仕事を手伝い、文字や計算も知りません。そして辺境の地故に、妖魔に襲われることも度々ありました。人々に本当の安らぎはないように思われました」
毎年、多くの人々が妖魔によって命を落としていた。そんな日常だからこそ、少しでも力のある者は妖魔狩りという仕事を選ぶようになる。
「私は幼い頃、危険だと言われつつも妖魔狩りを生業とする義母にいつもついて回っていました。義母は、困っている人々を放っておけない性分でしたから、生業としていた妖魔狩りも、貧しい人々からは無償で引き受けていました。ですから、生活はちっとも楽なものではなかったのですが、そんな義母を私は今でも大変誇らしく思っています。義母は妖魔に敗れ亡くなりましたが、私も力があれば、義母のように困っている人々のために使いたいと思っているんです」
レイのことばにダイアナは暫し耳を傾けていた。
「妖魔に対し、憎しみの感情を抱いていますか?」
「え・・・」
ダイアナはレイに最後の問いを投げかけた。
レイは答えに戸惑う。今まで誰もそんなことを聞いてきた人物はいない。なぜなら、ほとんどの人が妖魔を憎んでいたからだ。そして、レイは自分の中に渦巻く感情をどう返答すべきか悩んだ。
「・・・わかりません。義母を死に追いやった妖魔は憎いようにも感じます。でも、それだけではなく、何故妖魔は精霊界を襲うのかという疑問もあるし、刹那的な快楽だけを求める妖魔に対して哀れみの感情もあるように感じます。今の私には、はっきりと答えることができません」
レイは正直に今の気持ちを語った。
「・・・わかりました。貴女に私から、絶対神術を口伝する決心がつきました」
「え!! ダイアナ様が!?」
レイは驚いた。絶対神術という恐らくは最強と思われる術を、まさかダイアナが口伝するとは思っていなかったのだ。
「覚えておきなさい。術の会得者は”アメイジ”と呼ばれます。現在アメイジは三人ですが、そのうちのお一方は聖女王様です。もう一方は私の父なのですが、父はすでに隠居に近い生活をしており、表には出ません。四人目のアメイジ選出は、私に一任されているのです」
「そうだったんですか・・・」
今なされてきた問答は即ち、絶対神術の会得者足りうるかを量るための試験だったのだと、レイは納得した。
「絶対神術は自らの寿命を縮める危険な秘術です。ですが、その威力は絶大で、これを上回る術を、私は未だ見たことはありません」
「寿命を縮める・・・?」
なんということだ。なんと恐ろしい術だろうか。自らの命を削り使う術。それならば、秘術となるのも頷ける。
「恐ろしくなりましたか?」
「・・・はい、少し」
「正直ですね、レイは。ですが、それも当然のことです。今ならまだ引き返すこともできますよ」
ダイアナは優しく告げた。レイは未だダイアナに試されているように感じてならなかった。
「大丈夫です。続けてください」
強い意思のこもった声で、そう答えた。
「寿命を縮めるほどの秘術ですから、アメイジもそれに耐えうる強い力と精神力を持ち合わせる者でなければなりません。そして、無闇に使用すべきものでもありません。理性を失い、術を多用すればどうなるかは言うまでもないことです」
ダイアナの講義は続く。
レイはそれを一字一句聞き漏らすまいと懸命に耳を傾けた。
「レイ、おはよう」
「歴史」の講義の時間、いつものようにセルリアはレイに声をかけた。
「・・・おはよう、セルリア」
ダイアナからセルリアのことを聞いてからというもの、レイは少しずつセルリアに打ち解けてきてはいたが、実のところそれまでとっていた自分の態度から、セルリアにどう接していいのかわからずに戸惑っていた。
「最近、よくダイアナ様と一緒のところを見かけるね。いいなぁ」
セルリアはレイの感情の変化を知ってか知らずか、相変わらずの様子である。
「ええ・・・まぁ」
絶対神術は秘術のため、口外無用とダイアナから言われている。レイは、ただことばを濁しただけだった。
ダイアナから口伝を受けている絶対神術は、今は長い詠唱の呪文を教わっていた所で、これが最後のことばになるといっていた。レイはその長い詠唱呪文を忘れないよう、脳に刻み込むためにいつも頭の中で反復して唱えていた。
そのため、講義中以外はほとんど誰とも話すことなく、自分の世界に没頭してしまっている。周囲がほとんど見えていないような状態だった。
従ってその結果、セルリアと話した会話も今日はたったそれだけしかなかった。
「歴史」「宇宙学」の講義を続けて終了させると、レイは早速ダイアナと共に絶対神術の口伝の最終チェックを受けるために教室を後にする。
「レイーッ!!」
すると、廊下の向こうからレイを呼ぶ声がした。
レイが声のした方を見やると、その声の主は同じ「歴史」の講義を受けている、セルリアと年の近い少女だった。
「どうしたの?」
驚きながら、レイは走り寄ってきた少女に声をかける。
普段、年が離れていることもあり、滅多に講義中以外で声をかけられることはない。だから、そんなに親しいという間柄でもない。なのに、廊下の遥か反対側から声をかけてくるというのは尋常ではない。少女はかなり慌てた様子だった。
「セルリアが大変なの!! あなたのかわりに、つれていかれちゃったの!!」
「え!? どういうこと?!」
少女の叫ぶようなことばに、レイは我が耳を疑った。
「セルリア・・・レイをかばって・・・」
少女が泣き出す。
レイをかばって、かわりにセルリアが誰かにどこかに連れて行かれた――
泣き出した少女に事の重大さを察知すると、レイは少女に問うた。
「で、セルリアはどこに連れて行かれたの?」
「・・・たぶん・・・青の庭・・・」
「行きましょう」
ダイアナはレイを促す。
レイとダイアナは、青の庭と呼ばれる庭園へと急いだ。
|
  
|
「セルリア!!」
青の庭と呼ばれる庭園へレイとダイアナが到着すると、そこには数人のあまりみかけない者たちが集まっていた。
レイはセルリアの姿を探す。
「!!」
セルリアは、なんとその見かけぬ者たちの足元に倒れ伏しているではないか。
「どきなさい!!」
レイは、その者たちを蹴散らすように荒々しく中へ割って入り、セルリアの側に駆け寄る。どうやら、負わされたケガはそんなに重症ではなさそうだ。少しほっとした。
「貴女たちは、聖女王様に傾倒しているローズクラブの面々ですね。ここで何をしているのですか」
ダイアナが静かに、しかし厳しく問いかける。
「・・・ローズクラブ?」
レイにとっては、初めて聞く名だった。
「ローズクラブとは、盲目的に聖女王様を崇拝している集団です。実は・・・レイ、貴女に対する良からぬ噂を流していたのも彼女たちなのです」
「え!! そうなんですか?! 何故!?」
大学に通い始めて間もない頃、その噂に居心地の悪い思いをさせられたことを思い出し、レイは何故自分がそんな目にあわなければならないのか、不思議だった。
「お前は聖女王様の懐に入り込み、お心を煩わせ、惑わす存在だ。立場をわきまえもしない。そのような存在は排除すべきなのだ」
ローズクラブの面々のなかでも、中心人物と思われる人物がレイを見据えて口を開いた。
「なら、私だけを狙えばいいことでしょう!! 何故セルリアがこんな目にあわなければならないの!」
そう。レイの代わりにまだ幼いセルリアを攻撃目標にするなんて、卑怯すぎる。レイはどうしても納得できなかった。
「私たちの邪魔をする者は、すべて排除するのだ」
「――あの者たちの目を見てごらんなさい、レイ」
ダイアナが何かに気付いたらしく、レイに声をかける。
「・・・赤い・・・瞳!?」
彼女たちの瞳は、通常精霊界ではありえない、赤色をしていた。そしてそれは、ただひとつの事実を表している。
「嫉妬や妬みで自らを聖魔へと貶めてしまったのですね・・・」
悲しげにダイアナが言う。
聖魔とは、他人に対する負の感情を自分でコントロールできなくなった精霊が妖魔化した状態である。こうなってしまっては、理性や道徳観は失われ、こうしたいという欲望の赴くままにしか行動できなくなる。
「なんてこと・・・この月花城内で聖魔になるなんて。聖女王様を崇拝しているといいながら、その実はただ自分勝手なだけじゃないか!」
レイは自分勝手で周囲のものを傷つけるこの聖魔化した精霊たちが許せなかった。セルリアを傷つけるだけでなく、自分を慕う者たちが聖魔化してしまったなど、聖女王の心も深く傷ついていることだろう。
「レイ。聖魔にはあまり大きな力はありません。ですが、ここであえて絶対神術を使ってみなさい」
ダイアナが言う。つまり、あまり強くない敵で、初めての実戦を経験してみろということだ。
レイはダイアナに従うことにする。
「サポートは私が致しましょう。いいですか、レイ。決して憎しみの感情で術を執行してはいけませんよ」
念を押すようにダイアナは言う。
そうだ。憎しみや怒りにまかせるように術を使うことは、自分自身を暴走させて、場合によっては周囲だけでなく自分の身の破滅をも招く。絶対神術を使用するときは、必ず冷静な心でなければならないのだ。
レイはダイアナから教えられたことばを反復するかのように、思い出しながら段取りを進める。
「お前さえいなければ――!!」
これから長い呪文の詠唱をしようとしたとき、突然ローズクラブの面々が、一斉にレイめがけて襲ってきた。
「ちょっ、ああ、まったくー」
レイは彼女たちの攻撃に身を翻しながら対応する。これでは冷静な精神で――なんて到底無理だ。
レイはその手にUNITEを取り出した。
「レイ、いけません! UNITEでは彼女たちを救うことはできませんよ!!」
「なら、どうしろと!?」
ダイアナに向かってレイは叫ぶ。
するとダイアナは、小さくひと呼吸おいてから突然気を放出した。
「わあぁっ!!」
ローズクラブの面々は、数メートル一気に吹き飛ばされる。
「さぁ、今のうちに詠唱なさい」
「はい」
ダイアナに促され、レイは今度こそ絶対神術の詠唱をはじめた。
ローズクラブの面々をダイアナはレイにまったく寄せつけることなく引き離し続ける。そのため、安心して術に集中することができた。
歌のようにも聞こえるその呪文は、空気を振動させながら周囲を取り巻いていく。実践して初めて、それらの所作の意味するところを理解できたような気がした。
呪文と空気の波は大きな渦となり、そして悪しき心に取りつかれてしまった者たちを飲み込んでいく。残念だが、聖魔となった者は、元の精霊へ戻ることはない。
彼女たちは魂を浄化されたのち、恐らく花の精霊としてでも、再び生まれ変わることだろう。もし、レイがUNITEを振るっていれば、それはすなわち消滅を意味し、魂を救ってやることもできなかった。
ダイアナは、レイの強い精神力にアメイジとしての裁量を垣間見たと思った。
「・・・セル・・・リア・・・」
初めて使用した絶対神術に、体がついていけなかったのだろう。レイはセルリアの身を案じながらも、その場に昏倒した。
|
  
|
「セルリア・・・」
ルリハコベの青い花が咲き乱れる青の庭。美しいこの庭で、悲しい出来事が起きたのは一週間ほど前のことであった。
その後、手厚い看護を受けたセルリアは数日で回復し、昏倒したレイも丸三日眠り続けはしたものの、今では元気そのものである。
レイはセルリアがこの場所にいると聞いてやって来たのだ。セルリアには言いたいこと、言わねばならぬことがたくさんある。
「あら、レイ」
声を掛けられレイに気付くと、いつもと変わらぬ明るい声でセルリアは返事をした。
レイは照れくさそうにセルリアの隣に腰掛ける。
「どうしたの? レイからあたしの所に来るなんて、珍しいわね」
「あ・・・そうね」
なんとなく話しづらい。レイは生返事を返した。
「ん?」
セルリアが不思議そうにレイの方を見る。
レイは覚悟を決めた。新たな一歩を踏み出すために。
「セルリア。ごめんっ!!」
「え?」
「この間は私のせいでひどい目に遭わせてしまった・・・」
そう。レイを狙う輩にひとり立ち向かったセルリアは、結果としてそのためにひどいケガを負うことになってしまった。レイはそれに対し、負い目を感じていたのだ。
「あたしが自分で勝手にしたことだから。別にレイが謝ることなんてないわ。あたしが無鉄砲だっただけ。気にしないで」
にっこりとセルリアは笑う。
「他にも、謝りたいことがあるの。私、セルリアに嫉妬して、冷たくあたってしまったりしたわ」
「・・・そうだったっけ? あたし、全然気になんなかったけどなぁ・・・。だってレイは大学に来て間もなくて、知り合いも全然いなかったでしょ? だから色々と慎重になるのも当然だと思ってたし・・・そんなもんだと思ってた」
相変わらずセルリアは笑っている。とてもレイよりずっと年下とは思えなかった。自分の未熟さを痛感し、レイはセルリアの器の大きさを感じた。
そして、あの一件以来、なんだかセルリアが随分と大人になったように思えた。
「・・・今更と思うかもしれないけど・・・私と友だちになってくれる?」
ずっと告げたいと思っていたが口に出せなかったことば・・・。それをようやくレイは口にすることができた。セルリアのことを知り、彼女に嫉妬していた自分に気付いてから、レイはずっとセルリアと友だちになりたいと思っていたのだ。
「あら? あたしたち、もうずっと前からお友だちでしょ? 違った?」
満面の笑みでセルリアが答える。
敵わない――その時レイは思った。セルリアには敵わない。
そして、レイは声を出して笑った。
「ははは、そっか。私達はずっと前からもう友だちだったのね。あはは」
「そうだよー、えへへへ」
セルリアも共に声を上げて笑う。
ルリハコベの咲き誇る庭で、ふたりは大きな声で笑った。
|
 |
各章へジャンプできます |
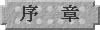 |
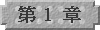 |
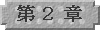 |
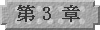 |
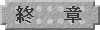 |

