「黒木さんと晶子が知り合いか・・・」
安珠は部屋のベッドに横たわりながら、今日起きた出来事を振り返っていた。
「いつ知り合ったんだろう。お世辞にも、仲は良さそうじゃなかったし」
うーん、と考えてみても、答えが出てくるわけではない。
「ああっ。もう、なんでこんなに晶子のことばっかり考えなくちゃなんないんだ。あのお伽話といい、この頃は晶子に振り回されっぱなしだよ。やめた、やめた。もう考えない。さっさと寝よ」
安珠は部屋のあかりを消すと、布団にもぐり込んだ。
〜目覚めよ、アンジェラ〜
「誰だ。誰のことを呼んでるんだ」
〜目覚めよ、戦士アンジェラ〜
「誰が呼んでるんだ。出てこい」
周りを取り巻くのはまた漆黒の闇のみ。安珠と謎の声だけが、その空間にこだましていく。
〜目覚めよ、アンジェラ・シェン〜
「オレはアンジェラなんとかなんかじゃないぞ!」
すると、途端に周りは鏡に変化した。何百何千という自分の姿が映る。しかし、その姿はまたしても二歳に満たない少年の姿に移り変わっていった。
「うわぁっ!」
安珠は飛び起きた。
「またあの夢だ・・・。いったい何だっていうんだ」
身体中、汗でべっとりとしている。着替えが必要かもしれないほどに。
額の汗を手で拭って、安珠は時計を見た。
「まだ一時半じゃないか。起きるには早すぎる時間だな」
ふうっと、再びベッドに横たわる。しかし、なかなか寝付かれない。
窓の外はまだ厚い夜のヴェールに包まれていて、外灯の光だけがこうこうと窓の外を照らしている。
「安珠・・・」
小さな声が安珠の耳に入ってきた。
「え、誰?」
「安珠、こっちへ・・・」
今度は先ほどよりも、もっとはっきりと聞こえてきた。
「この声は・・・晶子なのか。何処だ」
「ここよ、安珠・・・」
ベッドから起き上がって安珠は周りを見回した。すると、壁に掛かった大きな鏡がぼんやりと光っている。恐る恐る近づいていくと、突然強烈な紫の閃光が鏡から部屋中に飛び出した。
「うわぁっ」
安珠は思わず両手で顔を覆い、うずくまった。
しばらくして、ゆっくりと顔をあげると部屋の中はまた、暗闇に戻っていた。しかし、ただひとつ、壁に掛かった大きな鏡はうすぼんやりと光を纏っていた。先ほどとは明らかに違う、紫の光を。
安珠はそうっと鏡の前へ立った。
「あ。こ、これは・・・」
目の前にあるべきはずの自分が映っていない。そのかわりに、夢にいつも出てくるあの小さな少年が、無表情に立っていた。
それが次の瞬間、まるでCGのように晶子へと変化した。
「しょ、晶子!」
安珠が鏡に手を伸ばした途端、鏡に吸い込まれるようにして、部屋からその姿を消した。
部屋の中には、ぼんやりとした鏡の光だけが取り残されていた。
|
  
|
安珠が気付くと、それは夢で見たあの世界のように、ただ漆黒の闇だけが周りを取り巻く場所だった。
「ここは・・・。これは夢なのか・・・?」
〜目覚めよ、戦士アンジェラ〜
夢の中のあの声が聞こえてくる。
「いったいここは・・・。それにあんたは誰なんだ」
夢ではない・・・そんな確信だけは、安珠の中ではっきりとしていた。今の安珠には恐怖心よりも、意味がわからないことへの憤りのほうが勝っていた。
そう。臆病風に吹かれるほど安珠は弱くはなかったし、はっきりしたことはまだ何もわからないのだから。
「安珠・・・」
晶子の声が聞こえる。
はっとして振り返ると、安珠の背後に確かに晶子のような人影がある。
「晶子なのか・・・」
安珠は声を発した人影のほうへと歩み寄った。
「安珠・・・」
「しょう、こ?」
安珠がはっきりとした姿がわかるように人影に近づくと、そこにたっていたのは姿こそ晶子にそっくりな、しかし、人間とは到底考えにくい紫瞳(シトウ)を両眼に持つ女性だった。
「晶子にそっくりだ。貴女は誰」
「私は晶子」
その女性は自分を晶子だという。確かに声までもが酷似している。いや、晶子そのものだといっても過言ではないだろう。
「でも、私は紫鏡。周りをよくご覧なさい」
今度は紫鏡と名乗った女性がそういうと、急に周りは大昔の村らしい様子に変わった。それはさらに、どこか異国の風を吹かせている。
「これは・・・。ここはいったいどこなんだ」
「ここは、今から二千年前の中国。さらにいうのなら、前人未踏とさえもいわれる山奥の、いわゆる秘境」
紫鏡と名乗る女性は静かに答えた。
「ちゅ、中国!」
「そう。そしてここはあの紫鏡の伝説の地。ここで、その当時起きたことをよくご覧なさい」
そういうと、紫鏡はすっと姿を消してしまった。
|
  
|
村は、大昔の山奥にあるだけあって、農耕と狩猟で生活している村のようだった。村人たちは、皆穏やかな表情だ。恐らく争いやいざこざとは縁遠い人間たちなのだろう。それほどに、この村は平安を約束されているように見受けられた。男も女も額に汗して働き、こどもたちは元気に野山を駆け巡っている。のどかを絵に描いたような風景。
安珠はその村にえもいわれぬ懐かしさを感じていた。既視感というよりも、もっとしっかりとした懐かしさ。確かにここに存在していたような。
「紫鏡様だ」
村人のひとりが指を差して叫んだ。
はっと安珠は現実に引き戻されるように、その姿を見た。
村人の指し示す方向、少し高くなった丘の上に、確かに紫鏡という先刻の女性が立っていた。
「我が愛しき民よ、よくお聞きなさい。今すぐにこの村より立ち去りなさい。西方より、邪悪の力が迫り来ている。一刻の猶予もないの。さぁ、早く。私の弱ったこの身体では、我が民を守ることさえもままならないのです。さぁ、一刻も早くここから逃げて」
紫鏡は激しく訴えた。
村人たちは今までにない自分たちの守り神の様子に、事の重大さを感じ取ったのか、火の燃え広がる如く、大混乱となってしまった。
「さぁ、早く逃げるのです。ひとりでも多く、逃げて生き延びて」
紫鏡は叫んだ。
その時、村人たちの頭上に、突如巨大な石が轟音とともに降り注いだ。
「危ない!」
安珠は思わず叫んだ。しかし、声が届くはずもない。
いち早く気付いた紫鏡は、自らの霊力でそれらの幾つかを止めることはできたが、しかし、ほとんどは村人たちを押し潰した。
村人の断末魔の悲鳴が村中に響き渡る。
「ハーッハッハッハ」
どこからか、恐ろしい笑い声が響いてきた。
突如、村人の何人かの背中から炎が燃え上がった。人々は生きたまま焼かれ、気の狂うほどの苦しさに、地を転がり回っている。
「やめろ、やめてくれぇっ!」
まるで人の焼ける匂いさえもしてきそうなほどの臨場感。安珠はとても正視できるようなものでないその光景を前にして、もはや泣き出してしまいそうだった。
「ハハハハハ。我が名はジゴルゼーヌ。我にひれ伏し、我を崇めよ。そしてその苦しみの声を我に捧げるがいい」
その声とともに、ジゴルゼーヌと名乗る男が、紫鏡のいる丘の反対側にある崖の上に姿を現した。冷酷そうなその顔は、氷のような美しさだった。透 き通るような白い肌。ルビーに似た赤い瞳。この世のものとは思えない恐怖をつのらせる美。この男を見ただけで、あるいは死に至ることもあるかもしれない。 そして男の側には、ひとりの女が寄り添うようにして立っていた。
「黒梨(ヘイリー)!」
女を見て、紫鏡はそう言った。
「いい様ね、紫鏡様。この村は、残念だけどジゴルゼーヌ様のものになるのよ。ごめんなさいね」
黒梨という女は、為すすべもなくただ立ち尽くす紫鏡の姿を見てほくそえんだ。
「お前が妖魔を手引きしたのね。この村を、村の民を裏切ったというのね」
紫鏡は怒りに打ち震えていた。
村人たちの悲鳴は、いまだ絶えることなく続いている。
「ちきょうちゃま・・・」
紫鏡の側に小さな、まだ二歳に満たない少年が隠れるように立っていた。安珠の夢の中に何度も出てきたあのこどもだった。
「ジゴルゼーヌとか言ったわね。私はお前を許さない」
「ほう。我が力に貴様が敵わないことは必至。”許さない”とは、いったいどのようにするというのか」
「驚くわ」
そう言うと、紫鏡は何やら呪文を唱え出した。
すると紫鏡の身体から紫のオーラがほとばしり、空を紫に染めた。いつの間にか、額には大粒の紫水晶が浮き出ていた。
「それは、もしや」
ジゴルゼーヌは明らかにたじろいだ。
「(悠久の時を超え 神に召還を請う 今こそ悪しき者 ここに封印したもう)」
紫鏡は呪文を唱えあげた。
「それは、絶対神術・・・。や、や、やめるんだ。やめろーっ!」
紫鏡の額の水晶から紫の閃光が放たれ、そして口を開けた異空間へ叫ぶジゴルゼーヌは飲み込まれていった。
「あ、ジゴルゼーヌ様!」
黒梨は身動きもできず、ただジゴルゼーヌが封印されていくのを見ているだけだった。
「黒梨」
紫鏡が声を掛けた。
「貴女は大変な罪を犯したのよ。この罪は償っていってもらうわ。貴女には、生きてちゃんと寿命を全うしてもらわなくてはならないわ。自殺することは許されない。いえ、できないのよ。よく覚えておきなさい」
「できないですって! なに勝手なこと言ってるのよ。冗談じゃない。ジゴルゼーヌ様のいない世界で生きてなんていけないわ」
黒梨は咄嗟に懐から小さな剣を取り出し、喉元へ突き立てた。
しかし、確かに刺さったと思った剣はぐにゃりと、まるで柔らかいこんにゃくにでも変化したかの如く頭を垂れてしまった。
「! なんで・・・」
愕然と腰を落とした黒梨にむかって紫鏡は落ち着いた表情で語った。
「貴女は神の光を浴びたのよ。先ほど、ジゴルゼーヌに絶対神術を唱えた時にね。神の光を浴びた者は、自ら死を選択することはできないの。さらに、貴女は偉大なるシェン一族の人間。私の愛した村の民。もとより精霊の加護を受けているのだから、神の光を浴びずとも自殺などできるわけはなかったでしょうけれど。貴女はジゴルゼーヌに利用されていただけなのよ。早く目を覚まして悔い改めなさい」
「うるさい、うるさい、うるさい!」
黒梨は叫んだ。
何を言ってもだめなのか、と紫鏡は大きなため息をついた。そして、足元に身を隠しているアンジェラという小さな少年に視線を合わせるように腰を下ろした。
「さぁ、アンジェラ、私たちも眠りましょう。せめてもの救いは貴方が生きていてくれることです」
そう言うと、少年の額に紫鏡はそっと手をおいた。
アンジェラという少年は、それきり動かなくなった。
「神よ、今時は動けり。その力を以って今ここに、我らを二千年の眠りにつかせたもう。我らに封印を」
紫鏡が言い終わるか、終わらないうちに、激しい紫の閃光が空へ向かって飛び散った。
「・・・オレは、アンジェラ・シェン・・・」
安珠はぽつりと呟いた。
|
  
|
安珠―正しくはその名をアンジェラという―は、自らの力で鏡の世界より元の世界へと戻ってきた。
「おかえりなさい。アンジェラ」
そこには紫鏡が待っていた。
「紫鏡様。只今戻りました」
封印の呪文は、同時に封印を解く呪文でもあったらしい。
「まさか、僕が紫鏡様の弟として生活していたとは思いもよりませんでした」
「私が望んだことなの。アンジェラ、貴方には是非私と共にジゴルゼーヌを倒してもらいたいのです。もちろん、これは命令ではないけれど」
紫鏡は優しさの中に厳しさを兼ね備えた顔つきで、そして穏やかな口調で言った。
「貴方のその瞳。右の紫瞳と左の緑瞳(リョクトウ)。それは精霊界とのつながりを示すもの」
「精霊界とのつながり?」
アンジェラは、いまいち紫鏡の話を飲み込めないようである。
「そう。紫瞳は精霊のみが持つ特別な瞳。鏡で自分の顔をよくご覧なさい」
アンジェラはぱっと背後の大鏡に振り返った。
確かに、自分の瞳が紫と緑を片方ずつに持つのを認める。つい先ほどまでは、間違いなく普通のブラウン・アイズだったはずなのに、と我が目を疑いもしたが、何度見直しても確かに紫瞳と緑瞳に変わっていた。
「貴方はその瞳を持つ為に、人より長い寿命と、類稀なる超能力を身に付けているの」
「ええ! 超能力?」
紫鏡の突然の発言に、アンジェラは思わず大きな声を発した。
信じられない、だけど紫鏡の様子はからかっているふうでもない・・・と今この身に潜んだ秘密に驚きと恐怖を感じた。
紫鏡は静かに頷いた。
「貴方は、村の中でも特別な存在だったの。貴方の父上は村長(ムラオサ)の息子でした。しかし、他の地に住む女性と恋に堕ち、村から姿を消してしまったのです。その後、村長は永く病に伏しておられて、もはや今日明日の命という時に、貴方の父上が赤児の貴方を抱いて再び村に現れたのです。貴方は、私の愛した村の村長の跡を継ぐ人間だったのよ」
「紫鏡様」
アンジェラは紫鏡の昔語りを遮るように声を掛けた。
「僕の、僕のお母さんはどんな人なんですか?」
少しせつなげな、そして不安のこもった表情である。
「知らないわ。私の言えることは、貴方の母上が精霊であっただろうことと、貴方を生んですぐに亡くなったということだけなの」
「そうですか・・・」
アンジェラは、低くそう呟くとそれきり黙り込んでしまった。
「昔語りはもう止しましょう。アンジェラ、先ほどの話だけど、貴方には是非とも私の力になってもらいたいの。お願いできるかしら」
紫鏡はアンジェラの心をいたわるように優しく言った。
アンジェラは、すっと顔を上げた。確かな決意の表情。
「喜んでその大役引き受けさせていただきます。もう二度と、僕らの村みたいなあんな惨劇は見たくない」
きっぱりと言い放ったその瞳は、ひとつ大人になっていた。
「ありがとう。あと一週間ほどで敵との戦いになると思います。それまでは、必要な時以外、今まで通り貴方は”紫水 安珠”です。私のことも、また晶子と呼んでちょうだい」
「はい。あ、そうか。黒木さんが黒梨だったんだ。なんとなく、変な気配は感じていたんだけど、今わかった」
「そうよ。しかし、人前で騒ぎを起こすようなことだけはしないでちょうだい」
「わかってる・・・あ、います!」
「あまり気にしないでいいわ。今までのように普通にお話しなさい。無理は辛いだけでしょう」
「そ、そうだよね。すいません」
ふたりはふっとほほえんだ。張り詰めていた糸が緩むようだった。 |
 |
各章へジャンプできます |
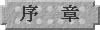 |
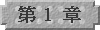 |
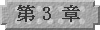 |
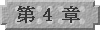 |
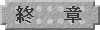 |

