「そうか、紫鏡をみつけたか」
暗い部屋。赤く炎を燃やす蝋燭の明かりに照らされて、ジゴルゼーヌは寝台に横たわり楽しそうに言った。左の手には銀の杯を弄んでいる。
「はい、ジゴルゼーヌ様」
その膝元に低く身を置きながら、うっとりとジゴルゼーヌを見つめて黒梨は答えた。
「ようやくだな。ところで、何か気に掛かることでもあるか」
ジゴルゼーヌは心を見透かすように、黒梨にほほえみかけた。その顔はぞっとするほど冷たく、そして美しかった。
「実は、紫鏡の双子の弟という者がおりまして・・・」
慎重に、ジゴルゼーヌの怒りをかわないよう、ゆっくりと話し始める黒梨。
「それがどうした」
「はい。人間らしくない気を放っているのです」
「ほう」
ジゴルゼーヌの左の眉がぴくりと動いた。
「まだ微かにしか感じ取れないのですが、どうも私と同族の気もします」
「何と。・・・しかし、例えもしそうだったとして、お前の村の民に何ができる。たかだか人間、紫鏡の力で生き延びた者がいたとしても、案ずることはなないだろう」
「・・・はい」
そう答えたものの、黒梨の不安は隠せない。
「黒梨」
ジゴルゼーヌは寝台の天蓋が見える形に仰向けになった。
「はい、ジゴルゼーヌ様」
そう答えると着衣を脱ぎ去り黒梨はおずおずと寝台の上にあがる。ジゴルゼーヌに何を言われたとしても、彼女は精一杯その要望に応えようとする。妖魔の・・・しかも魔性といわれる妖魔の貴族にしてみれば、これほど使いやすい道具はない。
黒梨は求められるがままに、ジゴルゼーヌの性欲の象徴に腰を沈めた。
「我は紫鏡に長い間封印され、さらに敗者の如き烙印まで押されてしまった。この怒りは一生消えることはない。必ずや紫鏡を倒すのだ」
ジゴルゼーヌは額にくっきりと浮かびあがる赤い炎の形をしたアザに手を触れながら、自分の上で身体を揺らす黒梨に吐き捨てるように言った。
「あ・・・はっ、はい・・・」
「そうだな。お前がそんなに心配するのなら、その紫鏡の弟という奴を調べてみるがいい。それでお前の気も晴れよう」
「はい、ジゴルゼーヌ様・・・ああ」
ジゴルゼーヌは目を閉じた。
赤い蝋燭にぼんやりと照らし出された黒梨のシルエットだけが壁を動き回り、部屋には動物からとる香料のような香が充満していて、荒い吐息と声と、そして寝台の軋む音だけが響いていた。
|
  
|
「おはよう、安珠くんっ」
「あ、おはよう香ちゃん」
ゲタ箱で靴を履き替えていた時、安珠の横にぴょんと軽く飛び跳ねるようにして香りは現れた。
安珠がアンジェラとして覚醒してからすでに三日が経過していた。
「ねぇねぇ、知ってる? 一昨日やった学力テストのね、上位者の結果発表してるのよ、今日」
「本当。だけどどうしてこの学校はなんでも成績発表するんだろうね。今時そんな学校他にもあるのかなぁ」
腕組みの姿勢をとって安珠は言った。
「ほんとね。あ、そんなことより安珠くんったらどうしちゃったの?!」
「ええっ! どうしちゃったのって、いったい何が?」
香の突然の発言に、安珠はもしや自分がただの人間ではないとバレてしまったのでは、と不安になって、異様に大袈裟な驚きかたをしてしまった。頭に熱いものが昇るのを感じた。
「学力テストの結果よぅ。一番なのよ。安珠くん、学年で一番!」
「ええっ、それ本当?!」
思いもよらない香のことばに安珠は己が耳を疑った。しかし、心の奥底では自分の正体がバレた訳ではなかったことに胸を撫で下ろした。
「安珠くんったら、二問しか間違えてないんだよ。あたし、びっくりしちゃった」
香は、けれどうれしそうな様子である。
「ふうん。それじゃあ大変ね」
いつの間に現れたのか、安珠の背後には晶子が立っていた。
「何が大変なんだよ。成績が良くなったってことは、良いことじゃんか」
手は腰に、首は右へ傾けてツンとすました安珠は得意気に言った。
「あのね、あんたみたいに今までたいした成績じゃなかった人間が、突然学年一位なんて結果を出して、”はい、よくできました”と認めてくれる人が何人いると思ってるの?
はっきり言って、カンニングでもしたんじゃないかと思う人間のほうが絶対に多いと思うけど」
こいつはバカか、とでも言いたげな晶子の目つきである。
「カンニング?! 僕はそんなことしてないよ!」
「それでも、疑われるのは間違いのない事実だわ」
晶子はきっぱりと言い放った。
ふぅっと安珠は小さなため息をひとつ、ついた。
その時。
「おーい、安珠。担任が呼んでるぞ」
クラスメイトから、丁寧にも伝言が届いた
「失礼します」
礼儀正しく一礼をして、安珠は職員室に入っていった。
「お呼びですか?」
「ああ、紫水。実は、な・・・」
担任の小林は明らかに言い出しにくそうな様子である。
「学力テストのことですね、先生」
「あ、ああ、まあな」
「僕がカンニングをしたんじゃないかって言いたいんでしょう、先生は」
落ち着き払った安珠の言動に、逆に小林のほうが焦ってしまっている。
「いや、そんなことは・・・」
「いいんですよ、わかってますから」
先ほど晶子に言われて初めて気付いたなんて、おくびにも出さずに安珠は毅然とした態度でことばを続けた。
「でも、僕はカンニングなんてしていませんからね」
「ほう、よくそんなこと言うなぁ」
その時、小林の隣の席に座る生徒指導の船橋(フナバシ)が口をはさんだ。
「お前みたいな普段たいした成績じゃない奴が、いくら勉強しようとも学力テストであんな点数、取れる訳ないだろうが。そうだろ」
船橋は嫌味を言わせれば天下一品の男で、当然ながら生徒からの人気は学校最低の教師である。安珠の体育の先生でもあり、以前柔道の時間に安珠に”みなとや落とし”という名の、まだできたばかりの新技を決められて負けたことがあり、それから安珠を目の敵にしている。
ちなみに、”みなとや落とし”という技は体格が大きい相手に対して有効な技らしい。
「船橋先生、そこまで言わなくても・・・」
「小林先生は黙っててくださいっ!」
助け船を出そうとした小林は、船橋に一喝されて黙り込んでしまった。どっちが担任なんだとか、そういうことは一切関係ないというほどに船橋の鼻息は荒い。
「おい、紫水。お前カンニングしただろう。えっ、そうだろう」
「僕はカンニングなんかしてませんよ」
「ウソをつくなっ!!」
船橋は、最初から安珠は不正したものと決めつけている。
「先生がそう思い込みたい気持ちはわからなくもないですけど、やってもいないことをやったと言われるのは甚だ不快です。そんなに言うなら、白黒はっきりさせましょうよ」
「ほほう、どうやって」
無理に決まっている・・・と船橋はほくそ笑みながら言った。
「放課後、もう一回テストしましょう。中身はもちろんすべてお任せしますよ。筆記用具とか、みんな用意してもらっても構いませんよ」
安珠は自信満々という具合でニッコリと笑ってみせた。
「よ、よーし、俺が見ててやる。そこでお前の不正を暴いてやるぜ。俺はカンニングなんてもんは見逃さんぞ。いいな、放課後だ。逃げるんじゃないぞ」
船橋の鼻息は更に荒ぶった。
しかし、テストの結果は船橋の大敗だった。安珠は船橋の見ている前で難問をスラスラと解き、見事満点。
安珠の身の潔白は証明され、船橋はあまりの悔しさに翌日は学校を休んでしまった。まわりの人間は、誰しもがその大人げのない有り様に辟易してしまった。
|
  
|
「ジゴルゼーヌ様、只今戻りました」
暗い部屋。いつものようにジゴルゼーヌは薄布を身体に纏い、寝台に横になっている。
「うむ」
今まで眠っていたのか、物憂げな表情でジゴルゼーヌは頷いた。
「・・・おぐしが」
黒梨は胸元から櫛を取り出すと、流れるように美しいジゴルゼーヌの長髪を梳きはじめた。髪に触れているだけでも、黒梨の身体に快感がはしる。
その時、ジゴルゼーヌが口を開いた。
「安珠と言ったか、紫鏡の弟という者は・・・」
「はい」
「何かわかったか」
「三日ほど前から、放散させている気が急に上昇しております。学業成績も同じく。あの変貌はやはり我が村の民と思われます。しかし、それ以上の詳しいことは・・・」
「・・・そうか。ご苦労」
ジゴルゼーヌはスッと手を伸ばした。
その手に黒梨はそっと接吻する。それが労苦の後に与えられる黒梨への褒美なのだ。ジゴルゼーヌの肌から立ちのぼるように香るムスクが鼻腔に広がる。脳まで痺れるような感覚に襲われて、黒梨は目眩するほどの幸せを感じた。
ジゴルゼーヌは魔性と呼ばれる妖魔の貴族である。本来、魔性というものは自らの美と強さと頭脳を誇り、自分の為だけに行動する。黒梨に時折かける優しい 仕種やことばも、黒梨の為を思っているのではない。ただ、便利な道具を無理に手放す必要がないから、故意に優しさを装っているだけなのだ。
そのことを理解していても、それでも黒梨にとってジゴルゼーヌはかけがえのない存在であった。側にいられるだけで、幸せを感じていられた。愛して止まない男だった。
|
  
|
同じ頃、安珠は紫鏡とともにアンジェラの持つ力をうまく使いこなせるように特訓をしていた。
「気を集中させなさい! 雑念を追い払えと何度言えばわかるの! そんなことじゃジゴルゼーヌはおろか、黒梨にさえも太刀打ちできないわよ!!」
時間がない・・・そんな焦りが、呑み込みの悪い安珠にぶつけられていた。
「なぁ、紫鏡」
それでも、安珠はまったく気にせずに、いつの間にか紫鏡のことも呼び捨てるようになっていた。
「どうして”安珠”のまんまでこんな訓練をしなきゃなんないんだよ。”アンジェラ”になっちゃえばこんなことしなくたって、十分力を使えるのに」
安珠の言う”アンジェラ”とは、紫瞳緑瞳に両眼を変化させたときのことらしい。
「どっちだって貴方だということには変わりないでしょう。それに、人前でそんな珍しい瞳など見せて歩ける? それなら、いつだって貴方の言う”安珠”のままで、力を自由に操れるようになるほうが良策だと思うのだけれど。違う?」
紫鏡も安珠のようすに、焦って気を揉むのが何だか馬鹿らしく感じられるようだ。その口調からは、すっかり毒気が抜けていた。
「わかったよ。今度こそ真面目にやります。えっと・・・気を集中させて、雑念を払って、体の力を抜いて・・・」
安珠はブツブツと、紫鏡の教えをひとつずつ思い出しながらも、精神集中を始めた。
すると、だんだんと安珠の気が高まり、オーラとして周囲を取り巻きはじめた。
「指先に気を集中させて・・・」
スッと伸ばした人差し指が光りだす。
「・・・そして、一気に放出!」
ビシューンッというすごい音とともに、光は一気に放たれた。
「あ。やった! やったぞ!! できたぁ」
安珠はうれしそうに飛び上がった。それはまるで兎のように、そこいらじゅうを、である。
「さぁ、今の呼吸を忘れないように。もう一度やって
その日一晩で、安珠は不思議な能力をマスターしてしまった。
「アンジェラ、よくやったわ。ご褒美として貴方に”精霊の剣(セイレイノツルギ)”を授けるわ」
そういうと、紫鏡は刃渡り一メートルほどもある、柄に見事な細工が施された剣をどこからともなく取り出した。
「すっごーい。これをオレに? でも・・・、こんな目立つモン持って道なんか歩けないよ。そんな時に悪いヤツに襲われたらどうするんだよ」
安珠がそういうと、紫鏡はフッと笑みを見せて安珠に剣を手渡した。
「お手本を見せてあげる。よく見てて」
紫鏡は後方に軽くひとつ、飛んだ。
といっても、常人とはまったく違う。五メートル以上も後方に飛び去ったのだが。
「Unite(ユナイト)・・・精霊の剣よ、我が元へ」
紫鏡がそういうと、今まで安珠の手の中にあったはずの剣が一瞬のうちに、紫鏡の手の中へと納まっていた。
「・・・今、一瞬何が起こったのかわかんなかった。もしかして、剣が瞬間移動したってこと?」
安珠は驚嘆と感嘆の声を洩らしながら尋ねた。
「そうよ」
「オレにもできるようになるの!?」
安珠は、その不思議な剣、精霊の剣にすっかり魅了されてしまった。
「今はまだ無理よ。この剣は、私のいうことしかきかないわ」
「何故?!」
明らかに安珠は不服そうだ。・・・なら、何故そんなものを授けるなんていうんだ、とでも言い出しそうである。
「この剣は、昔、まだ私が精霊聖五位という位を頂いて、今の紫水晶の精霊となる前に、ある人から頂いたものなの。その人に、私は剣の継承の儀式をしてもらった。だから今、この剣は私の言うことしかきかないのよ」
紫鏡は、剣をいとおしむかのように見つめていた。それはまるで、剣の向こうに遥か昔の思い出が見えているかのようだった。そして、その瞳には悲しみの色も混じっているように、安珠には見えた。
「じゃぁ、どうしたらオレのいうこともきくようになるの」
昔語る紫鏡の心をいたわるように優しい声で、それでも口を少し尖らせて拗ねたように安珠は尋ねた。
「これから、私が継承の儀式を執り行うわ」
「継承の儀式って・・・どうするの」
耳慣れない、とても神秘的なそのことばに、安珠は少しの不安と恐怖と、そして好奇心をもった。
「手を出して。中指を少し切るから痛いケド、我慢するのよ」
そういって、紫鏡は呪文らしきものを唱え始めた。しかし、人間の耳には聞き取れない音域までを使う呪文で、安珠にもよく聞き取れない。
紫鏡は精霊の剣を天にかざし、それから安珠の左手を取ると、剣で安珠の中指を傷つけた。澄んだ赤い血がぷっくりと溢れ出した。
「つっ・・・」
痛みに瞬時、安珠は顔を歪めた。しかし、それをぐっとこらえる。
紫鏡は血の滴る安珠の中指を、柄にはめ込まれた上質のエメラルドに円を描くようになすり付けた。すると、剣がまるでその血を飲んでいるかのように、エメラルドの中に染み込んでいった。エメラルドは妖しく光り出し、そしてその光は急に天へと飛んだ。
「な、何だぁっっ!! どうしたんだ、コレ」
いきなりの出来事に、安珠は尻もちをつきそうなほどに驚いた。
「天に承認していただいたのよ。これで儀式は終了よ。これでこの剣は貴方のものよ」
力を大分使ったのか、少し疲れたように微笑みながら紫鏡は言った。
「覚えておいて。この剣にはUnite(ユナイト)という名前がついているの。さぁ、剣を呼んで、貴方の元へ」
「よぉし。剣よ・・・我が元へ!」
カッコをつけて、安珠は紫鏡のまねをしてみた。
しかし、剣は安珠の手の中からぴくりとも動かない。
「動かない。動かないよぉ、紫鏡」
ふくれっ面をして安珠は言う。
「ただ呼ぶだけではダメ。自分の剣なのよ。もっとUniteのことを心に思い描いて。イメージするのよ。さぁ、もう一度」
「あ、うん。・・・Unite、オレの剣よ。来い!」
安珠が叫んだ途端、ヒュンッと音をたてるかのように剣は安珠の手の中に現れた。
「わぁっ。できた!」
「それでいいわ。その剣は、自分の持っている力を増幅させて、発散させてくれるの。アンジェラなら、きっと上手に使いこなせるわ」
紫鏡も安心したようである。うれしそうに微笑んで安珠を見つめた。安珠も嬉々としている。
「これで、きっとジゴルゼーヌを倒してやる」
「ふふ。その意気よ」
二人の結束はがっちりと固まっていた。元より、十数年も家族として共に生活をしてきたのである。この二人の絆を引きちぎるものは、恐らく何一つとして無いのだろうと感じられた・・
|
 |
各章へジャンプできます |
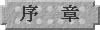 |
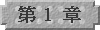 |
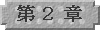 |
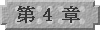 |
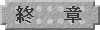 |

