「今日からお世話になります。紫水 安珠です、ヨロシク!」
「紫水 晶子です。宜しくお願いいたします」
安珠と晶子は、正式に聖学園に転入することが決定した。
「委員長は田端 薫さん。わからないことがあれば、田端さんに聞いて」
先生は言った。先生方の計らいで、安珠と晶子は同じクラスになった。
そして、座席も薫をはさんで両脇に位置している。エスカレーター式の学校で、知り合いがいないのは可哀相だろうという配慮だ。希に見る編入試験の結果に、ふたりの待遇は特別扱いと言ってもいいのだろう。
「薫ちゃん、また会ったね。ヨロシク」
「こちらこそ。ん・・・でも、あの試験でよくあんな点数とれたよね。すごく頭いいんだね」
少しオーバーに驚いてみせながら、薫は言った。
「バカに見えるけど、これで結構頭いいのよ、安珠は」
晶子はにやっと笑みを浮かべながら言った。
それはひどいよ、と安珠は晶子を睨みながら笑った。
「仲いいのね。あんまり似てないみたいだけど、双子、よね?」
「そうだよ。顔のイイ所と頭のイイ所がもう、そっくりでしょ?」
安珠はウインクをして言った。薫も楽しそうにくすくす笑っている。
何となく、顔のみならず雰囲気さえもが、薫と香はうりふたつだ。安珠にはそう思えてならなかった。
|
  
|
放課後になると、安珠と晶子は薫に連れられて、校内をいろいろと案内してもらうことになった。
「さっすが、元女子校。やっぱりキレイな学校だよなぁ。設備もしっかり整ってるし」
安珠は感心しながら周りを見回す。
「そうね、共学校の、しかも公立の学校なんて古い学校が多いしね」
晶子も同意して頷く。
確かに、ここ聖学園は綺麗な学校だった。専門の清掃業者を雇用し、美化にも力を入れているし、中庭もヨーロピアンスタイルで緑と光の降り注ぐ明るい庭に なっている。食堂はもちろんビュッフェスタイルで、味は良し、値段も手頃でバリエーションも豊富だ。レクリエーション室やその他様々な特別室も設けてある。これほどに充実した設備を持つ学校も、少ないように思われた。
「あれ。なんだろう、あの音楽・・・」
安珠はふと足を止めた。晶子と薫もそれにつられて足を止めて耳を澄ます。
「ああ、あれは日舞部よ。日舞部の練習用のCDが流れてるんだわ。今日は生徒会長の聖 永遠子さんが舞ってらっしゃるはずよ。行ってみます?」
薫は思い出したように、そう言った。
「どうする? 晶子」
「そうね・・・」
晶子は少し考えるとその後に一言返事した。
「行きましょう」
「じゃぁ、案内するわ。こっちよ」
薫は先頭をきって歩き出した。安珠たちはその後ろをついていく。三、四分程歩いた後に、日舞部の練習場に到着した。
「思ったより遠い所にあるんだなぁ。もっと近いと思ったのに」
「・・・そうね」
晶子は何か思うことがあるのか、口が重い。
三人が練習場の中へ入ると、ちょうど永遠子が舞っているところだった。
「あの人が永遠子さんよ」
「へぇ・・・」
永遠子は真紅の地に白い大輪の椿の入った着物を纏っていた。半衿の白と椿の白とが真紅の地に栄えて、妙に女の色香を感じる。顔立ちも日本人形のように
整った色白の美人なのだが、気の強そうな性格だけは隠せない。学園の理事長の孫として相応しい、毅然とした態度で舞うその姿は、誰の目をも魅了することだろう。
しかし、安珠は永遠子を見た瞬時、背中に悪寒が走るのを感じた。
「あなた方が噂の転校生ね」
安珠がはっと気づくと、いつのまにか目の前に永遠子がやって来ていた。
「編入試験では、随分と良い成績を修められたようですね。私、とても驚きましたわ」
永遠子はふっと口の端をほころばせて言った。
「それほどでも」
晶子はそれとは対照的にとげとげしく応えた。
「あら、怖いこと。そんなことで良いのかしら。むやみに敵を作る必要はないのではありませんか?」
にいっと笑いながら永遠子は言う。少し顔が歪んだ。
「あら、これが普通ですのよ、私。ごめんあそばせ。さぁ、安珠行きましょう」
晶子はサッと踵を返すと練習場から出ていった。安珠と薫も慌てて晶子についていった。
|
  
|
「アヤツラ 人間デハナイナ」
少女は言った。
「ヒトリハ人間ノ匂イハスルガ ソレデモ人間デハナサソウダ。シカシ 詳シイコトハイマダワカラヌ・・・」
周りにはただ一人として在席していない。そんな中、少女はひとりで呟き続けた。
「だけど、あいつらは必ず私たちの邪魔をする存在になりましょう。そんな奴なら、私たちが倒してしまえば良いのだわ」
キッとつり上がった目に妖しげな冷気を漂わせながら微笑みを浮かべる少女―――永遠子は言った。生徒会室の自分の席に腰を掛け、窓から学園を見下ろす永遠子のその流れるような黒髪には、あのかんざしがささっていた。
|
  
|
晶子は安珠と薫を連れて、人のまったくいない校庭の隅へとやって来た。
「晶子ぉ、なんでオレたちがこのド寒い中、こんな誰もいない校庭の隅っこまでやって来なくちゃなんないんだよぉ。さっきの生徒会長のことといい、ちょっとは落ち着けよなあ」
不平そうに安珠は言う。
「貴方は黙っていなさい。さて、田端 薫さん、素直に聞くわ。貴女、一体何者?」
「え・・・」
「何言ってんだよ晶子。薫ちゃんは薫ちゃんに決まってんだろ」
安珠が口をはさむと、晶子はキッと安珠を睨みつけた。
「うっ・・・な、なんだよぉ」
安珠はその迫力に気圧されて弱気になる。
「黙りなさいと私は命令しているんです、アンジェラ」
「!! わかったよ、紫鏡」
自分のことをアンジェラと呼ぶ晶子に、重大な話をしているんだとようやく気づいた安珠は、おとなしく晶子の言うことに従うことにした。
「・・・さて、薫さん。もう一度聞くわ。貴女は誰?」
「あらぁ、何言ってるの? 安珠くんが言ったとおり、あたしはあたしよぉ」
薫はにっこりと笑っていった。
「とぼけても無駄よ。どう考えても、貴女は普通の人間の域を越しているわ」
「・・・」
薫は黙って晶子の言うことを聞いている。
「その根拠はふたつあるわ。まずひとつ。私たちが転入生として貴女の隣の席に着いたとき、貴女は言ったわね。『あの試験でよくあんな点数とれたよね』と。
まるで試験の内容を知っているかのような様子で。編入試験は非公開が原則。どうしたら普通の生徒がその中身を知ることができるのかしら? それは、単にことばのアヤだったとしても、もうひとつ。先刻、安珠が最初に耳にした日舞部のCDの音。あれは実は人間の可聴域―――つまり、人間の聞き取
れる音域を越していた。音が小さすぎるのよ。それなのに貴女には聞こえていた。案内されて五分ちかくかかるような場所で流れていた、さして大きくなかった
CDの音をね」
晶子は、さぁもう逃れる道は無い、というふうに薫をみつめた。
安珠は自分には決して気付けないことに気付いてしまう晶子の、その類稀な頭脳にただただ唸るばかりだった。
「そうねぇ・・・。ま、バレちゃったんなら仕方がないわね。からかっちゃってゴメン。でも、あたし本当はもっと後から正体を明かして驚かそうと思ってたんだけどなぁ。残念だなぁ」
そう薫が言った瞬時、薫の周りを光が取り巻いた。まばゆいばかりの銀色の光。
「・・・!」
「か、香ちゃんっ!!」
薫は美しい銀髪を持つ少女、セルリアに変化していた。
「じゃじゃーん。あは、驚いた?」
小首を傾げてにっこりと笑みを浮かべる。その様は、間違いなくセルリアが持つものである。
「安珠くんたちがジゴルゼーヌと戦っていたときね、前の学校の人たちの呪術による後遺症を取り払ってたんだけど、それが終わってから安珠くんたちがやって来そうな所で待ち伏せしてやろうと思ってさ。で、この学校を選んで待ってたの。えへ、あたしの勘は当たったってことね」
セルリアはとてもうれしそうに言った。
「なんだぁ、そうだったのかぁ。でも、会えてうれしいよ、香ちゃん」
「あたしもよ、安珠くん」
みつめあう安珠とセルリア。すでにふたりの世界と化してしまっている。ただひとつ、迷いのあるセルリアの瞳を除いては。
「それにしても、うまくダマしてくれたもんね。まんまとセルリアの策にはめられたわ」
晶子がそこでふたりの世界を破って口を出した。
「そりゃぁ、そうよ。あたしだって苦労したんだもん。フツーの人間のふりをするのってすっごい大変なんだから」
そういいながら、セルリアは笑う。
久しぶりに三人が顔を合わせ、和やかな空気が流れた。ひと時の平安。
これが平和なんだ。この平和をオレは守っていきたい―――安珠は心の中で強く誓った。
|
 |
各章へジャンプできます |
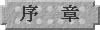 |
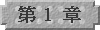 |
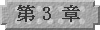 |
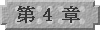 |
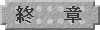 |

