「セルリア、もうあなたには今回の相手がわかっているのでしょう?」
「まぁね」
晶子と安珠が借りたマンションの一室で、紫鏡とセルリアはそんな話を始めた。
このマンションは4LDKの高級マンションなのだが、行動の拠点として最適の場所であったために、紫鏡が術を施して、いわば不法に住居としているのであった。むろん、家賃などは払っていない。収入のない人間(?)に家賃を払えというほうが無理な話である。
「で、敵さんはもう動いているのかしら?」
「気配だけは感じるんだけどぉ」
残念ながら―――という雰囲気でセルリアは首をすくめてみせた。
「まだ本格的には動いていないようね」
「そういうこと」
「ねぇ・・・」
今まで黙ってふたりの会話を聞いていた安珠が、ふいに口を開いた。
「ふたりとも、もう今回の相手が誰だかわかってるの? もしかして」
安珠は恐る恐る言った。
「当たり前でしょう。私たちはアンジェラと違って人間とは違う存在なのよ。それくらいのこと、わからなくってどうするの」
何をバカなことを―――紫鏡の紫の瞳はいかにもそう語っているように見える。
「でも、オレだってフツーの人間とは違うんだぜ」
安珠は少し拗ねたらしい。いつになく強気で言い張る。
「あ、そ。とにかく、超能力者だろうと、寿命が三百年あろうと、人間は人間。三千年は生きる私たち守護神的精霊とは、根本的に作りが違うのよ。とはいえ、私もそんなに長くは生きられそうにないのだけれどね」
紫鏡は一気にそういうと、少し疲れたようにため息をひとつ漏らした。
「ふぅーん、じゃあ紫鏡って・・・もうすぐ三千歳!! えーっ、信じらんねぇっ!?」
安珠はその大きな目をますます大きく見開いて叫んだ。
「当たり前でしょうっ。まだそんなおばさんなんかじゃないわよっ。私はまだ1823歳よっ!」
いたく憤慨して紫鏡は言った。
セルリアも横で、そうそう、と頷いている。
どっちにしても桁が違うよ―――と思いつつも、安珠は首を傾げた。
「なんでそれなのに、そんなに長生きできないなんて言うのかって顔ね、アンジェラのそれは」
紫鏡はくすりと笑った。
「私の寿命は本来三千年あったとしましょう。けれどね、神が私に与えたもうた力、絶対神術はね、その代償として、自らの命の炎を削っていくのよ。ほんの少しずつだけど、それは確実にね。だから恐らく、私は二千五百歳の誕生日を祝うことなく、寿命が尽きてしまうと思うわ」
「あの術って、そんな大変なものだったのか・・・全然知らなかった・・・」
安珠は絶対神術の真の恐ろしさを垣間見た気がした。それの真の恐ろしさとは、どんな人物・対象でも必ず術にかかるということではなく、その術を扱う術者の命を蝕んでいくということなのだ。
「もうひとつ、聞きたいことがあるんだ。香ちゃんってさ、依然黒梨(ヘイリー)と対峙した時に、黒梨のことを自分より年下って言ってたよね。香ちゃんって、一体今いくつなの?」
女性を相手にしながら、それでも臆することなく相手の年齢を聞いてしまう。純粋といえば純粋で、そこが安珠のいいところではあるが、悪くいえばただのデリカシーの欠如した人間である。
「あたしねー、すぐ自分の年がわかんなくなっちゃうんだけど・・・確か、2320歳のはずだよ」
しかし、セルリアはそういうことにはまったくこだわらないというように、すんなりと返答した。
「え、紫鏡より年上? うそだぁ、信じられないよ」
セルリアの返答に、つい大声を出して安珠は言った。
「あらぁ、本当よぉ。ただ、あたしは紫鏡や安珠くんが眠りについていた時も歩んでいた時間があるから、こんな年になっちゃったんだけど、生まれたのは紫鏡よりずっとずぅっと後なのよ」
「へぇ・・・それでかぁ」
安珠はフンフンという具合に頷いている。
「でも、あたしもあと三百年くらいの寿命でしょうね。なんていったって、邪悪の力による後遺症で人々が冒されないように、水晶の力を与えるのもだいぶ重労働だからね」
セルリアは肩をすくめながら言った。
「だけど、そのおかげで安珠くんの寿命が尽きてしまっても、すぐにあたしの寿命も尽きてくれるでしょう。そのほうがいいわ。やっぱり、別れほど悲しいものってないもの。悲しみ過ごす時間が少ないほうが、あたしはうれしい」
「・・・そうだね」
悲しそうに微笑むセルリアを見て、安珠もしんみりとしてしまった。
「さぁ、さぁ。シメッぽい話は置いといて。とにかく今日はもう休みましょう。あの学校で敵がどう動いているのか、明日ゆっくり調べることにしてね。さぁ、ふたりとも」
紫鏡はふたりを促した。
ふたりともそれに同意して、各々の部屋へと別れて行った。
|
  
|
永遠子はその時、ただひとり生徒会室にいた。
おもむろに紅色の袱紗から水晶玉を取り出し、そして永遠子は会長用の机の上に静かに置いた。
「サァ、ハジメヨウゾ」
永遠子は静かに頷くと、なにやら呪文を唱えだした。
「ふるへ、ふるへ、ゆらゆらと・・・ふるへ・・・」
すると、水晶玉の中に白い気体のようなものがフワフワと浮かんでいるのが見えた。
永遠子は息を呑んだ。
「案ズルコトハナイ、霊界トノ接点ヲ作リ出シタダケダ。サァ続ケヨ」
永遠子は何十枚もの生徒の写真を机の引き出しから取り出した。
「ふるへ、ふるへ、ゆらゆらと・・・ふるへ」
そう言いながら、取り出した写真に永遠子が次々と火を付けていく。
すると今度は水晶玉の中から気体のような白い物体がふわふわとたちのぼり、永遠子の周りをまるで覆い尽くすかのように取り巻いた。
「怯エルコトハナイ。ソレラハオ前ノ従順ナル下僕(シモベ)。オ前ハ自由ニコノ魂(タマ)ヲ操ルコトガデキルノダ」
まるで誰かに語りかけるかのように、永遠子はひとりで呟きつづける。
「コイツタチノ生命えねるぎぃデ邪魔者ドモヲ倒スコトモデキ、ソノ魂ノ器―――ツマリ人間ノ体ヲモ自由ニ操ルコトモ、オ前ニハデキルノダ」
永遠子は明るい笑みを漏らした。
「ソシテソノ魂ヲオ前ガ食ラエバ、ソノ魂ノ本体ハ死シテ果テル」
永遠子の目が鋭く光りを放つ。
「ソウダ、アノ女デモダ。母ノ魂ヲ取ルノダ。ソウシテソレヲ食ラウノダ」
しかし、永遠子は何故かためらいの感情に支配されていた。何か取り返しのつかない、恐ろしいことになるような気がして、それを心の奥底で無意識に予感して。
「殺シタイホドニ憎イ女ダ。何ヲタメラウ必要ガアルダロウカ、サァ」
永遠子に一体何が起きているのだろうか。永遠子は自分自身に命令でもするかのように、強く厳しい口調でことばを吐き出した。
「・・・わかりましたわ」
永遠子は観念したかのようにそうことばを漏らすと、先刻と同じ方法を用いて自分の憎い義母の魂を取り出した。
しばし、その靄もような魂を見つめていたが、目をつぶると永遠子はそれをひと息に飲み込んだ。
「クックック・・・コレデ オ前モ一人前ノ呪術者ダ。モハヤオ前ハコノ世界カラ逃レルコトハデキナイ・・・クックック―――」
永遠子は得体の知れぬ声でそう含み笑いをしながら、しかし、全身に喜びの感情は隠せない様子で打ち震えていた。
|
  
|
次の日の朝、安珠・晶子・そして薫が登校してみると、学校の様子は前日までとは一変していた。
「やっぱり・・・」
薫は呟く。
「これは・・・」
晶子は悲愴な声をあげた。
「どうしたんだよ、晶子?」
「周りをよくご覧なさい、安珠。ここにいる約半数が魂を失っているわ」
晶子がそういうと、安珠は周りの人間たちを見回した。
生徒のみならず、教師も、ほとんどの者たちが魂を抜き去られているようであった。もちろん、普通の人間では考えられないことである。魂を抜かれた人間たちは、誰かに操られ、一見普通に見える。普通に登校し、普通に生活を送る。そう、普通に、だ。
しかし、安珠たちは普通ではなかった。その異常を敏感に感じ取っていた。
「本当だ・・・まるで生気がない」
「とうとう、敵さんが動き出したのね」
薫が言う。
「そういえば、薫さん。貴女さっき『やっぱり』って言ってたわよね。気づいてたの?」
晶子の質問に薫は頷いた。
「ゆうべ、そろそろ寝ようかなと思った頃にね、気配を感じたの。水晶がそれを告げていたのよ。だから、何かあるな・・・と思っていたの」
薫は言った。
「だけど、こういう敵だったとは、正直言ってちょっと驚いちゃった」
「え? こういう敵ってどんな敵?」
「そうねぇ、敢えて言うなら“魂使い(タマツカイ)”かな」
「たまつかい・・・?」
耳慣れないことばに安珠は首をひねった。
それを晶子が説明する。
「古代日本の呪術のひとつでね、魂を操ることのできる術があるの。その術を操ることのできる術者のことを言ってるのよ、薫さんは」
「ふーん」
安珠たちは教室へと向かって歩いていた。
その途中、安珠は離れたところに永遠子を認めた。
「あ、あれ生徒会長だ。何だろう・・・? 白いモヤみたいなのがいっぱい・・・なんだか、周りを取り巻いてるみたいに見えるんだけど・・・」
「あれが人の霊魂よ。多くの霊魂が永遠子の周りを取り囲んでいるのよ」
晶子はそう答えた。
「へぇ・・・え? じゃぁもしかすると、さっき言ってた魂使いって、今回の敵って、生徒会長のことだったりするのか?!」
安珠のそんな発言に、晶子と薫は目を丸く見開いて互いに顔をみつめあった。
そうして、晶子はあきれたふうに口を開く。
薫はくすくすと笑っている。
「安珠、あんた今までほんとに全ッ然気づいてなかったの? あんたはそれでも半分は精霊の血が流れているのよ、わかってる? あー、情けない」
晶子はいい加減うんざりしてしまったという様子でふうっ、とひとつため息をついた。
薫は今まで笑っていたが、晶子のそのことばを聞くと途端に笑うのを止め、下を向いてしまった。
それを目の端に認めながら、晶子は言った。
「ま、安珠のそういう抜けてるトコが、逆にすぐ気負ってしまう私たちを安心させてくれるから、いいトコではあるんだけど。ねぇ、薫さん」
「え、ええ・・・」
薫は上の空というふうで微笑みの表情だけを浮かべていた。
セルリア――? 晶子は薫の明らかにいつもと違う様子に心を奪われた。
「晶子? どうしたの」
薫の様子がおかしいことにはまったく気づかないという鈍感な安珠が、それでも晶子の様子の異変には鋭く気をひかれた。
「え!? いいえ・・・」
晶子は気を取り直して答えた。
「あ、そうだ」
突然何かを思い出したかのように、安珠は急に話しはじめる。
「晶子の瞳ってさぁ、何かの能力を使っている時とかに紫色に変化するんだよな」
「・・・そうね。まぁ、別に能力を使ってるからとかじゃなくて、それが本来の色なんだけどね」
晶子は答える。
「いや、実際かっこいいなぁって思っちゃうんだよね、オレ。オレなんか、いっこずつ瞳の色違うし、変なカンジなんだもん」
「そんなことはないわよ。そういう希有な瞳をしている安珠のほうが、やっぱりいいと思うんだけど。ほら、ネコとかにもいるじゃない。あれって、結構人気高いんでしょ?それに、そのほうが安珠らしくていいじゃない」
「何か歯に衣着せた言い方だなぁ。何が言いたいんだよ?」
上目遣いに晶子を見ながら、いかにも不服そうに安珠は言った。
「別に。ただ、一応にも人間のはしくれの安珠のほうがいいんじゃないかしらーってことよ。精霊の瞳を両目に持っていたら、私があんたで遊べなくなっちゃうだろうから、今のままの、精霊と人間のハーフのちょっとおバカな安珠のほうが、私としては気に入っているってハナシ」
そう言って、晶子はけらけらと笑いだした。
「晶子ぉ」
安珠は恨めしそうに言った。しかしその実、嬉しそうにも見える。
「でも、この頃安珠ったら少し少し変よ。どうしたの? 私のことを根掘り葉掘り聞き出そうとしてるみたいじゃない」
ふっと、晶子は言った。
「え・・・べ、別に」
とまどいながら安珠は言う。
ホント、オレは一体どうしちゃったんだろう。この頃紫鏡のことばっかり気にしてるカンジだ――安珠は自分自身に対する疑問が膨らんでいくのを心に感じていた。純粋すぎて気づかない感情というものがあることを、安珠はまだ知らない。
「さぁ、行こうか」
もう教室に着く、そんな時に薫は突然そういい、進行方向と正反対を向いた。
「え? 行くってドコヘ? もう教室はそこだよ。これ以上ドコに行くつもりなの、香、じゃなくて薫ちゃん」
「もちろん、家に帰るの」
「え、家? なんでまた・・・」
安珠は薫の思いもよらぬ発言に度肝を抜かれた風だった。
「いろいろとわかったことがあったから、これからの対策を練りに、ね。準備がいっぱいあって、大変なのよ。ねえ、薫さん」
安珠の疑問に、代わって晶子が答えた。
「うん。それに、魂の抜けちゃった先生たちにお勉強、教えてもらいたいと思う? あたしはイヤ」
薫はくすくすと笑って言った。
「そういわれると、確かにそうか」
「でしょ。さ、早く帰ろ」
薫は安珠をせかした。
そうして、安珠・晶子・薫の三人はとんぼ返りで家へと帰っていくことにした。
今晩起きるであろう敵の攻撃に対抗すべく、その準備のために・・・
|
  
|
「いい、アンジェラ? 私は囮となって永遠子の元へと赴きます」
その夜、晶子は突然安珠に告げた。
「なっ、何故!!」
安珠は晶子の発言を絶対に賛成できないというふうに、声高に言った。
「そんな危ないこと、どうして?! 絶対にそんなこと、紫鏡がやるべきじゃない。ねぇ、香ちゃんもそう思うでしょう?!」
安珠はセルリアに賛同を求めた。
「そうね。あたしも紫鏡が行かなくってもいいと思うのよ。そう、その役目はやっぱりあたしの仕事なんじゃないかなぁ」
「うんうん・・・え? ええっ!! それもダメだよ、香ちゃんっ!!」
賛同してくれたと思いきや、自分の思いもよらないセルリアの切り返しに安珠はすっかりパニック状態に陥ってしまった。
「少し落ち着きなさい、アンジェラ。どうしても誰かが囮になって永遠子を調べなくてはならないのよ。どうしても」
晶子は安珠をなだめるように、しかし語気は強く言った。
「どうしてっ!?」
安珠はどうにも納得がいかない様子だ。
「い い? 精霊の剣は、人間の心がかけらも残らずすべて邪心に支配されてしまった人に使えば、その人は塵と消える・・・つまり死んでしまうのよ。アンジェラは知りたくない? 永遠子さんに人間らしい感情が残っていないか。願わない? この世から理不尽に消えてしまう人が出ないで欲しいって。私はそう思う。私たちは人間ではないから余計になのかもしれないけれど、勝手に一個の個人をこの世から抹殺してしまう権利があるのだろうかって。人間の世界にそんなに深く干渉していいのか、疑問もあるのよ。ただ、同じように人間とは異質のものが、深 くこの世に干渉しているという事実があって、それをできるだけ排除したいという意志があるからかそ、ここに私はいるのだけれど。それに、永遠子さんの背後には、必ず彼女を操る存在があるはずだわ。その正体を掴まなければ、思うように行動をとれないわ」
どう?・・・という具合に晶子は安珠を見つめた。
「言いたいことはわかるよ。でも、別に紫鏡が囮にならなくってもいいじゃないか。オレがその役、やるよ」
安珠もなかなか譲らない。
「無理よ、それは。安珠くんが囮役をしても、役目はきっと果たせない。安珠くんは半分はれっきとした人間だし、きっと永遠子さんにいいように操られてしまうもん」
そこへセルリアがことばを挟んできた。
晶子も深く頷いている。
安珠は黙り込んでしまった。
「囮にはやはり私がなります。アンジェラは私とセルリアの作る結界の中にいなさい。そして、私に何が起きても、絶対にその結界の外には出てはいけません。いいわね」
晶子は厳とした態度で言った。
「あ、ああ・・・」
かなり不服そうではあるが、晶子の命令なのだと思えば、それでも一応頷くしかない。
「セルリアは安珠が結界から出ないように、しっかりと捕まえておいてちょうだい」
「まかせておいて」
セルリアはにっこりと微笑んでみせた。
夜が更けていった。その中、安珠とセルリアは結界に守られるようにすやすやと寝息をたてている。晶子はそれをただひとり、いとおしそうにみつめていた。
そして、時計の針が二時をようやく回る頃、異変は起こった。
「あっ、うう・・・くっ」
晶子の苦しそうな声に、いままですっかり眠り込んでいた安珠も驚いて飛び起きた。
「紫鏡!」
安珠は叫んだ途端、結界から飛び出そうとした。
「け、結界から・・・うう、出るんじゃ、ないよっ。このバカッ・・・くくっ」
晶子はすかさずそれを懸命に咎める。
「そうよ、安珠くん」
やわらかな物言いとは正反対に、セルリアは安珠が結界から出ないよう、しっかりと安珠の腕を掴んだ。
「で、でもっ!!」
安珠に狼狽の色は隠せない。
「わ、私は平気・・・だ、から・・・あぅ」
晶子はそういった途端、がっくりとうなだれて倒れこんだ。すると、晶子のその体から薄い白味を帯びた陽炎のようなものがすーっと抜け出るのがわかった。しかし安珠が目を見張ったその瞬時、それは空気に溶け込んでいくかのようにその存在を消した。
「し、紫鏡っ、紫鏡ーっ!!」
安珠はセルリアの手を振り払って結界から飛び出ると、晶子の倒れこんだ場所へと走りよった。
しかし。
「あ・・・こ、こんな・・・」
晶子の体はそこには無く、ただ晶子の胸にいつも着けていた紫水晶のブローチだけが、淡い光を纏いながら転がっているだけであった。
「紫鏡・・・一体どこへ・・・」
安珠は晶子のブローチを握り締め、暫くの間呆然としていた。
「安珠くん」
安珠の側へセルリアは歩み寄る。
「し、紫鏡が・・・紫鏡が・・・僕、どうすればいいの? 教えてよ、香ちゃん、ねぇ」
それだけ言うと、安珠は床に突っ伏して鳴咽しはじめた。
「落ち着いて。泣かないで、安珠くん。大丈夫よ、紫鏡なら大丈夫。ね」
そういって、セルリアは安珠を優しく抱きしめた。
「紫鏡は大丈夫よ、精霊なんだから。胸のブローチのエネルギーで紫鏡はその姿を保っているのよ。エネルギーが抜けたから確かに体は消えてしまうケド、だからって死んでしまった訳じゃないのよ、わかるわね。だから、もう泣かなくっていいのよ」
セルリアは優しい声で安珠に語った。
安珠はうんうん、とただ頷くだけである。
そうして、安珠がようやく落ち着いたころ、セルリアはくすりと笑いながら言った。
「安珠くんったら、すごく動揺してたのね。いきなりあんなに泣き出すから、あたしビックリしちゃったよ」
安珠は恥ずかしそうに、顔のみならず耳までも真っ赤にしながら、俯いている。
「でも、安珠くんが今手にしてる紫鏡のブローチは、大切に持っていてね。そのブローチのある場所に、紫鏡は帰ってくるんだからね。しかも、そのブローチの紫水晶は紫鏡の命の一部なんだよ」
「うん、じゃぁ僕、いつも持ってるよ」
「そうね」
セルリアはにっこりと笑った。
「やっぱり香ちゃんは僕の彼女だね。僕、香ちゃんが彼女になってくれてよかった」
安珠は本当に無邪気に笑った。
その途端、セルリアの表情が凍りついた。ほんの刹那の出来事である。
安珠はその様子にまったく気づかないようで、紫水晶のブローチを大切そうに両手で覆うように持ち、そして見つめている。
「安珠くん、あのね・・・」
「え? 何、香ちゃん」
安珠は明るい声で返事をした。
「あ、ううん、別に・・・」
「?」
安珠は、何だったのかというふうに首を傾げはしたが、さして気にとめるふうもない。
セルリアは下を向いてしまった。
――やっぱり、安珠くんには言えそうにない。あたしが安珠くんの――
セルリアの心の中には大きな渦が巻き起こっていた。いまだ告白できない真実への苦悩の渦が。
|
 |
各章へジャンプできます |
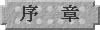 |
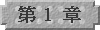 |
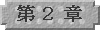 |
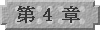 |
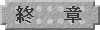 |

