「いやだぁーーーーーーっ、絶対にそんなのいやだぁーーーっ!!」
両隣の家にまで聞こえそうなくらいの大きな声。その声の主は安珠である。
「駄々をこねないで。あんた男でしょう。子供みたいなことを言わないでちょうだい、アンジェラ」
「男だからイヤなんだ!!」
「アンジェラ!」
紫鏡もそろそろ疲れてきた。
安珠の頑固は、誰の手にも負えるものではない。しかし、それほどにこだわるのには訳があった。
「オレ、女子校になんて、絶対行かないからなっ!!」
そう、安珠が強情を張るのはこれが理由なのだ。紫鏡は、安珠を女装させて女子校に入れようとしていた。
見た目に反して男気の強い安珠には、それがとても耐えられないのだ。
「わかったわ」
紫鏡はひとつ溜め息をついて言った。
「私が行くわ」
「えっ!!」
安珠はベッドに座っている紫鏡の元へ走り寄る。
「だ、だめだよっ! 紫鏡は安静にしてなくちゃだめだ!! まだ全快してないんだよ!」
安珠の言うとおり、紫鏡の体は今、無理がきかない。前に怨霊と対峙した時に使った術によるしっぺ返し――逆凪による後遺症が残ってしまったのだ。
つい昨日まで、それを安珠に気付かれないように隠していたのだが、日に日に悪くなる症状に、さすがの安珠も異変を察し、紫鏡はベッドに強制収容されてしまい、今に至っている。
「ダメだって言ったって、アンジェラが行かないって言えば他に行く人間はいないじゃないの。私が行くしかないでしょう?」
「でもっ」
安珠はどうしていいかわからない様子だ。
「でも、じゃないわよ。今回私たちが相手にするのは、もう五百年近く生きているような魔女なのよ。今の私の状態じゃすぐに私が普通の人間とは違うと正体がバレてしまうわ。だからアンジェラに頼んでいるのよ。でも、絶対に行かないというのなら、私が行くしかないでしょう」
そう、紫鏡は紫水晶の精霊である。人間ではない。普段は人間のふりをして生活もしているが、それなりにエネルギーも使う。今はそのエネルギーを使っていられない。ただ、養生するしかない。
そんな状態で敵地へ赴けば、さすがに正体も明るみに出よう。
更に言えば、五百年も生きているような魔女ならば、尚更である。人間とは異質の者同士は、すぐに互いの雰囲気でそれを感じ取ることができるのだ。
「アンジェラはこの街の人たちが皆、魔女にひどいことをされても構わないの?」
安珠はウッと喉が詰まったようになってしまって、何も言えなくなってしまった。
そこを突かれると弱い。
「それに、鏡の中から偵察に行ったとき、女の子に姿を見られたんでしょう。それはどうするつもりなの?」
紫鏡は少しだけ意地悪く笑ってみせた。
「わかったよぉ。やればいいんだろっ!?」
安珠はブスッとした様子で答えた。
「そうよ、そうこなくっちゃ。安珠って名前は変えなくって済むし、アンジェラなら美人になるわよ」
紫鏡はひどくうれしそうで、安珠は何となくはめられたような気分になった。
「どうせオレは女みたいな名前で女みたいな顔で、女みたいに細っこい体だよ」
拗ねたように、安珠はぽつりと呟いた。
時は一月、春にはまだまだ早く、時折雪がちらつくほどに朝晩の冷え込みが厳しい、そんなある日のことである。
|
  
|
「紫水 安珠さんね。あなたは三年二組ですよ」
ここ、聖マニフィカト女学園の校長は・・・と言っても、この学校はミッションスクールなので、正確にはシスターなのだが、彼女はにこやかな笑顔を向けながら、柔らかな口調で言った。
「この受験の近い時期に転校というのは大変なことですが、聖マニフィカト女学園の生徒として、立派なレディになるように努めてください」
「はい」
おとなしい、いかにも淑女といった感じの美人はしとやかに答えた。
と言っても、その美人はもちろん安珠、つまり性別は男なのだが。
しかし、どこから見ても女と見間違えるほどに美しい。紫鏡の術でおしりの辺りまで伸びたナチュラルウェーブのたゆたうような、それでいて艶のある美しい黒髪。明るいブラウンアイズの大きな、それでいて切れ長の両目。スラリと長身でまるでモデルのようなスタイル。ピンク色の唇は、まるで可憐な花を思い起こさせるほどだった。
紫鏡が手を加えたのは髪の長さだけだから、いかに安珠の土台が類稀なる美貌を持ち合わせているかうかがえる。
安珠にしてみれば、それがコンプレックスにもなっているのだが。
「紫水さん、あなたのクラスの担任はシスター・マルゲリータです。彼女は学年主任でもいらっしゃいますから、いろいろとお聞きなさいね」
校長は事務的に話を終えた。
『二組の担任で学年主任だってさ』
“変わってるわね 普通学年主任って 一組の先生がならないかしら”
安珠は紫鏡とテレパシーで会話を交わしていた。
その時、校長室の扉をノックする人物がいた。
「お入りください」
待っていたとばかりに、即座に校長は扉の向こうの人物に声をかけた。
「失礼します」
いかにも美人の出しそうな声と共に扉が開かれ、やはり声のとおりの美人が部屋の中へと歩みを進めてきた。
「紫水さん、この方があなたの担任です」
「マルゲリータ・リカーテです。宜しく」
安珠の担任となるその美しき女性は、これぞというくらいの大人の女である。セミロングのソバージュの髪は見事な金髪で、神に仕える身でありながら、全体的に派手なつくりの顔立ちには、真っ赤な口紅がのせられていた。その唇がますます艶っぽさをかもしだしている。
「さぁ、紫水さん。こちらへ」
シスター・マルゲリータは安珠を連れて教室へ向かった。
三年二組と書かれている教室は、北校舎の四階の一番端に位置していた。
妙な話だが三年一組は、教室数が増え、校舎を増築した結果、階下の三階に収められたのだということを、安珠はマルゲリータから聞かされた。
それにしても、マルゲリータはどう考えても日本人の血は一滴も混じっていない様子なのに、恐ろしく日本語がうまい。流暢だ。安珠は感心してしまった。
「生まれも育ちもイタリアですが、日本への関心から日本語は懸命に勉強しました」
シスター・マルゲリータはそう語っていた。
しばらくして、教室に到着したところで、シスター・マルゲリータは教室前方の扉を開けた。
みんなの視線が安珠の所へ集中する。
こういうの苦手だな―――と思いながらも、乗りかかった舟、と肝をすえて安珠はシスターの後に続いて教室の中に歩みを進めた。
「転入生です」
シスター・マルゲリータはたったひとことだけ告げた。
「あ、紫水 安珠です。宜しくお願いします」
安珠はぺこりとお辞儀をしてから微笑んだ。
少女らしい仕草である。紫鏡に、女の身のこなしかたを猛特訓してもらい、体得してこの学校に臨んだのだ。立派なものである。
「委員長」
「あっ、は、はい」
「何を惚けているのですか。そんなことでは困りますよ。転入生を宜しくお願いします」
そう言い残し、シスター・マルゲリータはさっさと教室から退出してしまった。
淡白なホームルームである。
すると、教室で静かに座っていた少女たちは急にバラバラと席を立ち、続々と教室から退出していく。
あり? どうなってんの、これ―――?
安珠がそう思うのも無理はない。普通なら転入生が来た日の休み時間ともなれば、好奇の目を持った生徒たちの幾人かは集まり、転入生を質問責めにしたりするものではないのか。
しかし、この学校ではそんなことにまるで関心がないかのように、気が付けば教室にはもうほとんど人が残っていない。
「紫水さん。よろしくね、委員長の炭野 貴子です」
ひとりの少女が安珠の背後から声をかけた。
「あ、よろし・・・」
安珠はそういいながら振り向くと、その少女の顔を見て、大きく目を見開き驚愕した。少女、貴子の顔は、まさしく安珠が鏡の中から見た、鏡の中の安珠の目撃者である。
度のきつそうな、まるでマンガでも最近はあまりみかけないような太い黒のプラスティックフレームのメガネ、ソバカスだらけの顔、無造作にふたつに分けて結わいたというような長いストレートの黒髪。どれをとっても美少女とはいいがたい、一心不乱に勉学に励んでいるというような少女。
いくら安珠がボケていたとしても、そこは安珠。女の子を見間違うはずはない。間違いなく鏡の中の安珠を目撃した少女である。
「どうしました?」
貴子は安珠の顔を覗き込むようにして見た。
『どうしよう、バレちゃうよぉ』
“何とかできないの? アンジェラ”
『無理だよ、紫鏡が考えろよ』
“し、知らないわよ”
安珠は紫鏡とテレパシーで言い合いを始めてしまった。そのために、しばし沈黙が訪れる。
「紫水さん? どうかしたんですか?」
貴子は再び安珠に聞いた。
「い、いえ。別に・・・」
ハッと我に返り、慌てて返事をする。
「そうですか・・・あら?」
「えっ!?」
貴子の発する一言で安珠の心は上へ下への大騒ぎである。
バ、バレたかな―――? 安珠の心臓は早鐘のようだ。
「肩に糸くずが。取って差し上げますわね」
思わずずっこけそうになる。拍子抜けして笑みがこぼれた。
「あ、ありがとう」
貴子は安珠の肩に手を伸ばし、小さな糸くずをそっと取り除いた。
その時にふっと安珠の顔に視線を投げる。
「あら?」
「今度はなあに?」
少々余裕が出たのか、安珠は笑みを浮かべたまま聞き返した。
「紫水さん、私と以前にお会いしたこと、ありませんでしたか?」
「えっ! き、気のせいじゃありません?」
突然核心に迫られ、笑う顔もひきつってしまった。
安珠は今にも湯気が出そうなほどに体温が上昇して、体中冷や汗が噴き出すのを感じていた。嘘をつけない、良く言えば素直な、悪く言えば単純な性格なのだ。
「そんなはずないわ」
貴子は真剣に考え始めてしまった。
「・・・」
もう何も言うことが見当たらないというように、安珠は貴子の反応を待つばかりとなる。ただ、気づかないで欲しいと願うのみだ。
「えっとー、つい最近なのよ。えーっと・・・あっ!」
「やばっ」
貴子が思い出した様子をみせて、安珠は慌てた。
『オレ、力使うぜっ』
“人に見られないようにね”
安珠は貴子の腕をとっさに掴んで、屋上へと瞬間移動した。立ち入り禁止になっていて、鍵もかかっているので好都合なのだ。
「あなた、鏡の中にいた・・・えっ、ええっ!?」
周りの様子が瞬時に変わったのを見て、貴子は驚きの声をあげた。なにしろ、春の訪れもまだ少し早く、木枯らしが体を縛りつける立ち入り禁止の屋上にいるのである。驚かないはずがない。
ごまかそうと思えば、口八丁手八丁でいくらでもごまかせただろうに、こういう時にはまったく頭が回らないのが、安珠と紫鏡である。ここにセルリアがいたなら、うまく切りぬけていたことだろう。
「い、いつの間に。ど、ど、どうやってここまで来たんですか!?」
貴子は少々気が動転してか、どもった口調で言う。
逆に、こうなったらヤケだとばかりにここまで瞬間移動してしまった安珠は、すっかり落ち着いた様子で、貴子のその質問に、少し呆れてしまった。
「“どうやって”ってねぇ。炭野さん、オレとどこで出会ったか覚えてるんでショ」
「えっ? じゃぁ、あなた、人間じゃないんですか?!」
安珠が鏡の中にいたことを思い浮かべて、貴子はそういった。
安珠も気が抜けて、ことばがすっかりいつもの男ことばに戻ってしまっている。
「うーん、一応自分では人間のつもりなんだけど、まぁ、その中間ってトコか。いわゆる超能力者だね。オレなんか、新陳代謝も遅れてるし、普通の人間とは違って、三百歳くらいまで生きちゃうんだ」
ついつい自慢げになって余計なことまでしゃべってしまう。
「えっ! 本当に?」
「本当だよ」
「すごーい!!」
そのことばが益々安珠を嬉しがらせた。もう得意満面といった感じである。
「ところで・・・」
貴子は尋ねた。
「あなたって、男の人なんじゃないんですか?」
「そうだよ、オレは男」
にっこりと笑って安珠は言う。しかし、その姿はとても男とは思えないほどにかわいい。
「じゃぁ、どうして男の人のあなたがこの聖マニフィカト女学園に? 変質者って訳ではないみたいですし」
いきなり核心に迫ったというようなその質問に、安珠は困った顔をしてみせた。
『紫鏡、どうする? 話すべきかな』
“そうねぇ。コソコソと好奇心だけで探られるよりは、ね”
紫鏡とテレパシーで相談をして、ようやく答えが出た。
「オレはいわゆる正義屋さんでね。この学校にちょっと悪いことが起きてて、そんでイヤイヤながらも偵察に入り込んでるってワケ。もし何か変なことがあれば、君も協力して情報を教えてね」
「はぁ」
あまりにも思いもよらない話でピンとこないのか、あやふやに貴子は頷いた。
「では、改めて。よろしく、炭野 貴子さん」
「あ、はい。・・・ところで」
貴子は再び安珠に質問した。
「ここから、どうやって戻ったらいいんですか? 私」
「あ、そっか」
すっかり忘れていた。ここは内から鍵のかかった立ち入り禁止の屋上。もしここで貴子にひとりで帰れといっても、とうてい無理なはなしである。そんなことをかけらも思い出しもせずに、ちゃっかりひとりで帰ろうとしていたのだ。
「じゃぁ、オレに掴まって」
「はい」
一瞬のうちに屋上から扉一枚内側、屋上へ抜ける階段の踊り場へと移動した。
ここなら目撃する人間はいないだろうと。
「・・・はぁぁ、すごい・・・」
貴子は感嘆の声を漏らした。
「どうしたの?」
「紫水さんの能力って、すごい。好きな距離を移動できるんですね」
貴子のメガネの下からも、驚きの表情が見て取れるくらいの感嘆ぶりである。
ちょっと照れくさそうに頬を赤らめながら、安珠はそのよく通る澄んだ声で言った。
「・・・うん。普通ならすごく疲れたりしちゃうものだと思うんだけど、オレとかにしてみると、寿命も長くて生命力強いし、逆に楽できるんだよね、テレポートって。ご覧のとおり。便利なもんです」
「そうなんですかぁ」
「そ。あ、授業!!」
安珠は思い出して叫んだ。
その時ちょうど、一限目開始のチャイムが鳴り始める。
「行こっ、炭野さん。急がなきゃ」
「あ、はい」
慌てて安珠と貴子は教室へと向かっていった。
|
  
|
その日の放課後、安珠はマルゲリータに呼び出され、理事長室へと向かっていた。
『理事長室で、いったい何をしようってんだろうね』
“さぁ。とにかく行ってみないとわからないわね”
『ああ』
そうして安珠は理事長室の扉の前に立つ。
大きくひとつ息を吐くと、安珠は扉をノックした。
「お入りなさい」
マルゲリータの声が部屋の中から返ってくる。
「失礼します」
と声をかけながら扉を開けて中へ入ると、マルゲリータは理事長のものだと思われる大きくて高価そうな革張りの椅子に腰をかけていた。
その両脇には生徒がふたり、まるで従者のように立っている。ふたりとも、美しい髪と透き通るような肌を持ち、品のある顔立ちだったが、感情のないうつろな瞳をしていた。
「せ、先生? 理事長先生の椅子に座っていてもよろしいのですか」
不思議に思い、素直に安珠は尋ねてみた。すると、マルゲリータはにっこりと微笑んだ。
「いいのよ。これは私の椅子ですから」
そう言いながら椅子から腰を上げると、マルゲリータは安珠の側へと歩み寄った。
「えっ、じゃぁ先生は理事長先生でいらっしゃったのですか?」
「ええ」
安珠の目の前に立って、マルゲリータは答えた。かなりの至近距離である。知らず知らずに安珠の体は少しのけぞって、距離を保とうとしている。マルゲリータはなにか怖い。射るようにまっすぐと安珠の眼差しに視線を絡ませてくる。
「安珠さん」
マルゲリータはそういいながら、彼女から離れようとしている安珠の体を引き寄せるようにぐっと腰に手を回した。
「あっ」
益々ふたりの距離は縮まる。これが男女なら間違いなく唇を重ねる距離である。安珠はマルゲリータの腕の中に納まってしまっているのだ。
安珠は益々怖くなった。女性に対してこんなに怖いと思ったことはこれまで一度もない。自分が今、なんの抵抗もできない女としてここにいて、彼女に束縛されて、初めて恐怖を抱いた。
「安珠さん」
もう一度マルゲリータは安珠の名を呼び、そして安珠の顎に手をかけた。
「あっ、先生! 何を!!」
身体中に鳥肌がたつ。安珠は正気を保つので精一杯だった。
「本当にかわいいわ、あなた。ねぇ、私の目を見て」
「え・・・」
“アンジェラッ”
紫鏡の声が頭の中に突然飛び込んできた。
“アンジェラッ!! 目を見てはダメよっ!”
『え? 何故』
“それ、一種の催眠術よ。ブローチを送るから、眼光を跳ね返すのよ。そうしないと、貴方の貞操の危機だからねっ”
『わ、わかったよ!!』
安珠がテレパシーでそう答えると、安珠の左手の中に瞬時に紫鏡のアメジストのブローチが現れた。それを安珠はギュッと握りしめる。
「あぁ、早く私の目を見て」
「・・・あ、はい」
安珠はマルゲリータに気付かれないように、ブローチを持った左手を胸の辺りまで持ち上げた。
マルゲリータはにたりと笑った。紅い唇が艶やかに光りながら大きく横に広がる。
「私好みの子。私のものになるといいわ」
うっとりと安珠をみつめる。
完全に世に言うレズである。そう確信して、更に安珠は悪寒を走らせた。やはり、自分にはこの世界にはついていけない、そう思った。
アブノーマルといわれる人間の中には、常軌を逸した怖さや気味悪さを持った人間がいる。その人たちの目は多くのものを見ず、狭い世界観でしか行動しない。
安珠は本当に気を失いそうになるのを必至で耐えた。
そして、マルゲリータが術をかける瞬間、素早くマルゲリータの目の前にブローチを突きつけた。自分は両目を固く閉じて。
「えっ!! あ、あなたっ!!」
マルゲリータはヘタッと床に座り込んで、それっきり、何も言わず少しも動かずという状態になってしまった。
「この人、大丈夫かなぁ?」
安珠はマルゲリータの目の前にピラピラと手をかざしてみたりもしたが、反応はない。
更に言えば、マルゲリータの従者のように寄り添うように近くに立っていた生徒ふたりも微動だにしない。
“大丈夫よ。それより、早く家に帰ってらっしゃい。今日はセルリアがやってくる日なんだから”
紫鏡は言った。もちろんテレパシーでなのだが。
「あ、そっか。やった。明日は日曜日だし、みんなでゆっくりできるんだ」
“ええ”
「よーし、早く帰ろっと」
うれしそうに、明るい声でそういうと、安珠はスキップするようにして理事長室を後にした。
しばらくすると、へたり込んでいたマルゲリータはブツとブツ呪文か何かを唱えはじめ、その後ニ・三分ですっくと立ちあがった。
まだ頭の中にモヤがかかった状態のようで焦点の合わない視線をしてはいたが、それもすぐに払拭され、怒りのこもった視線で安珠が立ち去った扉を睨み付ける。
「あの子は何なのっ? 紫水 安珠、私の術を跳ね返すなんて・・・普通の人間ではないのかもしれないわね。少し、警戒をすべきか」
どこか血の匂いのする濁った鋭い眼差し。その視線の先を側にいるふたりの女生徒に向けて、顎をしゃくりあげる。
すると、少女たちはマルゲリータの側に擦り寄るように体を寄せてきた。
「かわいい子羊たち、また新しい仲間を増やしてあげよう」
マルガリータはうれしそうに、その紅い唇を大きく歪ませると、ひとりの女生徒の柔らかな頬を舐め上げた。
|
 |
各章へジャンプできます |
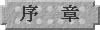 |
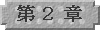 |
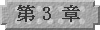 |
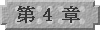 |
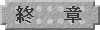 |

