アンジェラ・シェンはドイツにやって来ていた。
別に海外旅行に来たわけではない。
紫鏡が命を落としてしまった、あの魔女マルゲリータとの戦いから、ゆうに半年が過ぎていた。
「本当に、紫鏡はドイツにいるんだろうか」
アンジェラはダイアナに言われたことを思い出していた。
それは、ほんの一週間ほど前、アンジェラがドイツへ来る前の話である。
「アンジェラ君、紫鏡が蘇りました」
唐突にダイアナは、そう話した。
「え!? 本当ですか、それ!?」
「セルリアにも感じるでしょう、紫鏡の気配を」
「はい、ダイアナ様」
ダイアナもセルリアも意外そうな顔をしている。
しかし、一番驚いたのはアンジェラであった。
「ど、ど、どうして紫鏡が! だって、あのブローチは粉々に・・・」
「しかし、あの大鏡の行方はわからなくなっていたでしょう?」
「ええ」
ダイアナとセルリアの物を含んだ物言いはアンジェラにはあまりよく理解できない。
「一体どういうこと? 香ちゃん、オレにもわかるように説明してよ」
セルリアは仕様がないといった様子で軽く溜め息を漏らすと話しはじめた。
「つまりね・・・あの村へ帰ったとき、村の守り神であるはずの大鏡がなくなっていたワケよね」
セルリアは、ひとつひとつ確認をとっていくように、わかりやすく説明しようと心がけてくれる。
「うん、なかった」
「ということは、誰かがやって来て、珍しく思ってそれを持ち出したってことよね」
「ちょっと待ってよ、それって不可能なことなんじゃないの?」
アンジェラが話を止める。
「どうして?」
「だって、あの村には紫鏡の力で結界が張られて・・・あ、そうか・・・」
自分で話しながら、その誤りに気付いてしまい、そしてその結果が、できれば忘れてしまいたい哀しい記憶を思い出させたのだ。
アンジェラは下を向いて黙り込む。
半年が経っても、アンジェラにとっては、紫鏡を失ったという記憶は未だ昨日のことのような、真新しい傷のように心を傷めさせた。
「そう。結界は張られていたけど、紫鏡が死んで、その結界も消えてしまった。そして、大鏡は誰かの手へ渡り、何処かの大富豪によって、紫水晶が再びはめ込まれることになった。紫鏡の本体はあの大鏡よ。ブローチは単なる連結器でしかないわ」
セルリアはそう続けた。
「じゃぁ、つまり紫鏡はあの大鏡が今ある所にいることになるんだね」
「そうよ」
「ですけれど・・・」
その時、ダイアナが口を開いた。
「何ですか? ダイアナ様」
アンジェラはいっぱいに輝かせた瞳でダイアナをみつめた。アンジェラにとってみれば、恋しい紫鏡が生きているという事実がうれしくて仕方がないのだ。
「いえ」
ダイアナはそれを見て、何かを言いたげではあった。
しかし、結局口にはせず、再びその口を閉ざした。
普通、守護精霊として命を落とせば蘇生は不可能なはず。別の精霊が後を継ぐことになるきまり。いくらレイに血縁が無くとも、レイがこのように蘇生することなど、本来はあり得ないこと・・・
ならば何故?
もしやすると、これは精霊聖女王が!?
いいえ、そんなことあり得るわけは・・・
しかし、そうすれば、これもすべて神のプログラムに組み込まれていることなのかもしれない。
ならば、聖女王はすべてお見通しか―――
神妙な面持ちで、ダイアナは思考を巡らせていた。その考えは、アンジェラにも、ダイアナにさえも考え及ぶ範疇ではなかった。故にダイアナは口を噤んだのだ。
思い過ごしであれば良いのだけれど―――
ダイアナはその考えを打ち消そうと自分に暗示した。
「で、紫鏡はどこにいるの?」
「それは私がお教えしましょう」
アンジェラのことばで我に返ったダイアナが、再び口を開いてそう答えた。
そうして、アンジェラは、ダイアナに教えられた通り、ドイツへとやって来たのである。
紫鏡を捜し出すために。
セルリアとダイアナは、つい先日取り掛かり始めていた、中国・北京に現れた人食い妖怪を始末してから、少し遅れてドイツのこの地に来ることになっていた。
「面倒臭いなぁ。鏡の中を飛んだほうが、ずっと早く紫鏡をみつけられそうだな」
と、言うが早いか、途端にアンジェラは近くのショウウインドウに飛びこんだ―――といっても、ショウウインドウの中の鏡の世界に、の話だが。
「ダイアナ様の時みたいに、人に見られた、なんて失敗だけは、今回は気をつけなくっちゃいけないな」
などと言っているアンジェラだが、すでにショウウインドウに飛び込む時に、多くの人々がそれを目撃し、大騒ぎになっていたということには気付いていないようだった。
|
  
|
「ひぇー、それにしてもかがみの多い町だなぁ。ヨーロッパは全体的に鏡の多いイメージがするけど、ここは特に多いよ。なんじゃ、こりゃ」
アンジェラがしばらく鏡の中の世界を彷徨っていると、前方に紫色の淡い光が見えた。
「あ、あれ、紫鏡の大鏡だ。見つけた!!」
アンジェラは、その紫色の光の中に飛び込んだ。
「よっ、と」
鏡の外へ出ると、アンジェラは紫鏡の姿を探して周りを見まわした。
「あれ?」
自分以外は他に誰もいない。
何処かの屋敷の屋根裏という感じである。
周りには多くの鏡が置かれている。
ここは、ヴィクトールの住む、ハーンイシュターク城の屋根裏部屋だった。
「これは間違いなく紫鏡の大鏡なのに、当の紫鏡は何処へ行っちゃったんだよ? それにしても、この部屋、すっごい鏡の量だなぁ。ざっと数えて、四・五十個はあるぞ」
と、その時、部屋の重い木の扉が開かれて、中へ入ってきた人物がいた。
すっと、アンジェラは自然に警戒をする。
部屋にやってきたその人物こそ、アンジェラが待ち望んでいた紫鏡その人であった。
|
  
|
「し、紫鏡!?」
部屋に入ってきた紫鏡は、上等の生地――アンジェラにはその生地がなんなのか見当もつかないのだが――で仕立て上げられた襟ぐりの大きく開いた、レース使いやドレープのかけかたが絶妙で、スラリと長身の紫鏡の体にぴったりのエレガントで洗練された生成り色のくるぶしまであるロングのワンピースに見を包み、その上にストールをかけていて、いかにも何処かの令嬢という様子である。
「貴方、誰?」
「・・・え?」
思いもよらない紫鏡の反応に、アンジェラは一瞬我が耳を疑った。
「――オレだよ、アンジェラだよ。何冗談言ってんだよ、紫鏡は」
すぐに気を取り直し、アンジェラはとびきりの笑顔で紫鏡の姿をみつめた。
しかし、紫鏡の反応はいまいちはっきりとしない。
「すぐに見つけ出さなかったこと、もしかして怒ってるの?」
紫鏡の肩に手を置こうとして、アンジェラは両手を紫鏡へ伸ばした。
しかし、紫鏡はそれに対し、明らかに怯えた様子で一歩後退した。
「紫鏡・・・?」
アンジェラは怪訝な顔で言う。
「一体どうしちゃったんだよ。オレだよ、アンジェラだよ! まさかホントに忘れちゃったのかよ!?」
アンジェラは紫鏡の腕を強く掴んで引き寄せようとした。
「いやっ、やめて!! 私、貴方なんか知りません!! 放してっ!!」
「紫鏡!!」
信じられない、という様子のアンジェラは益々その手に力を込めた。
「痛い!! やめてください!! 旦那様っ、旦那様―――っ!!」
紫鏡はたまらずに叫んだ。
すると、まるで飛ぶ矢の如く、物凄い勢いでヴィクトールがやってきた。
「どうした、パーラジェーン!?」
ヴィクトールは驚いた。見ず知らずの男が何時の間にか屋根裏に現れて、しかもパーラジェーンの腕を掴んでいるなんて、思いもよらなかったのだ。
「旦那様! この人が」
紫鏡は視線でアンジェラを恐る恐る指し示した。
「お前は何者だ。私の城で、わたしのパーラジェーンに何をしている!」
驚きと恐怖を飲み下し、平静を装うとヴィクトールは、強い口調でアンジェラに向かった。
「パーラジェーン? 冗談じゃない、こいつはオレの紫鏡だ。レイ・紫鏡だ。勝手に名前つけんなよっ。オレはアンジェラ・シェン。紫鏡はオレの恋人だ! 返してもらおう」
アンジェラは、妙に紫鏡がこの見知らぬ男――ヴィクトールと仲良さげなので、不機嫌な様子を隠しきれない。
しかも、紫鏡は自分のことを知らないと言うのだ。アンジェラにとって、これほど衝撃的なことはなかっただろう。
「お前の、だと? 笑わせるな。パーラジェーンは私のものだ。証拠を見せて差し上げようか? パーラジェーンは私の言うことなら何でもきく。そうだな」
「はい」
紫鏡はヴィクトールのことばに同意し、軽く頷いた。
「パーラジェーン、ここへおいで」
「はい、旦那様」
そう答えると、紫鏡はヴィクトールの前で跪く。
「パーラジェーン、ここで服をお脱ぎ。できるかい?」
「なっ、何だって!?」
アンジェラは驚いて、大声で叫んだ。
自分の前でさえも、その肌のほとんどを見せることなどなかった紫鏡が、そんなことをするはずがない。しかも、こんな見知らぬ男の言いなりになってだなんて――とは思いつつも、アンジェラの不安は拭い去れない。
「旦那様が・・・言われるのでしたら」
アンジェラの不安は現実になった。
少し顔を赤らめつつも、アンジェラのことなど気にも留めないといった様子で、紫鏡は自らが纏っているストールをすとんと地に落とした。
「し、紫鏡? や、やめろよ・・・」
信じられない、といった面持ちのアンジェラは、ゆっくりと、優雅に美しくその衣を脱いでいく紫鏡の様子を目にして、いたたまれない気持ちだった。
そんな、見知らぬ男の前で、その男の命令で、紫鏡の未知なる、神秘な姿を見たくはなかったし、他の誰にも見せたくなかった。
「やめてくれよ、紫鏡!! お願いだよ!!」
アンジェラにも、そろそろ我慢の限界である。
紫鏡の裸は恐らく酔うほどに美しいだろうし、それを見てみたい――
アンジェラも男であり、そう思う気持ちもあった。しかし、その気持ちは自己嫌悪を招き、更にアンジェラを苦しめるのだ。
その間にも、紫鏡は衣服を脱ぎつづけ、とうとう下着姿になっている。
「やめろっ、紫鏡! やめろ―――っ!!」
アンジェラは見るに耐えかねて、すでに半泣きの状態で、悲痛な叫びをあげた。
「・・・ああっ!!」
途端、そう叫ぶように口を開くと、紫鏡は衣を脱ぐ手を止めた。
「どうした? パーラジェーン」
「いえ・・・ただ・・・」
紫鏡は焦点の合わない視線で、床をみつめて言った。
「何かを思い出せそうな・・・気がした・・・のですけれど・・・」
「そうか・・・」
ヴィクトールはひとつ溜め息をついた。
「もういい。悪趣味なお遊びは終わりにしよう。早く服を着なさい」
「はい・・・旦那様」
紫鏡は先刻とは逆の経路をたどり、先ほどとはうってかわって素早く服を身につけはじめる。
「さて」
ヴィクトールはアンジェラに向き直った。
「おわかりいただけたかな。とは言っても、かわいそうな君にチャンスを差し上げようと思う。ご覧になって気付いただろうが、パーラジェーンは記憶を失っている。もし、君が三日以内にパーラジェーンの記憶を取り戻し、そしてパーラジェーンが本当に、その紫鏡とかいう名前の君の恋人だったと判明したならば、私はおとなしくこのパーラジェーンから手を引くことにしよう」
ヴィクトールは不適に微笑んでみせた。
「どうだい? チャレンジするかい?」
「もちろんだ!!」
アンジェラは、その紫瞳と緑瞳で、強気にヴィクトールを睨み付けた。
|
  
|
ヴィクトールは自分の部屋の、ドレープのゆったりと入った柔らかなソファに埋もれるように腰をおろし、深い溜め息をひとつ、洩らした。
「アンジェラ・シェン・・・か」
ヴィクトールの脳裏には、紫鏡が目の前に現れたときに無意識に発したことばが、固くこびりついていた。
「“アンジェラ、何処”と、確かに彼女は口にしていた。本当にあの男の言っているとおり、パーラジェーンが紫鏡とかいう女だとしたら・・・いや、もしそうでも、三日以内にパーラジェーンの記憶を呼び戻そうなんて、到底無理だろう。そうだ。パーラジェーンは私のものだ」
ヴィクトールはそういうと、疲れたのだろうか、静かに目を閉じた。
その時、アンジェラは客室に案内されたところだった。
さすがに城だけあって、客室も広い。リビングとは別に隣にベッドルームがある。
リビングだけでも十六畳くらいはありそうで、天井のシャンデリアが、いかにも豪華の象徴という顔をして、きらびやかに輝きながら吊るされている。部屋のあちこちに置かれている絵画や置物も、どれも一見して高価とわかる品ばかり。そしてセンスもよく揃えられている。絵画などは、デューラーやノルデといったドイツの有名な画家のもので統一されている。センスだけではなく、愛国心の強さも伺える装飾だ。
「すごい・・・」
アンジェラは絶句してしまった。
「隣も、こんなに凄いのかな」
ふと、ベッドルームも気になって、隣の部屋―――ベッドルームへと続く扉を開いた。
「うわぁ」
半端でなく、とにかく広い。寝るだけの部屋じゃないのか、といいたくなる程だ。
室内は落ち着いた色調でまとめられていたが、ここまで広いと、どんなことをされても、日本の生活に慣れ親しんでいるアンジェラには、到底落ち着けそうにはなかった。
「こんなとこにひとりで、オレ、今夜眠れるかなぁ・・・」
その時、ベッドの辺りに気配を感じた。
「え!?」
ベッドを見ると、誰かがもぐり込んでいる感じである。
スゥッと布団から足だけが滑り出た。白くて形のよい、長い女性の足である。
「え、え?」
アンジェラは焦る。
その女性が、もしや裸ではないのかと思われたからだ。
「だ、誰ですか、そこにいるの・・・」
アンジェラは恐る恐る声をかけた。
すると!!
「バアッ!!」
「うわっ!」
その人物は布団を蹴飛ばしたらしく、布団は宙を舞い、ベッドの脇に落ちた。
「か、香ちゃん!!」
そう、そこにいたのはニヤニヤと笑みを浮かべたセルリアと、バツが悪そうに苦笑していたダイアナだった。
もちろん、ふたりともきちんと服は着ていた。
「あはははは。ごめんねぇ、ついイタズラしたくなっちゃって。あんまりにも安珠くんったら来るのが遅いんだもん」
セルリアは高らかに笑いながら言った。
セルリアたちがいうには、ふたりはあっというまに一撃必殺で人食い妖怪を退治し、ダイアナの力で、ここドイツまでやってきた。アンジェラを探すよりも、紫鏡を探すほうが楽だろうということで、アンジェラよりも少し早く、この城に侵入していたとのことだ。
「すごいなぁ、そんなに早くわかっちゃうなんて」
アンジェラは感嘆の声を洩らした。
「当たり前よ。ダイアナ様は聖従二位っていう、超! 高い位を持つんだから」
セルリアはまるで自分のことであるかのように、誇らしげに言う。
「“せいじゅうにい”って、一体なに? 紫鏡も言ってたよね、“せいごい”とかって」
アンジェラは少しもわからない、という顔でセルリアを見る。
それはそうだろう。
精霊聖従二位、聖五位というのは精霊界での格位である。これによって、能力も地位もまったく違うものになるのだ。
一般に、貴石の守護精霊になるのは聖従五位、つまりセルリアの位からである。そこから、精霊界では高格精霊と呼ばれるようになる。
そして、精霊聖従二位から上は、神域のようなものになる。なぜかといえば、これより上の位は、精霊界でも名門中の名門貴族である、モーゼ家、つまりはダイアナの家系の精霊と、聖女王から認められた異例の能力を持ったものにしか与えられることはないのだ。
「へぇー、何かすごいんだなぁ」
セルリアに説明されて、その精霊界のシステムの一端を知り、アンジェラは再び感嘆の声を洩らした。
「ところで」
アンジェラはダイアナに向き直った。
「紫鏡がすっかり記憶を失くしてしまってるんです」
冷静さを装っているものの、それでもその表情は険しい。
ダイアナの表情も、セルリアの表情も、冴えたものではなかった。ふたりにしても、この事態は予想だにしなかったのだろうということを感じさせる。
「恐らく・・・」
ダイアナはゆっくりと口を開いた。
「蘇生による一時的な記憶喪失だと思われます。ですから、すぐにきっかけさえあれば、すべてを思い出すと思いますけれど・・・」
「その“きっかけ”は自分でみつけなくっちゃ、ダメってことか」
ヴィクトールに約束したものの、アンジェラは段々と弱気になっていた。
脳裏には、先刻の、まるでヴィクトールのおもちゃになったような紫鏡の姿がチラついた。
「アンジェラくん、何もしない前から弱気になっては駄目ですよ」
ダイアナは、気持ちはわかるけれど―――という顔でアンジェラに優しく微笑んだ。
「・・・ダイアナ様には隠せないな。そうだね、何もしないであきらめてちゃいけないよね。オレ、努力してみます」
少しだけ、いつものアンジェラに戻ったような、そんな素直ではりのある声だった。
|
 |
各章へジャンプできます |
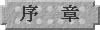 |
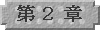 |
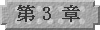 |
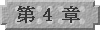 |
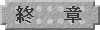 |

