ハーンイシュターク城には、大食堂があった。
一緒に三十人はゆうに食事を摂れる長テーブルが真中にどっしりと陣取り、昼は日の光が射し込み明るく、それでいて上品な装飾品がここかしこに見うけられる部屋である。
長テーブルに添った三つのシャンデリアや、毛足の二センチもあるような絨毯、背当てとクッション部分が革張りで、見事な鷲の彫刻が施された椅子。それに対なす長テーブルにはクリスタルやマイセンの花瓶に生けられた季節の花々。そしてマイセンや銀製の食器の数々。知らずに溜め息が洩れる。
そこでヴィクトールと紫鏡は客人よりもひと足早く朝食を摂っていた。
「食事中悪いんだが・・・」
そういいながら部屋にやって来たのは、昨日から客人となったアンジェラである。
「今日一日、紫鏡をオレに預けておいてくれないか」
そのアンジェラの申し出に、ナイフを動かしていたヴィクトールの手がぴたりと止まった。
「それは断る」
一言だけ口を開くと、再びナイフを動かして、黙々と朝食を食べ続ける。アンジェラの方には一瞥もくれずに。
「何故だ!!」
アンジェラは、この横柄な態度をとり続けるヴィクトールが無性に気に入らない。記憶を失った紫鏡がべったりなのに嫉妬しているということも、その一因にはあるだろうが。
それを大人げない奴だと思っているのか、それともこれはクセなのか、不敵な笑みを浮かべながらヴィクトールは再び口を開いた。
「今日は正式な、来客があるのだ。パーラジェーンも会見させることになっている。君の申し出は、申し訳ないが受けられないな」
「・・・」
アンジェラは苦虫を噛み潰したような表情で、しばらく考えていたが、
「なら、オレも一緒に行動させてもらうからな」
と、話を切り返した。
「・・・いいだろう。君に残されている時間はたった二日、だ。私たちと一緒に行動するといい」
ヴィクトールはそう、無表情に言う。
アンジェラよりも、ヴィクトールの方が一枚上手だと感じさせるやりとりだ。言動の端々に嫌味を織り交ぜながら、さらりとヴィクトールはことばを返す。
「ありがとう!」
それでもアンジェラは、自分の思い通りに紫鏡の側にいられることになったので、いつも通りの屈託のない笑顔と感謝のことばをヴィクトールに向けた。
もちろん、鈍感なアンジェラには、ヴィクトールが上品に散りばめた嫌味には気付いていなかったのだ。
結果的にはアンジェラの勝ちということになった。
ヴィクトールはアンジェラの笑顔を見て、一瞬ア然としたが、それから少しだけ、アンジェラにつられるように微笑んだ。
もしかしたら、こいつは思ってるほどイヤなヤツじゃないのかもな―――
ヴィクトールの微笑を見て、アンジェラはふと思った。
|
  
|
「姫、ここがハーンイシュターク城です」
銀髪の美形貴公子が、ちょうど車が城門をくぐる時に口を開いた。
「知っています。以前にも参りましたわ、私」
姫と呼ばれるハニーブロンドのウェーブヘアの少女は、その中に埋もれてしまいそうな小さな整った顔立ちで、そっと微笑む。
やっとお会いできるのですね、ヴィクトール様。ずっとこの時を心待ちにしておりましたわ。ずっと―――
「姫、はしたなきこと、決してなさいませぬよう、くれぐれもお気をつけになってくださいませ」
銀髪の貴公子が言う。
「デューク。私、そんなこといたしませんわ。婆やみたいな口はきかないで。貴方こそ、はしたないことをしないでちょうだい。伯爵でありながら、そのようなことばかり口にするんですもの。早くから老け込みますわよ」
姫はコロコロと笑った。
この姫と呼ばれる少女こそ、ヴィクトールの婚約者である、マリー=カナリスである。
そして、その横に座る銀髪の貴公子。
彼はつい数週間前にカナリス邸に現れた。デュークフリート=フォン=ラインと名乗る彼は、伯爵の爵位を持っている。
もちろん、現在では爵位など、ただの飾りでしかない。どちらかというと、爵位を持つ者のプライドの具現化した呼称というべきか。
出会って間もないが、デュークフリートは、たいそうマリーの父、カナリス元伯爵に気に入られ、今回のマリーの行動の監視役として、仕事を抜けられないカナリス元伯爵の代理として同行することになったのだ。
銀髪の貴公子デュークフリートは、マリーに負けず劣らずの美形である。
「姫のお気に召さぬことあれば、いつでもこの私め、デュークフリートにお言いつけくださいませ」
デュークフリートはにんまりと笑みを浮かべながら、マリーの顔を見つめて囁いた。
|
  
|
城に招き入れられたマリーとデュークフリートは、その足でヴィクトールに会見した。
ヴィクトールはいかにも偉そうな椅子に斜に構えている。
「君がマリー=カナリス嬢・・・ほう、お美しい方だ」
ヴィクトールもさすがに感嘆の声を洩らさずにはいられなかった。
マリーの大きなウェーブの柔らかそうなハニーブロンドとエメラルドグリーンのパッチリと見開かれた瞳には、確かにそれだけの魅力がある。
しかし、ヴィクトールはマリーを性格の悪い女と決めつけていた。マリーのその純粋な美しさを認めようとはしなかった。
すぐに意地の悪そうな笑みをマリーに向けると、紫鏡をちらりと見て言った。
「彼女はパーラジェーン。私の側使いだ。私の身の回りのことはすべて彼女に任せている。私にとって、パーラジェーンは最も大切な女性だから、君もそこのところをよく理解して、彼女と仲良くして欲しい」
「え・・・」
マリーは一瞬、目の前が真っ暗になった気がした。
ヴィクトール様の最も大切な女性?! 最も!? 彼女と仲良くして欲しい?! 仲良く!?
ヴィクトール様、それはヴィクトール様に恋い焦がれる私にとって、あまりにひどいおことばではありませんか。この日を心待ちにしておりましたのに、ヴィクトール様にお会いできるこの日を―――
マリーの頭の中はそんなことばで埋め尽くされていた。
しかし、マリーはそれを懸命にこらえると、震える声で
「わかりました」
と一言答えた。
「長旅の後ゆえ、これにて御前より失礼させていただきます」
そうことばを残し、深く一礼すると、マリーはデュークフリートを促し、部屋から憔悴した様子で出ていった。
「旦那様、悪戯が過ぎます!」
マリーが部屋から退出した後、咎めるような口調で紫鏡は言った。
「いいんだ。あれくらい言っておいたほうが、彼女のためだ。私は彼女と結婚するつもりなど、毛頭ないのだから」
「旦那様!!」
アンジェラは黙ってふたりの様子を見つめていた。
オレもよく紫鏡に叱られたな―――
ふと、そんなことを思った。
そう思うと、頭の中は紫鏡とのいろいろな思い出でいっぱいになってしまう。目の前に紫鏡がいるのに、紫鏡は今、自分の愛する女ではない。ヴィクトールの側使いである。
いたたまれない気持ちになって、アンジェラは静かに部屋を出ていった。
そんなアンジェラの背中を、紫鏡はそっと見つめていた。
|
  
|
その後、会見を退出して客室に通されたマリーはベッドに伏して泣いていた。
「あんまりです、ヴィクトール様」
私はヴィクトール様にお会いできるこの日を、ずっと心待ちにしておりましたのに。きっと約束を叶えてくださると信じておりましたのに―――
マリーの胸の内は、深い悲しみと絶望で溢れていた。恵まれ、愛されて育ったがゆえにもろい心を持ったマリーの感情は、深く暗い谷に飲み込まれてしまっていた。
どれくらい泣き続けていたのだろうか。昼食も夕食も断り、いつの間にか外はとっぷりと日も暮れて、すっかり闇のヴェールに包まれている。
泣き疲れて頭が重い。恐らく、瞼もずいぶんと腫れてしまっているだろう。
マリーはそっとベッドの端に腰掛けると、窓の外にぼんやり見える白い月を眺め、小さな、それでいて梢を揺らす初夏の風のように美しい声で、歌を口ずさみだした。
夜明けとともに 目を覚まし
マーマの腕を確かめる
木の実のスープに 焼きたてパン
マーマの愛した朝なのよ
坊や(ハニー)がいれば それでいい
マーマの愛した朝なのよ―――
マリーは何度も繰り返し歌い続けた。
それは、子守唄のようだった。
「美しい歌声ですね」
突如声をかけられ、マリーは驚き、歌うのを止めた。
声の主はデュークフリートだとすぐに判明した。
「突然レディの部屋に入ってくるなんて、失礼よ」
泣きはらした顔を隠すように、マリーは顔を逸らした。
「それは大変失礼致しました。あまりにも美しい歌声が聞こえたもので、つい」
「・・・ありがとう、デューク」
マリーは照れくさそうに微笑した。
デュークフリートはマリーの側へと静かに歩み寄ると、足元へ屈み込み、マリーのその顔を見上げて言った。
「睫毛が濡れている。泣いていたのでしょう、姫・・・いや、マリー」
とろけそうな美声。そして、耳の奥をくすぐるような囁き。
マリーは頭がボーっとなるのを感じた。
「・・・いえ、別に・・・」
「嘘をついても無駄ですよ、マリー。私にはすべてお見通しです。そう。マリー、貴女のことならば」
デュークフリートがマリーの名を呼ぶたびに、マリーは体の芯が段々と熱くなるのを感じていた。そして、それとともに、思考も段々と鈍っていく。
「マリー、可哀相に。ヴィクトールにひどい仕打ちをされたね」
「ヴィクトール、様・・・」
マリーはもうほとんど何も考えられないといった様子で、うわ言のようにヴィクトールの名を呟いた。
デュークフリートはそれを見ると立ちあがり、今度はマリーの腰掛けているベッドに、更にはマリーのその隣に腰掛けた。
「マリー、ヴィクトールが好きかい? ヴィクトールが恋しいかい?」
デュークフリートは問う。
「ヴィ、クトール・・・様ぁ・・・」
マリーは喘ぎにも似た切ない声でヴィクトールの名を呼んだ。
「そうか、彼が恋しいのだね。なんて奴だろうか、私のかわいいマリーをこんなにも悲しませるとは。マリー、そなたの望み、私が叶えて差し上げよう。ヴィクトールをそなたに振り向かせてみせようぞ。ヴィクトールは、そうだ、マリー、お前のものとなる」
デュークフリートはそういうと、にやりと笑みを浮かべた。先刻までとは明らかに表情が違う。マリーをいたわっているかのような優しい雰囲気は消え、氷のように冷たく淡々とした声になっていた。
それに気付くことなく、マリーは相変わらずヴィクトールの名を呟いている。
「今、この時より契約は執行される。手付金として、マリー、処女なるそなたの処女なるその唇をもらい受けよう」
そう言うと、デュークフリートはマリーの小さなあごに手をかけ、そのふっくらとしたこぶりの少し開いた唇に、薄い自らの唇を重ね合わせた。そして、少し長めの紅い舌を、マリーの少し開いた唇の間を縫うように口中に滑り込ませ、マリーの柔らかな弾力ある舌を絡め取るようにして動かした。
マリーに表情はなかった。
ただ、呆然と空を見つづける瞳から、たった一粒、真珠のような涙を落としただけだった。
|
 |
各章へジャンプできます |
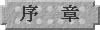 |
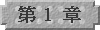 |
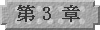 |
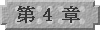 |
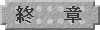 |

