紫鏡の記憶を取り戻す―――というカケをはじめて丸一日たったその夜。
アンジェラはその日一日、ヴィクトールと紫鏡にひっついて行動を共にしていたが、結局何の成果も上げられずにいた。
ヴィクトールに嫌味を言われつつ一日を過ごしたアンジェラは、精神的疲労を感じていた。
「もう、いやになるよなぁ、アイツ。なんかもしかしたら、オレすっごいイヤミを言われてたような気がするよ。それに、金持ちだって鼻にかけてるカンジもしたし・・・そんなに悪いヤツじゃないのかも、なんて思ったオレ、バカみたいだよ」
はっきりとあからさまに嫌味を言われつづけていても、アンジェラはやはりあまり気付いてはいないようだ。それでも、さすがに一日一緒にいれば、辟易してしまう。
ぶつぶつとグチをこぼすアンジェラに少々苦笑しながら、セルリアはおもむろに部屋の窓を開けた。
「あー、いい風だよー。天気もいいし、気持ちのいい夜」
少しでもアンジェラの気分を変えて、落ち着かせようとしているのか、アンジェラにそう声をかけた。
「あれ? 歌声が聞こえる」
アンジェラは言った。本当にごくごく小さな歌声。通常の人間ならば聞き取ることはできそうにない声の大きさ。しかし、人並み外れた聴力を持つアンジェラには、確かに聞こえていた。
「どうやら、子守唄のようですね」
ダイアナもそれに反応する。
「優しい声。そして、優しい歌。すごいなぁ、気持ちがいっぺんに安らぐよ」
アンジェラは先程までの疲労感や焦燥感が嘘のように消え去っていくのを感じた。
「あれ、でもこの声・・・あ! そうだよ!! 今日城に来たヴィクトールの婚約者って女の子。マリーの声だよ。へぇー、こんなに優しい歌を歌うんだ」
「じゃぁ、きっと心も優しい綺麗な女の子なんだと思うな、あたし」
セルリアもにっこりと笑って言った。
「うん、きっとそうだね。それなのに、ヴィクトールのヤツ、ヒドイこと言ってたよ、あの子に」
またヴィクトールのことを思い出して、アンジェラはひとつ溜め息を洩らした。
その時。
歌声が止んだ。
それとほぼ同じに三人は一斉に顔を見合わせた。
「このカンジ・・・」
「どうやら、紫鏡を含め、私たちがこの場に集まることになったのには、別の理由があったようですね」
「覚えてるよ、オレ。このカンジ・・・アイツと、ジゴルゼーヌと対峙した時のカンジと同じ。身の毛がよだつほどの恐怖っていうか、嫌悪っていうか・・・うん、間違いない!」
「妖魔の貴族、魔性の気配ね、コレ」
三人の体に緊張が走る。
「マリーという名の娘に、何かあったのかもしれません」
ダイアナはそういうと、アンジェラへと視線を送った。アンジェラはひとつ頷くと、部屋を後にする。セルリアも続いた。
|
  
|
その同じ時。紫鏡はヴィクトールにあてがわれていた自室で休息をとっていた。
『レイ・・・レイ・・・レイ=シキョウ・・・』
横になっていたベッドから飛び跳ねるかのごとく、紫鏡は立ちあがった。
自分を呼ぶ声。それが誰なのか、すぐに理解したからである。
「聖女王様!!」
そう、その声の主は、紫鏡たちの存在を許す世界“精霊界”の唯一絶対の存在である精霊聖女王のものだった。
紫鏡の呼びかけに応えるかのごとく、聖女王はその姿を紫鏡の前へ現した。といっても、当然実体ではないが。
「いかがなされましたか、かような場所に足をお運びになられますとは」
紫鏡は恭しく尋ねる。
『早急にそなたに伝えておかなくてはならないことがあります。レイ、近くへお寄りなさい』
少女とも女性とも形容しがたい未知なる存在である、聖女王の白く透き通るような手が、指が、紫鏡の額に触れる。
その瞬間、額に紫水晶が浮き上がり、閃光を放った。
『レイ、頼みましたよ』
そうひとことことばを残し、そうして聖女王はその姿を消した。
ひとり残された紫鏡はしばし呆然としていたが、突如ガクガクと震えだした。
「そ、そんな・・・聖女王様、これは事実なのですか!? 聖女王様が・・・そんな・・・それに、こんなこと・・・私のみならず、アンジェラまでが!? そんなことって・・・」
そう、紫鏡は完全に記憶を取り戻していた。アンジェラと再会したときに、すでに。しかし、あえてそのことを隠していたのだ。
なのに、そんな場合ではなくなっていた。聖女王が紫鏡の紫水晶を通して直接伝えたことは、彼女にとってはとてつもなく大きな事実であった。逃れられない運命の糸に絡めとられていくのを、紫鏡は今痛切に感じることになった。
「これは!!」
その時、ふいに気配を感じた。
ちょうどアンジェラたちが魔性の気配を感じた時間、紫鏡も同時に同じ気配を感じ取ったのである。
紫鏡はすぐさま気配のする方へと向かうことにした。
今は目の前にある事実が最優先、とばかりに、大きな運命への不安と恐怖心をしまいこんで。
|
  
|
こちらもほぼ同じ時刻。
ヴィクトールはいつものごとく、彼の秘密基地ともいえる屋根裏部屋でひとり、物思いにふけっていた。
「マリー嬢には少々言いすぎたかもしれないな。まさか、昼も夜も部屋に閉じこもり泣き続けているなんて。純情そうな少女だった、どこか懐かしさを感じさせるような・・・だが。だからといって勝手に決められた婚約など、私は認められない!! 彼女もそうは思わないのか? 私のことなど何も知りはしないというのに、何故簡単に婚約を承諾できるんだ。マリー嬢には申し訳ないが、何としてもこの婚約を破棄させなければ。その方が互いのためだ。本当に好きあった者同士が結ばれるのが、一番だろう」
ヴィクトールはただやみくもに婚約を反対している訳ではなかった。少々表現方法が素直ではないし、正しくもないが、自分のことだけでなく、マリーのことも考えての振舞いだった。
気性があまり穏やかではないせいで、よく嫌味な悪い奴と思われる。本人もそれはよく理解していた。だからそれを逆手にとって、周りの人間に、自分に素直に、何がやりたいのか考えて欲しいのだ。富や名声、爵位に踊らされて、ちやほやと集まる欲深い人間たちが、ヴィクトールの周りには幼い頃から大勢存在した。そして、その裏の顔を垣間見るたびに、幼いヴィクトールは心に大きな傷を負っていった。
自分のような悲しみを、自分の周りだけでも味あわせることのないように、そういつも願っているのである。
ただ、ヴィクトールは気付いていなかった。マリーがヴィクトールに恋しているということに。
そして彼の良かれと思ってとった行動によって、マリーが心に深い悲しみの色を落としてしまったことに。
ふうっと溜め息をひとつ洩らすと、ヴィクトールは座っていた椅子の肘掛に両肘をつき、組んだ手の上に顎を乗せた。
「そして、パーラジェーン・・・彼女はもしかしたら、本当はすでに記憶を取り戻しているのかもしれない。もしそうだとしたら―――なぜにそれを告白しない? 私に恩を感じているからか? 愛する男を目の前に置き、私にかしずいている姿を見るのは、私には苦痛だよ。私の心はそんな頑丈にできてはいないんだ。どうか、私に恩など感じず、もし記憶を取り戻しているのならば、正直に言っておくれ。無意識にでも口にするほど愛しい男なのだろう、彼は」
屋根裏部屋に置いてある紫鏡の大鏡を見ながら、ヴィクトールは紫鏡がこの城に現れた時のことを思い出していた。
「もう、彼の元へ戻りたくないというのならば、話は別だが―――」
美しい顔、体、声。どれをとっても一瞬で目を奪われ、心を奪われた。
「ここまできたら、後へは引けない。あとたった二日ですべてが決まるのだ。あの男がパーラジェーンの記憶を取り戻せなければ、約束どおりパーラジェーンは私のものだ。私も、いつまでも子ども時代の淡い恋心を引きずるわけにはいかないということは、充分理解しているさ。パーラジェーンなら、私のこの思いを断ち切ってくれるような気もするんだ―――」
そういってヴィクトールは少々自嘲的な微笑を浮かべた。
その時、屋根裏部屋の重い扉が音をたてながらゆっくりと開いた。
「パーラジェーンか、どうした」
声をかけながら扉へ目を向けると、そこに現れたのは、薄衣の寝巻きをまとったマリーであった。
「マリー嬢! こんなところまで何の用ですか、はしたない!」
「・・・ヴィクトール様ぁ・・・」
相変わらずマリーはヴィクトールの名をうわ言のように洩らしつづけている。その足取りもおぼつかない。フラフラと蛇行するように、それでもヴィクトールの前へと歩んでいく。
「ヴィクトール・・・様ぁ・・・」
とろんとした眼差し。少し開いた唇。揺れる大きなウェーブのハニーブロンド。あどけない顔立ちとは裏腹の官能的な表情と薄衣に包まれた肢体のすべてをヴィクトールに委ねるように、マリーはヴィクトールの胸のなかに倒れ込んだ。
「マ、マリー嬢!!」
それにはさすがにヴィクトールも驚きを隠せない。
「ヴィクトール様ぁ」
耳元で甘い吐息とともに己の名を呼ぶそのマリーの姿に、男としての欲望がふつふつと沸き上がるのを感じると、ヴィクトールは慌ててマリーを突き放した。
「マ、マリー嬢、私を色仕掛けでおとすおつもりですか、恥を知りなさい! なんて事をするんです!!」
「ヴィクトール・・・様ぁ・・・」
突き放され、ヴィクトールに拒絶されてもまだ、マリーはヴィクトールの名を呼び、そしてヴィクトールに抱きつこうとしてくる。
「いい加減にしないか! マリー!!」
ヴィクトールは怒鳴った。手を上げて彼女を引っぱたきたいところだが、そこは紳士、ぐっとこらえていた。
「おやおや、こんなにあなたに恋い焦がれている美しい少女を、むげにも拒絶されるとはあなたもずいぶんとむごい男だ」
突然の声。
驚いたヴィクトールは辺りを見回した。人の姿はない。
「だ、誰だ!!」
「ああ、失礼。私はジークフリート・フォン・ライン。先程も一度お目にかかったかと思うが―――とは言っても、すぐにお別れか」
クックックと笑いながら、ジークフリートは小さな窓の外からふわりと室内へ滑り込むようにその姿を現した。
「え、お、おい、ここは屋根裏・・・どうやってここまで・・・」
ヴィクトールの当然の驚きも、ジークフリートはまったく意に介した様子はない。
「マリー、おいで」
ジークフリートが呼ぶと、マリーは彼の元へとやって来た。
「ヴィクトール様ぁ・・・」
相変わらず、口にするのはヴィクトールの名だけである。
「クックック。困った娘だ。お前にはとうてい振り向きそうにないぞ、あの男は。それでもヴィクトールでなくては駄目なのか」
ジークフリートが何を話しかけても、やはりマリーが口にするのは恋しい男の名だけであった。
「人間の心とは、何故にここまで頑ななものなのか。愚かしいことだ」
吐き捨てるようにひとこと洩らすと、ジークフリートはヴィクトールに向き直った。
「お前はこの婚約を望まぬと聞いた。ならば、喜ぶがいいぞ。マリーは私が妃とする」
「え?」
突然のことにヴィクトールは驚いた。
突然現れた男に突然そんなことを告白されて、しかもマリーの様子は尋常ではない。そのマリーの意思はどうなっているのか、これは良いことなのか、悪いことなのか、それよりも今一体何が行われているのか、もう頭の中はめちゃくちゃになってしまっている。
「ただ、どうしても私の妃はお前が欲しいと駄々をこねるのだ。私は気に入らないが、仕方がない。お前の命を貰い受けることにしよう」
「な、なんだと!?」
何がどうなっているのかまったくわからない、が自分の命を奪う―――つまり、自分を殺そうとしていることだけは理解ができる。そんな理不尽なことが許されていいわけがない。ヴィクトールはジークフリートを睨み付けた。
「気は確かなのか? 私の命を奪おうというのか!? 冗談も大概にしてくれ」
「・・・冗談? それこそ冗談だろう。私は口にしたことは必ず実行する。マリーはどうしてもお前が欲しいと言う。だが、お前はマリーを拒んだではないか。私は妃思いでね、せめて器だけでも妃にプレゼントしてやろうと思っただけだ」
整った薄い唇を左右に大きく開いて笑みを浮かべながら、ヴィクトールを舐めるように見まわす視線に、ヴィクトールは猛烈な恐怖を感じた。
狂気に満ちていながらも、冷静な眼差し。彼が言うことは間違いない、本気で自分を殺害し、その死体となった自分をマリーにあてがおうとしている。殺される!!
ヴィクトールは体の震えを抑えるので精一杯だった。
「さて―――」
ジークフリートは一歩、ヴィクトールに近づいた。
その途端、更にヴィクトールの恐怖心が倍増する。気を失ってしまいたいほどの恐怖。
しかし、今気を失えば、自らの命は間違いなくそこで終えてしまう。そのギリギリの限界点で必死にヴィクトールは戦っていた。
「邪魔が入ったか」
また一歩、ヴィクトールに近づこうとしたとき、ジークフリートはそう口を開いて歩みを止めた。
「え・・・」
そう言うが早いか、そこでヴィクトールの意識は途絶えた。
長く続く廊下に三人の影が伸びる。
「この気配、屋根裏の方からだよ!!」
部屋を飛び出してすぐ、アンジェラは後続のセルリアとダイアナに告げた。
「そのようですね、急ぎましょう」
ダイアナはそう答えるとセルリアの手を取り、突如消える。
瞬間移動したのである。
「うわ、ちょっと待ってくれよぉーっ」
アンジェラも慌てて瞬間移動で後を追った。
|
 |
各章へジャンプできます |
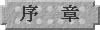 |
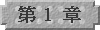 |
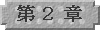 |
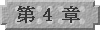 |
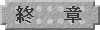 |

