「聖女王サイラ・フェアリー様、参りました」
月花城謁見の間。高いアーチ状の天井を持つ、広い広い一室。デコラティブな梁が天井と同じようにアーチを描いている。白い大理石を大きなタイル状に張り合わせた床の中央には、出入り口と玉座を繋ぐようまっすぐに紺青のカーペットが敷かれ、白い柱や壁の色の中で一際静謐さを醸し出していた。
玉座と出入り口のちょうど中ほどの位置、そこにアンジェラたち4人は膝をつき、頭を低く垂れて控えていた。
従者の声の後、衣擦れの音が聞こえてくる。それはゆっくり、落ち着いた足音と共に玉座へと近づいていた。そして、玉座の前で足音が止まる。アンジェラはまだ見ぬ女王の姿に思いを馳せた。
「皆、よく戻ってきました。さあ、顔をお上げなさい」
少女のような声に驚きながら、アンジェラはそっと顔を上げた。そして、更なる驚きを誘う。
眼前にいたのは、紛れも無く少女。自分よりもずっとずっと幼く見えた。彼女が聖女王だというのか。
サイラの姿を初めて見たアンジェラは、驚きを隠せなかった。誰からも、何も言われていなかったのだ。いったい、今何歳なのか、まったく理解できない。紫鏡たちが守護精霊になって、すでに2,000年以上が経過している。ということは、聖女王はそれ以上の年齢だというのに、まだこんなに幼い姿なのか。
実際、聖女王は即位したときから、年を取っていない。年を取らないというと語弊があるが、つまりはただでさえ長命の精霊だが、その百倍近いゆっくりとしたスピードで少しずつ齢を重ねていく。長く安定した世界を保つためにかけられた、先王の呪である。先王は比較的短命で、精霊界の行く末に不安を感じていた。幼い頃に女王の位に就かなければならなくなった自分の娘に、自分の分まで未来を託したのだ。
「聖女王様、ただいま戻りました」
四人を代表してダイアナがそう声をかける。
「ダイアナ、久しぶりですね。相変わらず曇りの無い目をしているようで、安心しました」
「……恐れ入ります」
ダイアナは再び頭を垂れた。
「そして、紫鏡。よく戻ってきてくれました」
サイラは次に紫鏡に目を向けた。
紫鏡は複雑な笑みを浮かべ、そして無言で頭を垂れる。
「セルリアも、よく戻りましたね。久しく見ない間に姉によく似て」
サイラは幼子を見るように目を細めてセルリアに声をかけた。外見ではサイラのほうがずっと幼く見えるというのに。
「自分でも最近は姉に似てきたと自覚しているところです」
セルリアははにかんだ笑みを浮かべながら答えた。
「そして……」
サイラの視線はアンジェラに注がれた。
「貴方がアンジェラですね」
「は、はいっ」
アンジェラは急に名前を呼ばれて、心臓が飛び上がりそうになった。そして、まじまじとサイラの顔を見る。水色に近い銀髪が毛先へ向かうに随って透明に透けていく。その幻想的な長髪はまっすぐ床へと伸びていた。同じように透けそうな、少し青みを帯びた肌の色。更には桜貝のような淡い薄桃色の唇。まだ十ほどの幼子のようなあどけない顔には、見慣れない金色の瞳。金色の瞳は聖女王だけが持つ、至高の瞳なのだと以前聞いたことを思い出した。着衣は白を基本としたパフスリーブ袖のドレス。胸元に編み上げられたリボンとハイウエストのつくりは『ロミオとジュリエット』のジュリエットを髣髴とさせる。
何もかもが浮世離れした姿に感じられた。まさに「おとぎの世界」の住人のようだ。今にも儚く消え去ってしまいそうで、アンジェラの胸はざわついた。
「はじめまして。精霊界へようこそ。私がこの世界の女王、サイラです」
やわらかく、サイラは笑みを浮かべて言った。
アンジェラも慌てて返事する。
「あ、アンジェラ・シェンです。お目にかかれて光栄です」
「貴方がクレアの息子なのですね。確かにクレアと同じ紫の瞳。どこか少し面影もありますね。会えてうれしく思います」
アンジェラは慌てて頭を垂れた。
「久しぶりの精霊界ですが、残念ながら皆を歓待する用意はありません。ただ、今日だけはゆっくりと時を過ごし、英気を養うと良いでしょう。部屋は用意させてあります」
サイラが言うと、侍女たちが4人を促した。
アンジェラたちは、再びサイラに頭を下げると謁見の間を後にした。
|
  
|
4人はそれぞれ個別に部屋が用意されていた。余分なものなど何もない、シンプルで落ち着いた部屋。広すぎることも無く、アンジェラには程よい空間だった。
セルリアとダイアナは、久々の精霊界で、家族の元へ出かけていった。まさに里帰りといった趣だ。紫鏡は自室にいたが、稽古をつけてほしいとたくさんの兵士に懇願され、仕方なく稽古場へ向かっていった。聖霊界一の剣士だったグリーンの唯一の弟子である紫鏡は、いまだに兵士たちの間では憧れの存在のようだった。
ひとりになったアンジェラは、時間を持て余して城内の散策でもすることに決めた。
広い回廊を抜け、目の前に開けた中庭に出る。さまざまな樹木や花々が彩る庭だ。空気はしっとりとしている。
ずいぶんと空高くにある城だけど、空気が薄く感じたりってことはないんだな。などと冷静に分析している自分に気づいて、アンジェラはふっと苦笑した。
精霊界に来ている実感がまだあまりないのだろう。それほどまでに、人間界と差異を感じることのない世界だった。
中庭にある白い円形のガゼボに人影がある。アンジェラはその小さな影に近寄るべきかためらわれた。見紛うことなく、その影とはサイラのものだったからだ。
サイラはこちらを振り向き、アンジェラを視認した。そして、微笑む。さすがに無視するわけにもいかず、アンジェラはサイラの元へと歩み寄った。
「こんな場所で何をされていたんですか?」
アンジェラがたずねると、サイラは「何も」と答え、それから
「ただ、貴方を待っていました」
と付け加えた。
「僕を、ですか?」
アンジェラは予想しなかった答えに面食らう。
「貴方と話をしたかったのです。ふたりだけで」
静かな、落ち着いた、しかしどこか寂しげな表情。ただ他愛無い話をしたいわけではなさそうだと、アンジェラは感じ取った。
「ここ、いいですか?」
そう言いながら、サイラの脇にあるベンチに腰掛ける。サイラも同じようにベンチに腰掛けた。傍から見れば、なんとアンバランスなふたりだろう。聖女王と人間とのハーフのふたり。そんな立場を無視したとしても、青く透明感のある儚げな美貌の少女と、やっと高校を卒業したかという少年とでは、やはり見た目に均衡は取れていなかった。
しばし流れる沈黙。アンジェラは何を話せばいいのかわからず、ただサイラの傍らに座すのみ。水分を含んだ空気が、ゆっくりとアンジェラの体を包み込んでいく。森を散策しているときのような、植物の生命を感じられる空気の重みだ。
森林浴をしているかのような、清浄とした気持ちになる。サイラに対しての緊張は、ほどなく解けていった。
それを見透かしたかのように、ようやくサイラはことばを紡いだ。
「今、精霊界では、ある病が流布しています。それによって、多くの者たちが命を落としているのです」
自然が豊かで、穏やかに見える森や街並みをアンジェラは思い返した。この世界では今、妖魔の侵略だけでなく、病魔にまでも脅かされているという。紫鏡の生まれたこの世界を守れるものなら、出来る限り力になりたいと、アンジェラは思わずにいられなかった。
「その病とは、精霊たちの体を腐らせる病で、初めは表皮に始まり、だんだんと内臓までを腐らせて、終いにはすべてを滅ぼしてしまう恐ろしい病気なのです。発病したが最後、治療法もみつかっておらず、ただ消滅を待つだけなのです。昔からある病ではありますが、近年富みに発病例が増えているのです。その名を「奇蝕病」といい、紫鏡の師であるグリーン・エメラルダも、この病で亡くなっているのです」
すべてを蝕み、腐らせ、消滅させてしまう病――なんと恐ろしい病なのだろうかと、アンジェラは震えた。そんな病に冒された人はどんな気持ちで最期を迎えていくのだろうか。あるいは、彼らを見守る者たちはどんな思いで彼らの最期を看取るのか。
紫鏡はどんな思いでグリーンの死を見届けたのだろうか。アンジェラは自分が一度、紫鏡の死ぬ瞬間に出くわしていたことを思い出した。そして、そのときの辛い気持ちを思い出すと、いたたまれない気がした。紫鏡も、同じように辛かったのだろうか。
「貴方には、これを見てもらいたいのです」
そういうと、サイラはふわりと軽そうな薄絹で出来たドレスの裾を大きく捲り上げ、その透き通る青白い両足を膝まで露出させた。そこには、火傷のようにただれた皮膚が大きく広がる。
「それは……」
アンジェラは恐る恐る尋ねた。
「これが、奇蝕病に冒された皮膚です」
淡々とサイラが語る。
「!!」
「私はすでに、奇蝕病に冒されています。恐らくならどんどんとこの症状は広がり、いつしか私のすべてを蝕むことでしょう。そのとき、私の治世の終わりを迎えるのです」
もう、サイラは自分の死を受け入れているようだった。その声には悲嘆も未練も感じない。
しかし、アンジェラはうろたえた。そんな重大な告白を自分が聞いてよかったのか、畏れを感じた。これは精霊界にとっての一大事のはずなのだ。なぜサイラは自分にそんなことを告白するのだろうか、と妬ましい気持ちさえしてくる。
そんなアンジェラの気持ちを見透かすように、あるいは見透かして、サイラは微笑を浮かべながらことばを続ける。
「確かに、私にとっても重大な告白を貴方に告げることは躊躇われました。しかし、貴方に聞いてもらわなければならない理由があるのです。貴方は、紫鏡のことをどのように考えていますか」
「え!?」
突然紫鏡の名前が出てびっくりしたアンジェラはすっ頓狂な声をあげた。
「紫鏡を大切に思っていますか?」
冗談や戯れではない、まっすぐに見つめる瞳。サイラの瞳を見つめ返すと、アンジェラは素直に頷いた。
「はい。何よりも、誰よりも」
「では、だからこそ、貴方に聞いて欲しい話があるのです」
ふわりと花の香りが漂う。わずかに風が吹いたのだろう。
「貴方は……紫鏡の過去について、どれほど聞かされていますか?」
「過去……ですか?」
アンジェラにとって、紫鏡は大切な存在だが、彼女はアンジェラよりもずっとずっと昔から生きていて、過去の話もたくさん聞かされた。たとえばUniteの持ち主で、紫鏡の師匠でもあり、初恋の人でもあったグリーンのこと。そして、セルリアとの出会いや交際について。あるいはシェンの村でのこと。そんなことをサイラに大雑把に伝えた。
「では、紫鏡の出生について、あるいは幼い頃のことについての話は聞かされたことはありませんか?」
「出生ですか?」
アンジェラは少し考えてみたが、そういえば紫鏡の幼い頃の話や、母親の話などは聞いたことがないことに気付く。
「全然知りません。紫鏡の小さい頃の話は、そういえば」
「そうですか……では、少し紫鏡の生い立ちについてお話ししましょう」
アンジェラにとって、紫鏡の生い立ちは、とても興味深い話題だった。それが、どんな過去なのか、まったく想像もできなかったからだ。
「紫鏡は、この城からはずいぶんと離れた辺境の村で育ちました。養い親はフルーラという妖魔狩りを仕事とする女性です」
「養い親……?」
「そうです。紫鏡はまだ乳飲み子だった時に、捨てられた子だったのです」
「!」
アンジェラは驚きを隠せない。アンジェラは、紫鏡から母親はフルーラというのだとだけ聞いていた。サイラが言うには、そのフルーラは実の親ではないという。
「母親の名はフルーラだって、紫鏡は昔教えてくれたんです」
アンジェラは悲痛な面持ちでサイラに告げた。
「彼女にとって、養い親であるフルーラは大切なただ一人の親だったのです。名も顔も、生死さえもわからない生みの親よりも、ずっと自分を立派に育ててくれた養い親に親愛の情を抱くのは当然のことでしょう」
でも――と前置きしたのち、サイラはことばを続けた。
「本当の親の存在を忘れたこともなかったはずです。フルーラやグリーンというすばらしい人たちに囲まれて過ごした幼少期に不満はなくても。だからこそ、あえてフルーラを『養い親』だとは言えずにいたのではないでしょうか」
アンジェラはそのことばになんとなく納得できた。自分も親のいない生活を送っていたからだ。紫鏡が親代わりに傍にずっといてくれたけれど、不満はなかったけれど、やはりいつも本当の親のことを考えていたからだ。
「紫鏡の生みの親は、どうしても自らで紫鏡を育てることができなかったのです」
「サイラ様は紫鏡の本当の親をご存知なんですか?」
アンジェラは驚かずにはいられなかった。
聖女王ともなれば、なんでもお見通しなのか。
「もちろん、知っています。先日、紫鏡にも話しました。どうしても今のうちに話しておかなければならなかったのです。そしてアンジェラ、貴方にも是非聞いておいて欲しいのです」
「……自分なら、紫鏡から直接聞くべきじゃないでしょうか」
勝手に紫鏡の秘密を知るのは、少々気がとがめた。
「いいえ。これは私から話さなければならないことなのです。おそらく、紫鏡も同意見でしょう」
ならば――と、アンジェラも話を聞く態勢をとった。
「紫鏡の母親の名はシキョウといいます」
「は?」
シキョウの母親の名はシキョウ? 当たり前のような、訳がわからないような話し出しだった。
「シキョウ……母親のほうですが、彼女は先王の妾でした」
「めっ妾って……つまり、愛人?」
「そうです。そしてそれは、公にされていない事実でもありました。なぜなら、彼女は先王の側使いであり、しかも一夫一婦制のこの精霊界において、あまりにも不道徳な行いだったからです」
サイラは自分の父親の話だというのに、ずいぶんと冷静に語る。それが聖女王の立場だからなのか、あるいは本当に何とも思わないのか、アンジェラには判断がつかなかった。
「シキョウは自分の妊娠を先王にも隠し続けました。病と偽り、長期の休みを取って人目を避けたまま、ひっそりと子を産み落としたのです。先王の子を堕胎することは、到底考えられないことでした。私利や権力ではなく、彼女は本当に先王を愛していたためでした。私は先王の娘でありながら、公にできずにひとりですべてを隠し通そうとしたシキョウに心惹かれました。妾という存在であることを知っていながら、私は母親よりも彼女を慕いました。母親にとっては、裏切られたと感じたかもしれません。あるいは、母親もシキョウを不憫に思っていたのかもしれません。私が彼女の元へ行くことを咎めも認めもしませんでした。ただ無関心を装っていました。それは、王の后としてのプライドだったのかもしれませんが。そのため、私はシキョウの元へ足しげく通うこともできたし、事の顛末を把握することもできました」
ふわりと風が吹き、また花の香りが鼻先をくすぐった。シリアスな雰囲気を少しだけやわらげてくれたような華やかな香りだった。
「シキョウは子を産み落とすと、愛しそうに子をみつめ、そうして祝福の口づけを送りました。最初で最後の親としての精一杯の愛情を与えたのです。私を立会人として、シキョウはわが子に名をつけました。レイ、それはシキョウが、産みの親がつけた名なのです」
紫鏡の名がレイということは聞いていた。麗という字を当てていることも知っている。紫鏡にふさわしい名だと思っていた。それは産みの親が愛情を込めてつけた名だったことを知り、アンジェラは胸が熱くなった。
「その後、シキョウは入念に里親を探しました。愛する子を預けるに足りる親を。王に気取られることなく、育て上げることのできる親を。そうして見つけたのがフルーラだったのです。シキョウは自分では名乗らず、ただフルーラにレイを託しました。フルーラはシキョウが思ったとおり、立派にレイを育て上げたのです」
サイラがふと微笑んだのを、アンジェラは見逃さなかった。サイラは本当に紫鏡の母親のことを好きだったんだと感じた。きっと、すごく素敵な人だったのだろう、素直にそう思えた。
「でも、ということは……」
紫鏡の生い立ちを聞いたアンジェラは、その事実に気づかずにはいられなかった。
「そうです。レイは私の異母妹です」
なんということだろう。聖女王の腹違いの妹だなんて。アンジェラは思いもよらなかった事実にめまいを起こしそうだった。それを、紫鏡はつい最近知らされたという。そんな素振りを全然見せていなかった、自分が気づかなかったことに、ますます驚愕する。
「私はレイが初めてこの城へやってきたときに、それがシキョウの娘であることにすぐ気づきました。そして、再会した義妹を愛しくも感じました。その内に秘めた力の強さもさることながら、私に残された最後の血縁でもあったのです。そう。私とレイのほかに、血を分けた者はすでにこの世にはいませんでした。だからこそ、彼女を立派に育て上げたいと思ったのです。彼女は見事に私の期待以上のすばらしい精霊へと成長しました。そこで私は、彼女にシキョウという名を与えたのです。母親と同じ名を」
長い時間が経過していた。あたりは夜の帳に覆われ始める。
アンジェラはサイラから語られる、秘められた真実に、ただ耳を傾けるしかなかった。何も発することばがない。頭の中では話を整理するだけでいっぱいいっぱいなのだ。
「先ほども話しましたが、私の寿命はまもなく尽きようとしています。つまり、私の跡を継ぐ者が必要になるのです。もう分かりますね」
「え……じゃぁ、紫鏡が次の……」
「私はそう考えています。そして、恐らくなら誰もがそれを認めるでしょう」
紫鏡が次の聖女王となる――、アンジェラは足元から崩れ落ちそうになるのを懸命に堪えていた。自分の彼女が精霊だってことだけでも尋常じゃない。自分が半分精霊だってことにようやく慣れて、紫鏡のことを守ろうと決めて間もないのに。彼女はまるで手の届かない空に上る太陽のようだと思った。決して近づけない人。
「私が、貴方に私から話すべきだと思ったのは、こういう理由からです。貴方には、覚悟が必要だと」
「……覚悟……ですか?」
「そうです。貴方はレイを大切に思うと言ってくれました。何よりも大切だと。ならば、レイと共にいて欲しいのです。レイの傍に」
「……どういうことでしょうか?」
「つまり、聖女王に即位したレイの伴侶として、彼女を守り、支え続けて欲しいということです」
「はっ、伴侶!! ですか!?」
いつまでも傍にいられたら――と、確かにそう思っていた。しかし、結婚という儀式は、成人もしてない自分にはまだまだ遠い話のように思っていた。しかも、聖女王の夫だなんて。
「どうですか、アンジェラ。貴方にその覚悟ができますか」
アンジェラは考えた。自分が夫になるということではなく、紫鏡のことを。彼女が一度この世から姿を消してしまったときの喪失感、悲しみ。そうして彼女が復活したときに感じた喜び。決して離れないと誓った想い。形式はどうでもいいことだと思った。ただ、彼女の力になり、彼女と共に歩んでいきたい。純粋にそう思った。
「自分は、ずっと紫鏡の傍にいたいです。彼女を支えていきたい」
混乱していた頭は靄が晴れるように、すっきりと軽くなった。アンジェラの視線も、まっすぐとサイラをみつめる。
サイラは柔らかに微笑む。
「貴方ならそう言ってくれると信じていました。では、アンジェラにはまず、クライスター家の家督を相続してもらいます」
「え?」
突然の家督相続命令。アンジェラには理解できないことがまたひとつ。
「貴方には、クレアの息子として、正式にクライスター家に入ってもらいます。聖女王の伴侶として、せめてふさわしい家柄を継いでもらわなければ、民が納得しないでしょう」
「はあ」
そんな簡単にクライスター家の一員となれるのだろうか? 貴族というからには、それなりの誇りやこだわりがあるんじゃないのか? アンジェラは不安になった。
「不安に思うのも無理はありません。ですが、大丈夫ですよ。その辺はセルリアがうまくやってくれていることでしょう」
サイラがいたずらっぽい笑みを漏らした。聖女王でもそんな顔をするのかと、またしてもアンジェラは驚かされた。
|
  
|
そうして、城にやってきた迎えの者に連れられて、アンジェラはクライスター家へ訪れることとなった。屋敷の前にはセルリアが待っていた。
屋敷へ迎えられると、セルリアの両親は「クレアに面影が」などと感慨深げにアンジェラを歓迎し、孫の存在を自然に受け入れてくれた。
アンジェラは初めて現れた自分の祖父母にただ戸惑うばかりだったが、それはどこか懐かしく、安らぐ時間でもあった。
のちに、アンジェラは正式にクライスター家の血族と認められることとなった。
|
 |
各章へジャンプできます |
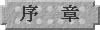 |
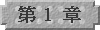 |
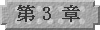 |
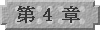 |
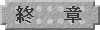 |
「紫鏡」シリーズ
TOPへ
 |
|
|
|
|
 |

