翌日、謁見の間には多くの守護精霊が集められた。アンジェラが今まで会ったことなどない多くの精霊たち。
こんなに多くの守護精霊がいるのかと、アンジェラは驚きを隠せない。その数、百余名といったところか。もちろん、その中には昨日会ったヴェールもいた。
ほとんどの守護精霊は女性が占めていたので、ヴェールの存在は明らかに目立つ。つまりはアンジェラも同じくらい、あるいは見知らぬ者という立場もあり、ヴェール以上に目立つ存在だということに、アンジェラはまだ気づいていなかった。
「聖女王サイラ・フェアリー様、参りました」
その声と共に、謁見の間に控えるすべての精霊たちが頭を垂れた。アンジェラももちろん、それに倣う。
「皆の者、面をあげなさい」
サイラの声が凛と響いた。その声に合わせてみんなが顔を上げる。
「守護精霊という役目、長くご苦労様でした。よもや皆が再び精霊界へ戻ってくることになるとは思いもしませんでしたが、これは喜ばしいことではありません。事態はそれほどまでに深刻なのです」
そう前置きして、サイラは事の詳細を語り始めた。
精霊界を取り巻くリアンの森の西部、グリーンが守っていたエンドフォレストの周囲には、侵入してきた妖魔たちが跳梁跋扈しているということ。今では森は枯れ、近くに暮らす民は殺され、紫鏡が修行をしていた頃の美しい森の面影は微塵もない。そして、妖魔たちはさらに勢力を拡大し、どんどん精霊界へ侵入し続けている。妖魔ごときなら、守護精霊までの高格精霊でなくてもいくらでも凌げようが、実はそれらを使い、操る妖魔の貴族である魔性までもが精霊界へ入り込んでいるというのだ。魔性の力は並大抵のものではない。高格精霊でさえ、油断をすれば一溜まりもないほどの力を持っている。その魔性が、一人ならず、何人か入り込んでいるという情報だった。ゆえに、事は重大性を帯びたのだ。
もはや、精霊と妖魔の全面戦争という態である。
「貴方がたにばかり、苦労をかけますが、この世界を守るために、重ねて願うのです。妖魔や魔性をこの世界から排除しなさい。それが貴方がたの新たな任務です」
辛そうなサイラの表情。どれだけの試練か理解しているからこそなのだろう。ただ軽々しく命令しているわけではない。それだけに、精霊たちにも自ずと真剣さが増していく。
「この戦いにおける参謀として、レイ・紫鏡を任命します。皆の指揮を取り、迅速に処理しなさい」
「はっ」
紫鏡は姿勢を正して短く返答した。誰も異を唱える者はなかった。それだけ、紫鏡の強さは認知されているのだ。サイラの寵愛を受ける、グリーンの秘蔵っ子という色眼鏡さえ、打ち砕くほどに。
|
  
|
紫鏡は、ダイアナとセルリアを補佐として策を練ることにした。冷静沈着で視野の広いダイアナと自由奔放で柔軟なセルリアの意見は、時として紫鏡には思い浮かばない良策や奇策を捻り出す。そして共に過ごした時間の長さ、濃さからも、何よりも信頼できる相手である。これ以上素晴らしい補佐はいないだろう。
アンジェラは精霊界の地理も、あるいは戦術なども、何も知らない、つい先日まではただの高校生だったので、ただ三人とそれを取り巻く高格精霊たちの話を遠巻きに見ていることしかできなかった。
何もすることがないとなると、余計なことばかりが脳裏に浮かぶ。
紫鏡が聖女王の妹ということは、聖女王の親戚筋だというダイアナ様にとっても、紫鏡は親戚になるのかな? 聖女王の母方の親戚だったら、他人かな?
くだらないことを考えて、詮無いことだと苦笑する。
「ぐずぐずと策を練るよりも、まずはエンドフォレストへ赴いたほうがいいんじゃないか」
ヴェールの少し大きな声が響く。
「偵察に出る程度ならかまわないかもしれませんが、無駄に戦地へ赴いては、負傷者を出すだけではないですか? それでは、戦力を大幅に減衰させてしまう惧れがあります」
ダイアナは言う。
紫鏡は思案した。
ふたりの意見は対照的だった。思慮深く、二重三重に安全策を考える慎重派のダイアナと、当たって砕けろタイプのヴェール。多くの者を従える立場としては、ダイアナの意見が正しいと思うが、ヴェールのような熱い存在は、他者を惹きつけるところがある。
少々無鉄砲だった少女時代の自分を思うと、ヴェールの意見もよく理解できた。何より、場所はエンドフォレストなのだ。グリーンが守っていた森。それが妖魔に占拠されていると考えると、兄を慕うヴェールの我慢がきかないのだろう。本当ならば紫鏡だって、すぐに飛んでいきたい。自分で妖魔を蹴散らして、あの美しかった森を取り戻したかった。
だが、自分の立場を考えるとそれはまかり通らない。聖女王ならなんと言うだろうか。
最近は、自分が何かをするときに、聖女王のことを考えるようになった。彼女はどうするだろうか。
それは紫鏡の中で起きた、新たな変化だった。聖女王の後継者としての自覚を持ち始めたのかもしれない。あるいはただ単に姉という存在への思慕か。
しばし思案の末、出した結論。
「やはり、エンドフォレスト周辺の様子を知る必要があります。まず状況を把握してから、確実に勝利する道を選ぶべきだと私は思います」
概ねダイアナを支持する形となった。
「そして、その斥候隊長に、ヴェールを指名します。現状を具に偵察し、情報を確実にこちらへ届けて欲しいのです。くれぐれも、無茶をしないように」
紫鏡が考えうる最上の答えだった。エンドフォレストへ行きたいヴェールの気持ちを尊重しながら、戦いに勝利するための情報を得る。一挙両得とはいかないが、ふたりの意見をなるべく尊重できたのではないか、と。
「セルリア、貴女は何も意見してないけど、それでいいかしら?」
紫鏡はセルリアの表情を盗み見た。
「あ……うん。そう、ね。それがいいんじゃないかと、あたしは思う」
歯切れの悪い答え。紫鏡の心に不安がよぎる。自分は間違えた選択をしただろうか、と。
しかし、他に反対する者も、別の意見を述べる者もなく、紫鏡の案を受け入れることとなった。
|
  
|
「セルリア、ちょっといいかしら?」
月花城にあてがわれたセルリアの部屋の前。扉の外から紫鏡が声をかける。
「紫鏡? どうしたの? どうぞ入って」
いつもと変わらぬセルリアの明るい声。自分の心配のしすぎだろうか、紫鏡は思った。
今朝早く、ヴェールは数人の供を連れてエンドフォレストへと向かった。
見送るものもなく、静かな出発だった。紫鏡だけが、彼らの出発を見守ったのだ。
斥候隊は、ある種非常に危険を伴う。セルリアの元婚約者であるヴェールが戦地へ赴くのを、セルリアは不安に思っていないだろうか、と紫鏡は心配しているのだ。
扉が開いて、紫鏡は部屋に通される。そこには笑顔のセルリアがいた。
「どうしたの? 紫鏡。なんだか変じゃない?」
「セルリアに聞きたいことがあって……」
紫鏡はどうやって話し出すべきか、考えあぐねていた。
「立ったままもなんだから、座ったら?」
セルリアに促されて、セルリアの向かいの椅子に腰掛ける。そして、セルリアの顔を見た。正面からまっすぐと。そこで、セルリアの笑顔に揺らぎを見つけ、自分の疑問をセルリアにぶつけることに決めた。
「セルリア、あなたに聞きたいことがあるの」
真面目な紫鏡の表情に、セルリアは笑顔を消しはしなかった。はかない笑顔を顔に乗せたまま紫鏡を見つめる。
「セルリア、あたしは間違ってないわよね?」
「急に何よ? 何を間違うっていうの?」
唐突な紫鏡の言葉に、セルリアは面食らった。そこに素のセルリアが現れる。
「ヴェールを斥候隊長に任命したこと、今回の作戦、あたし間違ってないわよね?」
じっとセルリアの顔をみつめる。セルリアは一瞬ハッとした表情を浮かべ、それから少し目を伏せて、紫鏡の視線を避けた。
「・・・・・・間違ってなんか、ないよ。今の時点で最善の策だと、思う」
「じゃあなぜ、そんなに浮かない顔をするの、セルリア」
「え」
セルリアが一瞬紫鏡を見た。目が合った瞬間、また視線をそらす。普段のセルリアには、到底ありえない行動だった。彼女はいつでもまっすぐ相手の目を見て、視線をそらすことなどないのだ。
「セルリア、あなた本当は今でもヴェールのことを……」
「やめてよ」
紫鏡が言いかけるのを、セルリアが止めた。
「やぁねぇ、そんなワケないじゃない。あいつが城からいなくなって、せいせいするわ」
セルリアはそう言うものの、その憎まれ口の裏に見えるセルリアの本心を、紫鏡は見逃せなかった。
「ねぇ、無理しないでよ、セルリア。私の前で、そうまで自分を偽る必要があるの? 私たち、親友でしょう?」
紫鏡は居たたまれない気持ちになった。
「紫鏡ってば、心配性なんだから」
なおもセルリアは自分を偽りおどけてみせる。
「セルリア!」
紫鏡は声を荒げた。
紫鏡の声に、セルリアは瞬時体をすくめる。そしておもむろに深いため息を吐くと、ゆるゆると言葉を洩らし始めた。
「仕方ないのよ……紫鏡は間違ってない。あの場合は正しい選択だって思ってる。それで駄々をこねたりしないわ。アイツにとっても、それが最適だったはずだもの」
伏し目勝ちなセルリアに、いつもの明るい表情は戻ってこない。
「それに……婚約解消した相手だもの」
吐き捨てるような言葉。
「セルリア……」
紫鏡は悲しくなった。セルリアは、ずっとヴェールのことを想っていたのだ。親が決めた婚約者だったはず。それでも交流の深い両家だから、きっとふたりが幼い頃から、よく共に時間を過ごしていたことだろう。初めは形だけの関係が、ふたりが年を重ね、少しずつ成長していく中で、実を伴っていったに違いない。
守護聖霊になることで、姉を失い、紫鏡と別れ、更には愛すべき婚約者とも離れなくてはならなくなったセルリア。
明るく振舞うその強さは、紫鏡には絶対に真似のできない、セルリアの強さだった。
セルリアは強い女性だと改めて感じる。
それなのに。
強いセルリアがその仮面を落としてしまう程に動揺しているのは、それだけの危険がヴェールを取り巻いているからだ。自身、使命と愛情の板ばさみに苦しんでいるからだ。
大切な友を苦しめることしかできない自分に、紫鏡は嫌悪した。
「セルリア……」
ことばが見つからず、紫鏡は再び口を閉ざした。
「この話はもうヤメにしよ。不毛だわ。どうしようもないことだもん」
セルリアが顔を上げてにっこりと笑う。
この強さだ。自分にない強さ。セルリアには、いつまでも敵わない。紫鏡は苦笑するしかなかった。
|
 |
各章へジャンプできます |
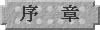 |
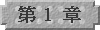 |
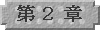 |
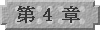 |
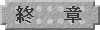 |
「紫鏡」シリーズ
TOPへ
 |
|
|
|
|
 |

