ヴェールが単身魔性の元へ乗り込んでいったとの知らせの後、セルリアは勝手に飛び出して、ヴェールの元へ向かっていた。気付いたら、体が勝手に動いていたのだ。自分でも驚いてしまう。
こんなときに、アンジェラや紫鏡がいれば瞬間移動で追っていけたのに……
そう思っても、いてもたってもいられなかったのだ。今更そんなことを思っても後の祭りというものだ。
高速艇を利用して、リアンの森へ向かう。瞬間移動には敵わなくても、全速ならかなり短い時間で移動できるのだ。もちろん、通常は全速で飛ぶことも、気軽に乗ることもない、特別な飛行艇であるのだが。
「ヴェール……無事で……」
セルリアは祈るしかなかった。
紫鏡は、緊急召集会議を開いていた。
斥候隊の報告では、ヴェールは到着してすぐに魔性のいる場所を見つけ出し、単身乗り込んだというのだ。
それはリアンの森の滝の近くにある建物だと言っていた。
紫鏡にはすぐにそれがグリーンが、そして自分が住んでいた家だとわかった。ヴェールにしてみれば、最愛の兄の思い出の家を汚されることなど、きっと我慢できなかったのだろう。
「こういう事態になってしまったのは、私の責任です。事は一刻を争います」
険しい表情を崩さずに、紫鏡は言う。
「ヴェールとセルリアの救出には、私他、ダイアナ様、アンジェラが向かいます。実戦に長けた者は、同行してください。途中、他にも妖魔がどれだけ潜んでいるのかわかりません。戦いを不得手とする者は、二手に分かれ、現地付近で傷ついた者の回復をする救護班と、状況をつぶさに集約し、どんな状況になっても咄嗟の判断を取れるニュートラルな位置付けのグループとして、バックアップをお願いします。城への連絡を密に、連絡を怠ることのないよう、お願いします」
それだけを一気に告げると、紫鏡は大きな息をひとつ吐いた。
わずかなざわめきはあったものの、事の重大さを理解する守護聖霊というエリート集団ゆえに、混乱はないようだった。きりりと空気が引き締まっていく。
アンジェラは、その只中で全体を束ねる紫鏡を見て、頼もしく思えた。自分が守ると決めていても、実際紫鏡に守られることが多い現実がある。素直に尊敬しつつも、自分ももっと強く、紫鏡を心から支えられる男にならなくてはと、決意を新たにしていた。
「エンドフォレストへ向かいます!」
紫鏡の声が響いた。
|
  
|
他の守護聖霊たちよりも一足先に、紫鏡、アンジェラ、ダイアナはエンドフォレストにあるリアンの森までやってきていた。一時戦闘指揮は別の者に託してある。とにかく戦いの活路を見出すためにも、先陣を切る必要があると感じていたからだ。もちろん、セルリアやヴェールの安否が気になるということもあった。
紫鏡がかつて修行していたリアンの森は、明らかに変貌していた。あんなに神に祝福され輝いていた緑は、枯れ、くすみ、うなだれている。生き物たちの気配はすっかりと消えてしまっている。
「……」
紫鏡はその惨状にことばもなかった。
「まるで死の森だな……」
アンジェラがぽつりと洩らした。その表情は憐れみに満ちていた。
感傷に浸っている場合でないことは、わかっていた。しかし、グリーンと過ごした満ち足りた日々が、紫鏡の脳裏に一気に湧き出して、理性で簡単に消し去ることはできなかった。
しばし、呆然と立ち尽くす。
「この森を、元の美しい森へ戻したいですね」
ダイアナが言う。紫鏡はハッと我に返った。そうだ。感傷に浸っている場合ではないのだ。妖魔を倒し、本来の美しい森を取り戻さなくては。
「道案内は私に任せて。二人とも、行くわよ」
しっかりとした口調で告げる紫鏡に、二人は頷いた。
|
  
|
外観は、それほど大きい建物ではなかった。木造の、質素な家である。屋根もヨーロッパの町並みで見かけるようなレンガ屋根だ。暖かみのある家。それがグリーンが晩年過ごしたリアンの森の住まいだ。
セルリアがこの建物を目にしたのは、これが初めてだった。いかにもグリーンが好みそうな造り。
意を決して扉を引くと、それは容易に開いた。
「!」
そこは、想像していた内部とまったく違う。
目の前に広がるのは奥へ奥へと続く歩廊だった。
魔性の魔力によって、内部の空間は大きく変化していた。恐らくなら自分好みの城を、歪めた空間の中に作り上げているのだ。以前ドイツで対峙した魔性・デュークフリートと同じように。それは、魔性の完全なるテリトリーであり、侵入者は明らかに不利な立場である。聖霊界にいようとも、それは変わりない。
セルリアは、ためらわなかったわけではない。しかし、ヴェールの安否が気になればこそ、ここで留まるわけにはいかなかった。
意を決して、足を踏み入れる。
すると、途端に背後で扉が閉められた。もちろん、誰かがそこにいたのではなく、扉が自らセルリアを閉じ込めたのだ。もう逃げ場は無いと言わんばかりに。
固唾を飲んで、それでもセルリアはまっすぐ奥へ続く廊下を走り出した。
真っ白な歩廊。天井も壁も床も、等間隔で置かれた燭台も恐らくならすべてがアラバスターでできているようだった。純白の空間に、走り抜けるセルリアの影だけが黒い。
普段はどちらかといえば明るい色彩に包まれていて、光のようなイメージを受けるセルリアだが、純白の空間に置かれると、自分がほの暗い存在のように感じてしまう。自覚したことのない、不思議な感覚だった。
実際、このときのセルリアの精神状態は、とても不安定で焦りばかりが渦巻いていたので、余計にそう感じたのかもしれないが。
歩廊は、まっすぐと伸びていた。つまりは、中心部へ向かってまっすぐと誘われているのだと理解できた。
ダイアナなら罠だと言うだろう。賢明な行動でないことは重々承知だった。しかしセルリアには、回りくどく外堀から埋めていく時間を待つことができなかった。
変わり映えのしない景色に少々苛ついた。もう、ゴシック建築の彫刻で立体的に掘り起こされた燭台の細部まで子細に記憶してしまった。脇に逸れるような扉も存在しないこの廊下は、もしかしたら無限に続くのではないかと感じ始めた頃、ようやく先に終点が見える。
セルリアは、あと数歩というところまで駆け寄ると、いったん歩を緩めた。どれだけ走ろうとも、息があがるようなことはないけれど、焦燥感でいっぱいの気持ちを少し落ち着けたかったのだ。気付けば握り締めた手のひらには、汗が浮いていた。
「ふぅぅぅぅ」
息を大きく吐き出し、少し心を鎮める。それでも緊張で脈拍が上がるような気がした。
覚悟を決めると、セルリアは目の前に大きくそびえる扉を押し開いた。
「ようこそ。招かれざる客人」
セルリアが部屋に入った途端風が吹き抜け、それに乗って声が届く。
声の主を見やると、部屋の少し奥に浮かぶ椅子があり、それに腰掛ける女性の姿があった。
無造作にカールさせた毛束を自由に散らし、軽やかな雰囲気をかもし出した白髪のロングヘア。印象的な長い首に乗る小さな頭と、華奢な体型に似合わないほどの胸のボリュームは、現実感を感じられないほどだった。まるで少年漫画の登場人物のようである。
首や鎖骨に伸びる紐は胸元へと結ばれ、肩を露出したイブニングドレスのような薄い布地がスレンダーでグラマラスな体型を浮き彫りにしている。椅子に組んだ足は太腿の際まで露わになっていることを見ると、サイドスリットが深く切り込まれていることがよくわかる。
髪も肌も服も白く、室内も白。恐らく魔性の四天王なのだと、セルリアはその時直感した。
「ようこそ。招かれざる客人。もう少し近くまで寄ってはいかがか」
再び、声をかけられた。やはり、風が吹き抜けていくようだった。
セルリアは一歩前に出た。
「招かれざる客は、本来あなたのほうでしょう? ここは、あなたの世界ではないし、あなたの家でもない」
いつになく厳しさを伴ったセルリアの声が響く。
「ふふふ。確かに、言われてみれば道理。では改めよう。ようこそ。間もなく死に行く客人よ」
魔性の女は大きな口を左右に広げ、いやらしく笑った。
「我が名はセレレイト。四天王がひとり。光栄に思うがいい」
セレレイトは、魔性の四天王のひとりであった。赤き炎のジゴルゼーヌ、青き氷のデュークフリート、黒き闇のアポストフと肩を並べる魔性の中の魔性。冠名は白き風のセレレイトだ。
「四天王のひとりが、わざわざこんなところまで足を運んでくるなんて、ご苦労様ね。でも、間もなく死に行くなんて決め付けられても困るわ」
セルリアは、少し肝を据えたのだろうか、いつものコミカルな雰囲気を取り戻しつつあった。もちろん、気を緩めているわけではなく、いつも以上に神経は集中していた。
「ねえ。とりあえず彼を返してもらいたいのだけど、どこにいるのかしら」
「彼……? ああ、もしやあのうるさい緑髪の男のことか?」
セルリアの問いかけに、セレレイトは少し思案顔を見せて言う。もちろん、それは芝居であって、当然セルリアの言わんとしていることは、理解していた。魔性は基本、すべてを戯れにしてしまうものだ。真剣になることも、感情的になることも、格好悪い行為と思っている。余裕こそが、彼らの美徳なのだ。もちろん、通常は圧倒的な力の差で、真剣になる必要などないのだが。
「彼なら、そら」
セレレイトが視線を斜め上に逸らした。セルリアが視線をたどると、視線の先にあったのは、丸い球体のようなものだった。
丸い球体に見えるそれは、なにやら表面に動きを見せているように思えた。
怪訝な表情でもう少しよく観察すると、それは風が渦巻いたもののようだ。
外側と内側で風の向きが違う。速度も違う。恐らく何重にも方向と速度の違う風が取り巻いているのだろう。外側は、風が風を相殺しているからか、騒音を嫌うセレレイトの作り出したものだからか、風音がしないようになっていた。だから静かで気付かなかったのだろう。風でできた不思議な玉。
その風の玉の中心に、影が見えた。
それは、見まがうこと無きヴェールの姿。
「!!」
セルリアが息を飲む。
風の玉の中心は、恐らく渦巻く激しい風でできているに違いなかった。その中で苦しみ顔を歪めているヴェールの姿が見えたのだ。
それでも、外へその声は届かない。音声を消してしまったテレビ画面に映し出された映像のようだった。
「ヴェール!」
セルリアが悲痛な声をあげる。それは、セレレイトにとって極上の調べ。セレレイトは恍惚の表情を浮かべた。
「良い声だ。私はその声を聞くと体中が喜びに震えるのだ。くくく」
セレレイトが言い終わらないうちに、セルリアはセレレイトを睨みつけた。
「彼を解放して」
はっきりとした口調で、セルリアはセレレイトに告げた。
「別に開放するのは構わないが、開放することで私に何かよいことでもあるだろうか。私は自分にメリットの無い願いを聞いてやるほどお人よしではなくてねぇ」
すまし顔のセレレイトは、意地悪く応える。
「あのうるさい男がどうなろうと私の知ることではないが、タダでくれてやるのも惜しいのだ。私は欲深い女なのだよ」
ふふふと小さく笑みを洩らしながらセレレイトは言う。
「さて。女。お前は代わりに私に何をくれる」
交換条件を提示しろと告げられ、セルリアは困ってしまった。セレレイトに替わりに渡せるものなど、何もない。自分の身ひとつでやってきたのだ。
「……」
「そうだ」
セルリアが答えに窮しているとセレレイトが明るい声をあげた。
「女、水晶を持っているな。その美しく大きな水晶を私にくれるなら、あの男を解放してもいいぞ」
口の端を大きく歪ませてセレレイトが言う。
セレレイトには、わかっているのだ。水晶がセルリアの命であることを。わかっていて、わざわざもったいぶって、そう告げる。
「どうする、どうしたい。自分とあの男とどちらを取るか」
セルリアを凝視して目線を逸らすことなく、セレレイトは畳み掛ける。
デュークフリートと対峙したときに、痛いほど理解していた。トップクラスの魔性には、セルリアひとりで到底敵わないということを。
頭上で囚われているヴェールを見遣り、セルリアは覚悟を決めた。
「わかったわ。水晶と交換で、ヴェールを解放して」
その途端、セレレイトはニタリと笑い、ヴェールが囚われている風の檻を地上まで降ろした。
「いい心がけだね。じゃぁ交渉成立ということで、この男は解放しようではないか」
セルリアから水晶を渡される前に、ヴェールを解放しようと言う。当然だった。セレレイトは圧倒的な己の力の優位を感じていた。そして、ここはセレレイトの作り出した空間であり、セルリアが簡単に逃げ出せないこともわかっていた。さらに言うなら、ヴェールとセルリア二人がかりでも、セレレイトは負けない自信がある。しかも、ヴェールはすでにかなりのダメージを受けているのだ。
風でできた不思議な玉が、不意に解ける。風が静かに消え去った。
中で囚われていたヴェールが崩れ落ちるように地に臥す。
「ヴェール!」
セルリアはヴェールに駆け寄った。
ヴェールは、小さくうめき声をあげた。
「……す、すまない。君を巻き込むつもりは……なかったの、に……結果、こんなことに……なってしまっ……て」
セルリアが首を横に振る。
「いいのよ。いいから。もうしゃべらないで」
ヴェールの体を抱き留める。
「感動的な再会だこと。私はなんて優しいんでしょうね。感謝しなさい」
セレレイトは恩着せがましく口を挟んできた。
「さてと。そろそろいいかしらねぇ」
ヴェールを解放し、セルリアとヴェールのドラマを見物して満足したのだろう。セレレイトは、退屈そうにあくびをして見せた。
途端、セルリアの体が緊張する。絶体絶命だと感じたからだった。
セルリアは小さく息を吐くと、覚悟を決めて立ち上がった。
ほとんどまともに動けないヴェールは、セルリアの足元から彼女を悲しげにみつめていた。
セルリアはそんなヴェールの顔を見ずに、セレレイトにまっすぐ視線を合わせる。
ゆっくり、ゆっくり、一歩一歩セレレイトの元へと歩んでいく。
セレレイトは、舌なめずりをしながら愉快そうに笑みを浮かべていた。焦らされることも、楽しみのひとつと思っているのだろう。
そして、セレレイトの元まで歩んでいくと、セルリアは立ち止まる。
「さあ、水晶をいただきましょう」
セレレイトがひと際大きく笑みを浮かべる。
目を瞑りふぅーっと大きく息をひとつ吐くと、セルリアは自らの手を耳に飾られた大きな水晶のイヤリングへと伸ばした。
「ほぅ。長く遊びすぎたか。助っ人が登場のようだ」
セレレイトは、顔をしかめた。
|
 |
各章へジャンプできます |
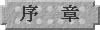 |
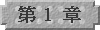 |
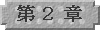 |
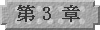 |
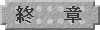 |
「紫鏡」シリーズ
TOPへ
 |
|
|
|
|
 |

